クレア・ビショップの『インスタレーション・アート:批評的歴史(Installation Art: A Critical History)』(2005)*1の各章を簡単にまとめました。本書の美点は、以下に紹介する記述の部分だけでなく、多くのカラー図版が収録されている点にあります。また、以下の要約でも多くの作品・議論は省略しました。各章の概略と、読むときの手がかりを提示したつもりです。引用は大岩による訳です。
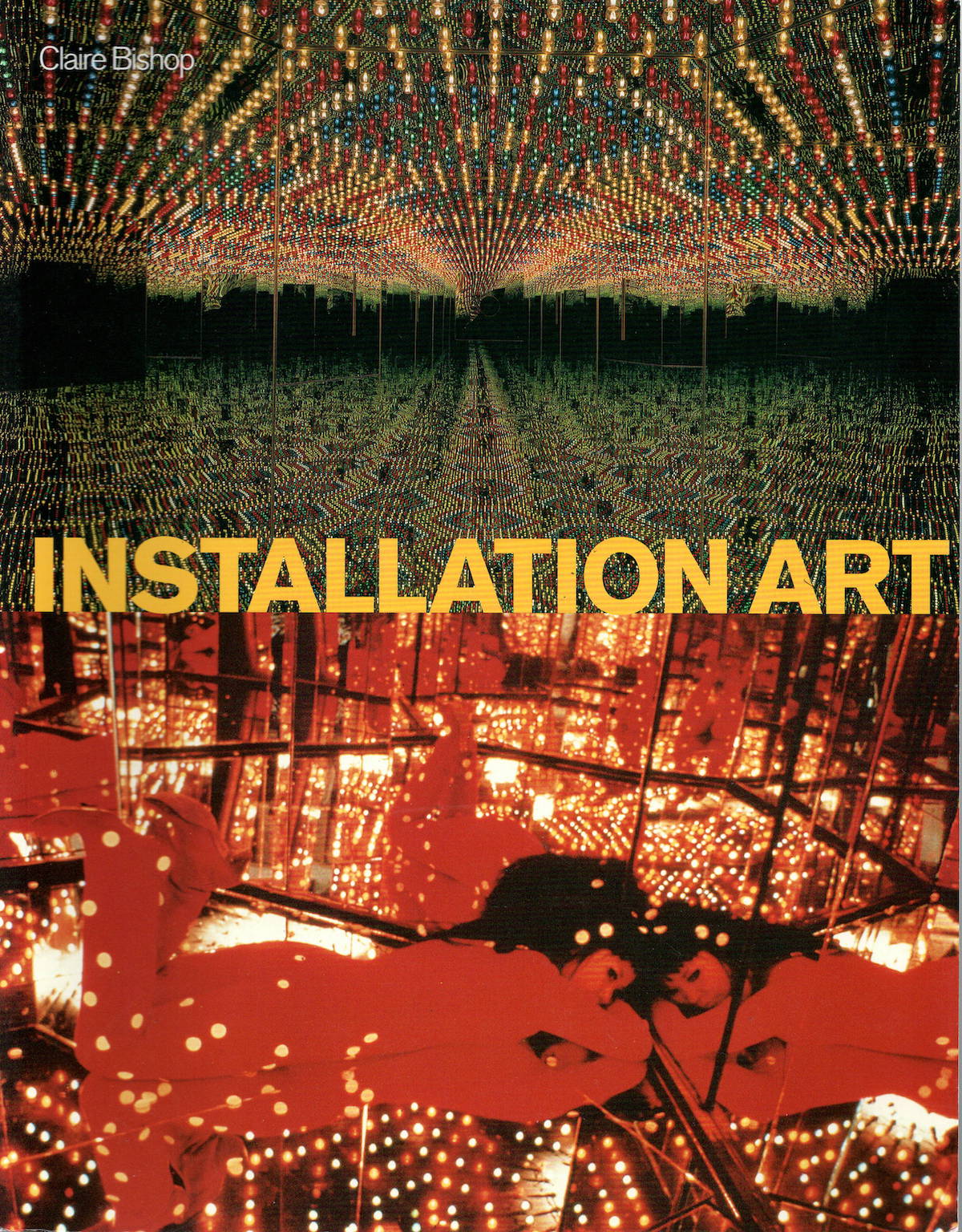
書影
0.全体像
本書は題のとおり、インスタレーション・アートの批評史をたどるもので、古くは、エル・リシツキーやクルト・シュヴィッタース、マルセル・デュシャンら1920年代の「前インスタレーション」期から、刊行当時の2000年代前半の作品までが扱われています。
イントロダクションの冒頭で、あくまで今日の作品は多様だと注記しながら、ビショップはインスタレーション・アートをこう定義します。
「インスタレーション・アート」という語は、鑑賞者が物理的に=身体的にその中へ入るような、しばしば「演劇的」「没入的」「経験的」と描写されるような芸術のタイプをおおまかに指す*2。
物理的=身体的に入る「状況」が「ひとつの全体性」をもつのがインスタレーション・アートである。ただしこれはあくまで大まかな定義で、ビショップは従来の歴史観ではその細かな実践を捉えきれないことを指摘し、「複数のパラレルな歴史」を本書で描き出すと提案します*3。
本書は、イントロダクションと結論のあいだに4つの章があり、それぞれ別のテーマが充てられています。つまり各章が「小さな歴史」をたどるのが特徴で、各章冒頭で示されるモデルが、それぞれの歴史が下るにしたがって展開・更新されるように記されています。各章の題は以下の通りです。
本稿ではこの章題は適宜参考にしつつ、より簡潔な言葉で各章のテーマを追っていきたいと思います。
理由としては、短い分量で把握するためと、それぞれの章題の語彙が参照しているディシプリンが、一部の作品を自然には包含しないように思えるためです。たとえば「夢の情景」は、フロイト精神分析のニュアンスでの「夢」を参照していますが、同章では「制度批評(Institutional Critique)」という小見出しで、マルセル・ブロータースによる、美術館をパロディしたインスタレーション(後述)が紹介されています。
というわけで、本稿では各章を以下の言葉で押さえていこうと思います。
- 第一章:フィクション・物語(fiction and narrative)
- 第二章:対象の知覚(objective perception)
- 第三章:自己の未分化と断片化(dedifferentiation and fragmentation of self)
- 第四章:関係するという政治性(politics of relation)
またもう一点、これらの主題の共通点としてビショップは「鑑賞主体のアクティベート(activating)」と「鑑賞主体の脱中心化(decentring)」を挙げます。この両方、特に後者は、たとえば絵画に向き合う、モダニスティックで線遠近法的、静的な「中心的」鑑賞の視点へのカウンターとして提示されます。第一章のメアリー・ケリーの言葉でいえば「単視点的(single-point perspective)」で「父権的」なイデオロギーへの抵抗です。やや手垢のついたロジックですが、1970年代の(ポスト)構造主義的な構図をビショップが採用していることが確認できると思います。
以下各章では、この「アクティベート」と「脱中心化」のさまざまな様式・パラダイムが確認されていきます。
1.フィクション・物語
第一章は「夢の情景(Dream Scene)」と題されています。
アパートメントから蒸発した人物をモチーフに、その人物のいた部屋の様子を作り上げたイリヤ・カバコフ《The Man Who Flew into Space from his Apartment》(1985)の紹介から始まります。カバコフはこれを「全体的インスタレーション(total installation)」と呼び、演劇的なものと捉えています*4。
ビショップはこの系譜の前身を、1938年にパリで開催された「国際シュルレアリスム」展の様子に見ます。同展では、もともとギャラリーにあった絨毯や家具は除かれ、枯葉、コルク、ベッドや池、火鉢などが置かれました。シュルレアリスムの理論につなげてか、「精神分析」「無意識」「夢幻的(oneiric)」とビショップは形容します。これを承けて、多様な種類の素材があり、その応答の可能性があることで鑑賞者は「アクティベート」されるというアラン・カプローの視点が参照されます。
ここまでは、鑑賞すべき対象の不分明を「夢」と形容するのも納得がいきますが、以降は現実にある空間を明晰に再現したものが多くなります。スーパーマーケットの食品売り場を再現した「The American Supermarket」展、寝室を再現したクレス・オルデンバーグ《Bedroom Ensemble》(1963)にまず触れたあと、後者のような作品が、鑑賞者が入ることのできない「タブロー」にとどまっていることを批判したルーカス・サマラスの《Room》(1964)や、さらに鑑賞者の移動に合わせてモチーフが展開するデザインを用いたポール・テックを紹介します。
シーガルやキーンホルツの絵画とは異なり、サマラスは「鑑賞者を、彼の留守のあいだに彼を探るような、ひとりの共謀者、ピーピング・トムに仕立てた。鑑賞者はスパイとしてそこに誘われたにもかかわらず、その物理的な脅威を、彼自身の禁断の出歯亀の脅威にとってかわられる」〔サマラス〕
本章のテーマの一端を「フィクション」と改めたいのは、これ以降のブロータースへの言及ゆえです。ビショップはテックの出自の政治的背景から、当時の反市場・反制度的思潮を紹介します。それをインスタレーションで反映したのが、ダニエル・ビュレンや、特にブロータースの《Musée d’Art Moderne, Département des Aigles》(1968-1972)です。この作品は美術館における作品とキャプションとの並置を、展示室を仮構することでパロディします。さらにビショップはそのような「〔美術館による分類の権力を〕下支えするイデオロギーを暗示する」傾向をもつ1990年代の作品も紹介しています。
さて、これら作品は、イデオロギーを反映した情景を、アクティベートされた鑑賞者が連想しながら読み解く……という趣旨で本章は精神分析的な意味で「夢」と題されているように考えられますが、やや牽強付会にも思えます。その点で、ある人物像や社会的欲望の流れを反映した対象としては「フィクション」と一括するほうが妥当ではないかと思います。
なぜなら「夢」はアイロニカルにも分析的にも組織されないためです。ビショップは続けて、フェミニズムの文脈でメアリー・ケリーやジュディ・シカゴ+ミリアム・シャピロの作品を紹介します。ケリーの作品も美術館的展示をパロディしながら、おしめや服、落書きなどが配され、父権的イデオロギーへの牽制との結びつき、欲望の分散が紹介されます*5。
また注目すべきは、クルト・シュヴィッタースとグレゴール・シュナイダーとの比較です。スタジオをインスタレーションに変換した前者を、スタジオの放棄とサイトスペシフィシティの称揚を説いたビュレンの主張と対比しながら、シュナイダーの《Das Totes Haus Ur》を取り上げます。家をまるごとインスタレーションにしたと言えるこの作品は、美術館やギャラリーで記憶から再構築されます。
美術館、スタジオ、家といった制度的機関(=フィクション*6)を、形式的に再現したり変換したりすることで、その内部で鑑賞者がアクティベートされて行う能動的・連想的経験が、その対象の分析になる。そうしたデザインがインスタレーションで可能になります。
こうした「イデオロギー的探求」が、冒頭のカバコフの演劇的インスタレーションと改めて合流するのが、《The Coral Reef》(2000)を初めとした、マイク・ネルソンのインスタレーションです。ネルソン作品の「インスタレーションへの物語的アプローチ(narrative approach to installation)」を紹介してから、ビショップはこう総括します。
このような作品は、心理的な没入と、身体的な潜入によって特徴づけられる。鑑賞者は、その場面に描かれた登場人物と同一化するのではなく、主人公の位置を占める。結果として、この形式のインスタレーション・アートは、なんらかのしかたで、絵画や物語、映画におけるような、没入的な特徴(absorptive character)と関係するものと考えうるだろう。
2.対象の知覚
第二章は「高められた知覚(Heightened Perception)」と題されています。
本章はミニマリズムとポストミニマリズムの作品を主に紹介します。モーリス・メルロ=ポンティの『知覚の現象学』をはじめとした著作が1960年代に英訳されたことが、それら作品を鑑賞するさいの美的経験を理論づけるために一役買いました。ロザリンド・クラウスによる参照が紹介されています。後半ではラカンにも接続するように、「知覚」というモチーフによって主客の関係、さらには「客体としての主体」を主題化する作品群が本章の要だとまとめられるでしょう。
1960年代のミニマリズムの作家、ロバート・モリスやドナルド・ジャッド、カール・アンドレ、トニー・スミスの名前を挙げたあと、ビショップはマイケル・フリード「芸術と客体性」(1967)から重点を抽出します。ミニマリズムの作品は、その状況に、時空間的に鑑賞者を含んでおり、それをフリードは「演劇性(theatricality)」と呼びました。
ここで「演劇性」は、鑑賞者自身の存在や知覚行為自体を作品が内含・反照する性質と言い直せるでしょう。「あなたの見るものが、あなたが見るもの(what you see is what you see)の美学」といフランク・ステラのフレーズはそれを端的に表しています。
1970年代西海岸の作家から、ロバート・アーウィンやジェームズ・タレル、ブルース・ナウマンなどが紹介されます。「光と空間(Light and Space)」と要約されるその作品群は、光やそれを反射する布などを主な素材に用いています。ビショップはここに、ミニマリズム彫刻の客体性から鑑賞者の感覚的な経験への焦点の移動を見出します。
この焦点の移動は、知覚という主題が即物性にとどまらなくなる契機となります。部屋に黒い線を引いただけの作品、ロバート・アーウィン《Black Line Volume》(1975)のエピソードがそれを象徴します。作品の中央に立っている柱について、美術館職員が「あの柱はアーウィンが作ったのか」と訊き、アーウィンは「彼らはまるで、初めてその部屋を見たかのようだった」と語った。ここで知覚の対象は、現前する彫刻ではなく、美術館の部屋、状況のほうにシフトしています。ビショップは続けてマイケル・アッシャーの、屋外の顕彰彫刻を美術館内に移動させた《George Washington》(1979)や、ホイットニー美術館のグループ展で展示室内の換気を操作した作品、ポモナ・カレッジでギャラリーのエントランスを取り除いて開放した作品などを紹介します。
第一章のブロータースやケリーが美術館を批評した実践と異なるところは、その批評性が、可能な状況のフィクションではなく、そこにある状況の知覚によって駆動されている点です。
ミニマリズムおよびポストミニマリズムにおける「知覚の主客」の主題は、インスタレーションへ展開するのと同時に、コンセプチュアル・アートとも接続します。ビショップはヴィト・アコンチ《Seedbed》(1972)と《Command Performance》(1974)を紹介し、さらに後者における映像中継が、まさに〈わたしが見ているのをわたしが見ている(I see what/that I see)〉経験であることから、ピーター・キャンパス《mem》《dor》(1975)や、ブルース・ナウマンの映像インスタレーション《Live-Taped Video Corridor》(1970)を紹介します。クラウスが、映像における被写体(芸術家)の中心化を「ナルシシック」と論じたことに対する、また、現象学が想定する主体が無標であり、それゆえ暗に男性的な主体であることに対する、「フェミニズム」的な自己知覚(の頓挫)として、これらインスタレーションに含まれる映像中継は機能します。ビショップのまとめを引きます。
ミニマリズムの彫刻と、ナウマンのポストミニマリズムのインスタレーションとの微妙な違いがこうして浮き彫りになるだろう。クラウスはミニマリズムを、鑑賞者を脱中心化するものとして論じた。わたしたちがミニマリズムの芸術オブジェクトを観察するとき、もはや支配的な単一の地点は与えられない。しかし、作品との関係においては脱中心化するといえるが、わたしたち自身の知覚の装置との関係においては脱中心化はおきない。他方ナウマンのインスタレーションは、知覚というものがいかに簡単に離れ離れになるか、わたしたちが考えるよりもはるかに脆く偶発的なものにすぎないかを呈示する。この知覚の不調をメルロ=ポンティは『見えるものと見えざるもの』で描き出している。主体と客体に同時になることなど不可能であり、それは並立したところで「実現の瞬間に崩壊する」はずなのだ。
このような知覚の「盲点(blind spot)」を追究した作家として、ナウマンのほかにダン・グレアムの作品や主張が取り上げられます。従来のミニマリズムの超時間性、また観客の瞑想的孤立をグレアムは批判します。そうした「忘我」にたいして、グレアムは、知覚が、他者の存在と切り離せない社会的構造物であることを、《Present Continuous Past(s)》(1974)《Opposing Mirrors on Time Delay》(1974)《Public Space/Two Audience》(1976)《Cinema》(1981)などの作品で、マジックミラーや映像中継を用いて主題化します。
イメージに没入しようと思っても、身体的自覚、つまり自己を対象として知覚してしまう経験が、映像を含めど含まざれど、インスタレーションの鬼門として残ります。ビショップは最後にオラファー・エリアソンの作品を、ナウマンと比較しながら紹介します。「You(r)」という代名詞がしばしばエリアソン作品のタイトルに含まれることを指摘しながら、その知覚によって、機関・制度(institution)との関係において鑑賞者が自分の位置を見定め、知覚のほうに変化がもたらされるというエリアソンの見通しが紹介されます。ここでも、フィクションを通じて制度のフィクションを問うというブロータースの態度と比較できるでしょう。
このように考えると、インスタレーション・アートが暗示するのは、それが、世界のなかで人間にとって意味をもつものの「真の」性質を露わにする、ということだ。それは、絵画、映画、テレビなどを経験することで作られる、「偽の」、幻影のような(illusional)主体の位置に対置したものだ。
3.自己の未分化と断片化
第三章は「擬態の侵襲(Mimetic Engulfment)」と題されています。
この「mimetic」を「模倣の」ではなく「擬態の」と訳したのは、冒頭でロジェ・カイヨワの著作が引かれているためです。カイヨワは昆虫の擬態を分析し、「何かに似ている(similar to something)」という客体的な関係が崩落した、「ただ似ている(just similar)」状況、その活性と不活性との融合した状態を論じています。これは、第二章で扱った「自己を客体とする」知覚ではない、自己を客体とすらしえない感覚です。ビショップはこれをフロイトの「死の欲動」やミンコフスキーの「夜」の経験と並べています。
こうした自他未分化の例としてまず取り上げられるのが、ジェームズ・タレルの《Wedgework III》(1969)から《Arhirit》(1971)、《Earth Shadow》(1991)まで、光を素材としたインスタレーションです。その無辺に広がる光や闇は、第二章で扱ったような「客体」としての光ではなく、ビショップも「わたしたちから隔たったオブジェクトと呼べるようなものがない」と特徴づけています。
こうした自他未分化は、1960年代から1970年代にかけて、鏡を用いた作品が増加したことにも特徴づけられます。ミケランジェロ・ピストレットの《Mirror Painting》(1962)やロバート・モリス《Untitled》(1965)と並べて、すべてが鏡面で構成され無限に反射する部屋であるサマラスの《Room 2(Mirror Room)》(1966)、また草間彌生のパフォーマンスやインスタレーションが紹介されます。草間においてはその「自己抹消(self-obliteration)」が、鏡だけでなく、草間自身がまとう衣服にも印刷されるパターンに実現され、さらに「愛」という言葉で表現されます。
後半では、映像インスタレーションが取り上げられます。ロバート・スミッソンのエッセイ「映画的アトピア」は、映画館で映画を座って見るときの「侵襲的なけだるさ」について語っています。自分の知覚がなくなり、映像を観るしかできなくなる「純粋知覚のタンク」だ、と指摘します。しかしこれだけではインスタレーションの問題にはなりづらい。ビショップは対置するように、ロラン・バルトの「映画館を去る」というエッセイを紹介します。バルトは映画館も含めた装置の経験全体、つまり音の肌理や暗闇、他の観客の物量感や投影光線、映画館への出入りの経験までを無視することなく含めて、「映画館-状況(cinema-situation)」と論じました。
映像の「周辺(surroundings)」が映像インスタレーションにおいては重要な問題になります。「未分化」という主題は一旦退き、アイザック・ジュリアンやダグラス・ゴードンの紹介を経て、ビル・ヴィオラとジャネット・カーディフにおいて「分裂」という形で改めて追究されます。
ヴィオラ《Tiny Deaths》(1993)は、暗闇のなかのスクリーンにシルエットを映す作品ですが、光量のバランスを極端にすることで、網膜が慣れる隙がなくされています。暗闇のなかに溶け込む経験と、シルエットと自己が混ざり合う経験とを、ビショップは「ふたつのレベルでの擬態の侵襲」と論じます。いっぽうカーディフの、バイノーラル録音やカーディフ自身のささやき声などを用いた作品は、他にも鑑賞者が同時に観ているという状況を、音響によって「映画館-状況」を過度に強調します。それは、映画と声、さらにその状況へと鑑賞者の注意が断片化することで、なにかひとつを客体とした一対一の没入関係を築くことが頓挫します。
本章で論じた作品は、空間のなかで現前しているという鑑賞者の感覚を断片化し、脅かすことで、安定したもの・中心化したものとしての主体性という理念を問題化する。
ビショップがここで「主体性(subjectivity)」という言葉を選んでいるのは非常に明晰で、なぜなら前章で「主体性」とは、まなざしや知覚によって構成される、現象学的ないし精神分析的な概念だったからです。たいして本章の鑑賞者のありかたは、主体性の手前で断片化する「自己(self)」という語で象徴されるでしょう。この対比は以下のようにも表されます。
本章で扱ったインスタレーションは、身体の知覚的な自覚を増大させようとはしない。むしろ、さまざまなしかたで、周辺の空間へと鑑賞者を吸収融合する(assimilate)ことで、その自覚を減少させるのだ。これらの作品において、鑑賞者とインスタレーションとは、崩落する、もしくは〔…〕未分化=脱差異化する(dedifferentiate)*7。
4.関係するという政治性
第四章は「アクティベートされた鑑賞者性(Activated Spectatorship)」と題されています。
「鑑賞者のアクティベート」は他の章でも、それぞれのテーマに沿った形でたびたび出てくる概念なので、この章が改めてこの言葉で括られるのは、いささか不明瞭だし、ともすれば「パラレル」なはずの複数の歴史が収斂するかのような印象さえあります。とはいえ内容を読むと、やはり本章はほかの章からは独立しているとわかります。
簡潔に言ってしまえば、本章の中心となるのは「関係性の美学」です。冒頭では、「政治化された美的実践(politicized aesthetic practice)としての、アクティベートされた鑑賞者性」と題が補完されます。またここでいう「政治」が、従来プロパガンダや政治批判によってイラストレーション・象徴されてきた「国家や政府による編成」ではない、と注記されます。
本章のテーマはインスタレーションの空間に、巻きこまれた鑑賞者どうしが立ち会うこと、共同体・集団の一員としてあることの問題だとはじめに提言されます*8。続けてヨーゼフ・ボイスの、オフィスを再現して来場者と対話を行う《The Bureau for Direct Democracy》(1972)などを紹介し、また「社会彫刻」の理念を取り上げます。そこでは芸術は資本主義的関係から自由な「遊びのある活動」であるとみなされ、政治的活動それ自体が、その意味で芸術的実践であるべきだと提案されます。この「誰もが芸術家」という主張が第三帝国的な「政治の美学化」に通ずるとしたベンジャミン・ブクローの批判を紹介しながら、むしろボイスは「対話」「直接のコミュニケーション」のほうを芸術の素材に加えた点で、現在のインスタレーションの先例となったラディカルなものだとビショップは擁護します。
さらに、第一章でも取り上げた(本稿では省略)ヘリオ・オイティシカが再度取り上げられます。創造、レジャー、快楽、信念などを組み合わせた造語「creleisure」をオイティシカはコンセプトにしており、儀式的で集団的な感情の高まりを、仕事と休日とのコントラストにもとづく資本主義的労働からの解放として提案しました。それを実現する作品として、《Eden》(1969)や《Babylonests》(1970)などが紹介されます。
その後、グループ・マテリアルの紹介を経て、その一員だったフェリックス・ゴンザレス=トレスが紹介されます。積み上げたキャンディーを鑑賞者が持ち帰ることのできる《Untitled(Placebo)》や、一台のウォークマンに繋がった二つのヘッドホンからワルツを聴いて、二人で踊ることのできる《Untitled(Arena)》などが紹介されます。リテラルに複数の人間がインスタレーションの空間において出会い、共在するボイスやオイティシカに比べ、ここでは、ゴンザレス=トレスのパートナーに代表される「喪失」をめぐる共同体の一員として鑑賞者がアクティベートされます。
ゴンザレス=トレスは、ニコラ・ブリオーの主著『関係性の美学』(2002)でも、一章を割いて取り上げられます。作品と鑑賞者だけの一対一関係ではなく、複数・集団的な関係をインスタレーションにおいて、実際的もしくは潜在的にアクティベートするような作品を、「関係性の美学(relational aesthetics)」とブリオーは論じました。同書でゴンザレス=トレスと等しく重要な位置を示すリクリット・ティラヴァーニャをビショップは取り上げ、オープニング・パーティの残骸を残した《Untitled(Still)》(1992)や、再現されたアパートの一室で来場者がともに過ごすことのできる《Untitled(Tomorrow is Another Day)》(1996)が紹介されます。
本書の前年に発表された論考「敵対と関係性の美学」(2004)でビショップは、エルネスト・ラクラウ+シャンタル・ムフの著作『民主主義の革命』を参照しながら、ブリオーのコンセプトを批判しています。本章でも、同様の批判が要約された形で紹介されます。対話をそれ自体で民主的だと前提するブリオーのコンセプトでは、あくまで「何かを共有」した人々の、調和的なものとしか政治性が考えられていません。そこでは、芸術もまた制度的な機能をもつことがやり過ごされています。
移民や低賃金雇用、ホームレスなどの領域を無視したり調和しようとするのではなく、その緊張や不安定を保ちながら変化に開く作家として、ビショップはサンティアゴ・シエラを紹介します。《160cm line tattooed on 4 people》(2000)では麻薬中毒者、《A person paid for 360 continuous working hours》(2000)では低賃金労働、《Workers who cannot be paid, enumerated to remain inside cardboard boxes》(2000)では移民の不法労働、《Wall Enclosing a Space》(2003)では入国審査と国籍がモチーフになっています。
シエラのライブ・インスタレーションやアクションを目撃したとき――〔展示室を塞ぐ〕壁に直面するのであれ、〔移民が隠れているという〕箱の前に座るのであれ、インクの線のタトゥーを施されるのであれ――、わたしたちは、関係性の美学のいう「ともにあること(togetherness)」とはまったく異なる反応をする。これらの作品は、わたしたちの目の前にある不穏な状況をなだめるような、人としての共感の経験を提供などしない。むしろ、人種的・経済的に同一化できないような存在を指し示すのだ。「これは私ではない」。この軋轢、不穏さ、その不快感の残存は、シエラの作品における関係的な敵対性(relational antagonism)へと、わたしたちの注意を向けるのだ。
ビショップは最後に、トーマス・ヒルシュホルンの「祭壇」のシリーズを紹介します。ヒルシュホルンは、鑑賞者を「役者」としてアクティベートするのではなく、形式・素材・場所の質をもちいて、その「祭壇」で扱われる哲学者、たとえばヒルシュホルンが「ファン」と公言するジョルジュ・バタイユについて、その作品の小屋に据えられた書籍や資料を読み、芸術観光者と地域住民とが交流するような場所を作ります。そこで鑑賞者は、参加のしかたがあらかじめ決定づけられ、その自律性を毀損された「参加者」ではない、「思慮深い訪問者」となっています。
ヒルシュホルンは、もはやそうした解放への執着は必要ではないと言う。あらゆる芸術は――没入的であろうとなかろうと――価値を再配分し、既存の支配的なコンセンサスからわたしたちの思考を脱中心化=逸脱させる(decentring)ような、批評的な力でありうる。
結論
各章で紹介した四つの「パラレルな」主題に共通するものとして、ビショップはイントロダクションで、鑑賞者の「アクティベート」と「脱中心化」を挙げていました。各章のテーマは、この脱中心化を、それぞれ「心理的(遊戯的)」「知覚的(現象学・精神分析的)」「感覚的(擬態的)」「社会的(政治的)」におこなうと整理できるかもしれません。
ビショップは、インスタレーションにおける「脱中心化」が、政治的なものであれ哲学的なものであれ、しかし鑑賞者の「中心化した現前」を強調せざるをえないことを指摘します。つまり、断片化の経験には、鑑賞者の主体としてのアクティベートが不可欠だということです。冒頭で明示された二つの特徴のあいだは、本来的な拮抗があった、ということです。
この対比は、「鑑賞者とモデル」という両義性で論じ直されます。つまり、実際に足を踏み入れる「リテラルな鑑賞者」と、あらかじめ出会い方を仮定された「抽象的で哲学的な主体のモデル」という二つの主体のありかたです*9。この断片化する主体と自己反省的な主体との緊張が、インスタレーション・アートにおける矛盾だ、と指摘しながらビショップは、このような敵対をこそラクラウ+ムフが政治性とみなしていると考えます。リテラルな鑑賞者のなかで、モデルを産出するという重なり合いをインスタレーション・アートは企み、作り出す。その度合いこそがインスタレーション・アートの美的判断の基準になる、とビショップは提起します。脱中心化した主体のリアリティに晒されるために、インスタレーションへのリテラルな没入は必要なのです。
英語表記一覧
文中では作家人名の英語表記を省略しました。ここに一覧を載せておきます。検索などにお役立てください。
- エル・リシツキー:El Lissitzky
- クルト・シュヴィッタース:Kurt Schwitters
- マルセル・デュシャン:Marcel Duchamp
- マルセル・ブロータース:Marcel Broodtaers
- イリヤ・カバコフ:Ilya Kabakov
- アラン・カプロー:Allan Kaprow
- クレス・オルデンバーグ:Claes Oldenburg
- ルーカス・サマラス:Lucas Samaras
- ジョージ・シーガル:George Segal
- エドワード・キーンホルツ:Edward Kienholz
- ダニエル・ビュレン:Daniel Buren
- メアリー・ケリー:Mary Kelly
- ジュディ・シカゴ:Judy Chicago
- ミリアム・シャピロ:Miriam Schapiro
- グレゴール・シュナイダー:Gregor Schneider
- マイク・ネルソン:Mike Nelson
- ロバート・モリス:Robert Morris
- ドナルド・ジャッド:Donald Judd
- カール・アンドレ:Carl Andre
- トニー・スミス:Tony Smith
- フランク・ステラ:Frank Stella
- ロバート・アーウィン:Robert Irwin
- ジェームズ・タレル:James Turrell
- ブルース・ナウマン:Bruce Nauman
- ヴィト・アコンチ:Vito Acconci
- ピーター・キャンパス:Peter Campus
- ダン・グレアム:Dan Graham
- オラファー・エリアソン:Olafur Eliasson
- ミケランジェロ・ピストレット:Michelangelo Pistoletto
- ロバート・スミッソン:Robert Smithson
- アイザック・ジュリアン:Isaac Julien
- ダグラス・ゴードン:Douglas Gordon
- ビル・ヴィオラ:Bill Viola
- ジャネット・カーディフ:Janet Cardiff
- ヨーゼフ・ボイス:Josef Beuys
- ヘリオ・オイティシカ:Hélio Oiticica
- フェリックス・ゴンザレス=トレス:Felix González-Torres
- リクリット・ティラヴァーニャ:Rirkrit Tiravanija
- サンティアゴ・シエラ:Santiago Sierra
- トーマス・ヒルシュホルン:Thomas Hirschhorn