ユリアーネ・レーベンティッシュの『インスタレーション・アートの美学(Aesthetics of Installation Art)』(2003)*1の各章をまとめました。

書影
この記事は、インスタレーションに関する文献の要約を公開していくシリーズです。前回取り上げたクレア・ビショップの『インスタレーション・アート:ある批評史』と、今回取り上げるレーベンティッシュの本書とは、三つの点で非常に対照的です。
- ビショップの著書を半分近くカラー図版が占めていたのに対し、レーベンティッシュの本書は一枚も図版がなく、具体的な作品記述は少ない。
- ビショップの著書が「複数の歴史」をコンセプトに章分けしていたのに対し、レーベンティッシュの本書には、ひとつのアイデアを繰り返し確認します。
- これがとくに重要ですが、ビショップの著書が「インスタレーション・アート」特有の性格を論じたのに対し、レーベンティッシュの本書は「芸術一般」に通じるような議論を展開します。インスタレーション・アートはその特徴(2.)を強調するものとして扱われます。
カタログ的なビショップの著書に比べて、分量も二倍以上ある本書は、とっつきにくくもありますが、より重要かつ射程の広い提案をしていると個人的に思います。
以下の要約では、本書のコンセプトを簡潔に伝えるため、一部詳細な・派生的な議論を省略・付記したところがあります。引用は注記がないかぎり大岩による訳です。名義がないものはレーベンティッシュからの引用です。
0.全体像——「美的経験」のプロセス
本書冒頭でレーベンティッシュは、本書が「インスタレーションの起源」や「美術史的な分類」「多様な実践の調査」を提供するものではなく、「哲学的な意味での美学(philosophical aesthetics)」を示すと明言します。そこでは、「芸術」とは何か、芸術における「美的」なものとは何かという問いが、インスタレーションを中心とした議論をめぐって考えられます。
本書を貫くひとつの単語が「美的経験(aesthetic experience)」です。文字どおりそれは、芸術がもたらすような、わたしたちが何かを美的に経験する、その経験を指します。
さて「美的な経験」とは何でしょうか。素朴に考えると、絵画なり彫刻なり「作品」があって、それがまず「美的なもの」なのであって、それを知覚するのが美的な経験だ……と考えるかもしれません。
しかし最近の芸術では、一体何が、どこからどこまでが「作品」なのか、そもそも芸術家の作り出すものは「作品」だけなのか……「作品」という、ひとつのまとまったものを指すような概念は溶けかけようとしています。インスタレーションという形式は、まだ「作品」の面影を残してはいるものの、ひとつの「美的なもの」を前にしているというより、さまざまなものに注目したり、見逃したりする、より散漫な「対象」ではないでしょうか。
レーベンティッシュは、美的経験についての従来の考え方を刷新しようとします。従来の考え方とは、まず作品という「対象」が、何か美的な性質をもって存在し、それを観るわたしたち「主体」のほうは、そこから一方的に快を受け取る……というモデルです。レーベンティッシュはこのモデルを「客観主義的誤解」と呼んで退け、現代の芸術実践により相容れるような芸術概念を提案します。
レーベンティッシュは、美的経験は「プロセス」だと考えます*2。ある対象について、こうではないか、こうならばこうか、おっと変わったな、つまりじゃあこうなのか、なるほどね、もしかして、とすると……と関係を作っていくプロセスです。むしろ、そうしたプロセスを踏みながら関わることができることで初めて、その対象は美的なものになる。何かのものがはじめから勝手に「美的」なのではなく、それに直面した主体が「ああだこうだ」知覚したり解釈したりする中で、即自的な物そのものではない、さまざまな文脈や意味を巻き込んだ「美的な対象(aesthetic object)」が存在し、それを観る主体も同時に「美的な主体」となります。
目の前の何かをきっかけに改めていろいろ考え、そこで関係を作っていくこと。それが美的経験であり、当のその何かを含んだ「美的対象」が存在します。美的経験と美的対象は互いに孤立したものではありません。この「改めていろいろ考え」を、本書では「反省(reflection)」と呼びます。目の前にある作品は、造りがこうなっているな、だからここはこうなっているのだ、なるほど、そしてそうなっているのは、こうした文脈があるからだし、そう私が思ったのも、私がこのような人物だからだ……このような反省のプロセスをひっくるめて美的経験は起きます。それは、当の経験自体や主体自身についても考え直す点で「自己反省的(self-reflective)」とも言えるでしょう。
1960年代以降、従来考えられてきた芸術の「自律(autonomy)」は危うくなり、もはや「美的自律性」概念ごとお役御免になるところでした。ここでいう「自律」とは、美的であるということは、理論的に良いとか倫理的に良いという価値から独立した価値なのだ、という意味での「自律」です。それは、グリーンバーグがモダニズムの題目に据えたような、絵画作品は絵画の、彫刻作品は彫刻の本分を排他的にもつようにあるという意味での「自律」を支えるものでもあるでしょう*3。
たしかに現代の芸術は、それ自体で理論的な批評性をもったり、具体的な政治的・実存的なステートメントを掲げたり、インスタレーションが複数のメディウムを含んだり、含まれたり……美的なものとしての「自律」という概念とは折り合いが悪いように思えます。
レーベンティッシュはしかし、芸術経験には美的に自律性があると考えます。
芸術は、〔その対象自体が、たとえば絵画の本分を提示するとか、それだけで美的であるとか〕あれやこれやのしかたで本質的に構成されている(constituted)ために自律しているわけではない。そうではなく、主体と対象とのあいだのスペシフィックな構造(structure)があることで、論理や制作実践の領分とは異なる経験を可能にさせるために、芸術は自律的なのだ。
ある対象を美的対象として受容する美的経験のプロセスが、芸術にスペシフィック(それ特有)であることで、芸術は自律している。物のもつ「構成」ではなく、経験のもつ「構造」こそが特有で美的なものである……この重点の移動こそ、レーベンティッシュが本書で展開するものです。
この提案は、インスタレーションにおいて後者の特徴が見てとれる、と主張する足場になります。たしかにインスタレーションは、絵画や彫刻といったさまざまなメディウムを含んでいたり(間メディウム性)、周囲の空間と明確な境界をもたなかったり(空間)、政治や社会の文脈と切り分けられなかったり(社会的な場)、個々の鑑賞者の動きと不可分だったり(演劇性)します。こうした場合において、その(自己反省を含む)経験が特有の形をもつという点こそが、美的に自律した価値なのだ、と主張できるでしょう。
インスタレーションは、ただ見られる対象であるだけではなく、同時に、見るという美的実践について反省するような場でもあるのだ。*4
本書は三つの章で、インスタレーションに関わるこうした特徴を議論しながら、その「美的経験」のありかたを論じていきます。
- 1 演劇性(Theatricality)
- 2 間メディウム性(Intermediality)
- 3 サイト・スペシフィシティ(Site Specificity)
本書の特徴は、各章各節の議論が、先人の議論をある種モチーフとして「変奏」するように展開する点です。紹介から始まり、部分的に(ときに全体的に)反論しながら、レーベンティッシュは自身の「経験の美学」を基礎づけていきます。
各節で扱われる内容と、モチーフになる理論家は以下の目次の通りです。各節のタイトルは直訳ではなく、内容を想像しやすいように改変しました。また本要約では必ずしもこの参照元全員には触れません。
- 1 演劇性
1.2 ミニマリズムと演劇性についての再考(マイケル・フリード)
- 2 間メディウム性
2.2 芸術ジャンルの”ほつれ”(テオドール・アドルノ)
(一旦、前半のまとめ)
2.3 空間芸術と時間芸術(G.E.レッシング、ジャック・デリダ)
2.3.1-2 舞台のようなインスタレーション(ガートルード・スタイン、イリヤ・カバコフ)
2.3.3 映画技術的なインスタレーション(ボリス・グロイス、ヴァルター・ベンヤミン)
2.3.4 サウンド・インスタレーション(アドルノ、カヴェル)
- 3 サイト・スペシフィシティ
3.2 インスタレーションが介入する政治的・社会的な文脈
このなかでは、2.3節や、3.2節でのダニエル・ビュレンへの短い言及で、具体的な作品分析が見られます。また3.2節には、昨今のポリティカル・アートや「アイデンティティ・ポリティクス」について重要な批評性があると思います。個人的には、2.3.2節の「複数の部屋をもつインスタレーション」や、2.3.3節の「映像のループ」の議論が、本書の抽象的な議論と具体的な作品デザインとがわかりやすく結びついた話だと思います。
1.演劇性
本章では、「演劇性(theatricality)」の概念をめぐって二人の理論家が取り上げられます。インスタレーションとの関係でいえば、フリードがミニマル・アートについて批判的に言及した「演劇性」がまず思い出されます。
否定的にも肯定的にもしばしば「ポストモダン」と結びつけられがちなこの概念について、レーベンティッシュは「特定の種類の芸術がもつ特徴ではなく、あらゆる芸術における構造的特徴である」と一般性を主張します。
フリードの「演劇性」批判は、アドルノ、カヴェル、ゲオルグ・ガダマーらが関わった、1960年代の美学における倫理的な展開と関係する……とレーベンティッシュは紹介し、まずカヴェルによる議論から口火を切ります。
1.1. ドラマの中の出来事とそれを観ている観客との実存的/美的関係(スタンリー・カヴェル)

William Blake, 1779ごろ, Lear and Cordelia in Prison
本章は、演劇を題材としたスタンリー・カヴェルの議論の紹介から始まります。それは、主体の認識という点に関わっています。
演劇の観客は、たとえば『リア王』のような悲劇の中で苦しむ登場人物を、外からのんきに眺める存在です。
助けられなさ(helplessness)という誤った感覚のもとで、単なる観客役へと引きこもる(withdraw)ことで、わたしたちは罪深いものとなる。自分たちのために、他人に劇をさせているという点で、わたしたちは罪深い。まるで窃視者のように、他人が苦しむのを見る。(カヴェル)
この意味でカヴェルにとって「演劇性」は、倫理的に批判するべき受動性です。世界はわたしたちの目の前にただ現前しているだけのものではないし、他者の苦難も眺めてとれるだけでおさまるはずがない。
そのような窃視症的な「演劇化(theatricalization)」は、個人の観客以上に、演劇自体がもつ悪しき構造だとカヴェルは指摘します。サミュエル・ベケットらによる近代の演劇は、このような観客の身分を捉え返すことを重視しました。カヴェルはベケットの劇『エンドゲーム』に、観客が舞台上の出来事へ「共感的に関わっていけること(empathic possible engagement)」を見出します。観客は登場人物とともに、何か起こっていることを目撃し、恐れたり苛んだりします。
本来観客と登場人物とは別の水準にあります。観客は、俳優本人とは知り合いでありうるけれど、ドラマの中の人物とは知り合えないし、ましてや助けることはできない。この分断をカヴェルは「存在論的断絶(ontological divide)」と言います。
しかし上記の『リア王』『エンドゲーム』では、わたしたち観客は、劇中の受難する人々を単なる「美的な対象」として眺める以上に、いまや「目の前にいるのに助けられない!」というその断絶に実存的な意味で直面することができる。
この意識の転換こそ「演劇」における倫理的な態度だ、とカヴェルは論じます。
観客席と舞台上の出来事とのあいだの存在論的分断という演劇的な構造は、もはや異なる機能を満たす。それは美的に距離をとることの条件ではなく、そのかわりに、他者から実存的に切り離されていることを経験するための条件となるのだ。
存在論的に断絶しながらも、しかし彼らと「同じ時間のなかに」いることで、わたしたちは「もはや美的に楽しんでいるのではなく、実存的に苦しんでいる」。
この共感的な現前のためには、「これはドラマなんだ」という意識つまり「表象の意識」を克服しなければいけないとカヴェルは批判し、「ドラマが劇場を超克する(べき)」と主張します。むしろ俳優の水準に触れることは、ドラマの中の人物への関わりを抜け出してしまうとカヴェルは考えます。
ここからレーベンティッシュは批判します。演劇の表象にたいする美的な態度が、現実の他者にたいする倫理的な態度と同一視されるのは、飛躍、メタファーではないか。
観る/観られるの非対称性や、そこで主体がさも世界を支配するかのような勘違いについて、別に演劇を槍玉とする必要はない。つまりカヴェルが本当に批判しているのは、近代(デカルト以降)の主体・客体という形而上学的な概念が帯びてしまう、他者を「対象化」する盲目さのほうであり、演劇はその比喩にすぎないのです。
レーベンティッシュは、そうした倫理実践的な対象のありかたと、芸術に特有の美的な対象のありかたは異なると一蹴します。舞台上のものと観客との関係は「霊的親交」(ガダマー)などではなく、むしろその隔たりで起こる「出来事」が重要である。
その出来事は「解釈学的アクセスの、スペシフィックで美的な不安定化」であるとレーベンティッシュは考えます。何かを解釈しようとする・し続けるときの果てしない不安定。表象とは何かが別の何かを表象しているのであり、それを「表象されているもの」つまりドラマ内の人物に寄り添うことだけに還元はできないわけです。
それは、敬虔な目撃というよりも、解釈のための機会であろう。
劇場の表象の問題は窃視のモラルの問題と同型ではない。むしろ、「表象しているもの(what is representing)」と「表象されるもの(what is represented)」という二極のあいだの緊張にこそ、解釈のプロセスという美的経験を可能にする特異な開かれがあるのです。
1.2. ミニマリズムと演劇性についての再考(マイケル・フリード)
Judd | MoMA EXHIBITION from The Museum of Modern Art , YouTube
, YouTube
さて、カヴェルは倫理的な動機から(鑑賞者が窃視者になるという意味での)「演劇性」を批判しました。フリードはまた別の観点から「演劇性」を批判します。それもまた、主体と客体の問題に関わるものです。本節はフリードのエッセイ「芸術と客体性」を分析します*5。
カヴェルの問題提起が「第四の壁」*6と関わることは明らかです。それはフリードにおいて、作品が鑑賞者を「包含(inclusion)」することの問題にあたります。それを推し進めたのがミニマリズムです。ミニマリズムの作品は「見られるがために存在している(existing to be looked at)」*7のであり、これこそカヴェルが観る主体の専横として批判したものです。
こうした批判において、ひとつの概念が二人に共通します。「現前性(presentness)」です。カヴェルは鑑賞者がドラマの人物に共感する実存的な直面を「現前性」と倫理的な意味で呼びました。いっぽうフリードの「現前性」は美的な意味をもちます。
フリードは、モダニズムの作品は「どう見られるかというパースペクティブから独立している」と特徴づけ、称賛しました。作品のこのような自律、自己充足こそ「現前性」です。
それは、あたかもカロの諸々の彫刻が、そのようなものとしての意味深さの本質を語っているかのようである〔…〕(フリード)
しかしフリードのこの考えは、ベンヤミンが批判した、芸術をロマンティックな象徴とみなすイデオロギーと同型です。ある「神秘的な瞬間」に、作品の「一貫性」「シンタクス(統語法)」によって「高度な何か」が見いだされるという、いささか神学的な定義――フリードはこれを「恩寵」とまで呼びます。
芸術は自律性をもつべきとフリードは考えますが、ミニマリズムの芸術作品はそれに反している。ただ産業的な素材の幾何形体でしかないミニマリズム作品は、それ自体では空虚で、だから鑑賞者のなすがままに存在する。つまり鑑賞者ありきのもので、その芸術経験は鑑賞者を「包含」しています。皮肉にもそれは、グリーンバーグの「絵画は絵画たるべき」という還元主義の行き着いた、「立方体は立方体たる」という、「客体性そのまま(literal)」主義とも言えます*8。
この従属関係こそ、フリードが「演劇性」と呼んで批判したものです。それは「スペクタクル」(ギー・ドゥボール)「文化産業のメカニズム」(アドルノ)という、観客の他律性への文化的批判にも沿っています。
さてしかし、美的に自律した一体のものであるためには、意味が満ちていればいい(モダニズム・現前性)のでしょうか、物そのままでよい(ミニマリズム・客体性)のでしょうか。
レーベンティッシュはこの二項対立自体を突きます。そもそも明白で即自的な「客体性」自体ありえない、と。
実は「客体性」に反対するコンセプトは、フリードの演劇性批判にすでに含まれています。ミニマリズムには、フリードが「演劇」になぞらえる特徴がもうひとつあったのです。
フリードがミニマリズム作品を「人っぽくて不気味」と忌避することにレーベンティッシュは注目します。それは、役者のようであるという意味なのです。ミニマリズムのオブジェクトは、そのシンプルな見かけの下に何か真の対象があるのか、それともただの物なのか……この「記号かものか」という不安定な二重性を、フリードは「救いがたいまでに演劇的」と呼んで嫌悪しました。フリードはミニマリズムに「意味の生産とその転覆」のプロセスを見ていたのです。
「記号/もの」の二重性、そしてそれがもたらす意味解釈のプロセスこそあらゆる芸術の構造だとレーベンティッシュは強調します。
〔…〕非演劇的な芸術でないようなものなどない、ということだ。
対象は、こうした(演劇的な)二重性をもち、それゆえに解釈プロセスは反省的(「いかにそう表されているのだろう」)になります。この点で、
「演劇性」とは、主体・客体間のヒエラルキーを打ち立てるというより、対象にたいする実験的な、いずれにせよ非支配的な関係を主体がもつような、可能性の開かれた空間に与えられる名であろう。
フリードはすでに、こうした開かれた経験の「終わりの無さと無尽蔵さ」を鑑賞者が意識する、と主張しています。つまりミニマリズムの芸術(というか芸術一般)の経験は「汲み尽くしえない(inexhaustible)」*9ものなのです。
やはり作品は、それ自体の「そのまま」で充分でもないし、それ自体でもつという「意味深さ」で充分でもない。そうした「客観主義的誤解」をレーベンティッシュは、本書を通じて繰り返し批判します。
自己充足した作品ではなく、汲み尽くしえない経験プロセスにこそ、芸術のもつ美的な自律性はある。対象との関係が不確かだからこそ、美的経験は開かれた構造をもつ。この「パフォーマティヴ」な関係づくりが、主体が対象を一方的に支配する関係ではないことは明白です。
パフォーマティヴィティとはこのように、意図的にパフォームされた行為という意味においてではなく、主体と対象とのあいだの出来事として理解されるべきであり、この出来事とは、それを経験する主体によって意図的に達成されたものというより、その主体へと「降りかかる(befall)」ものなのだ。
鑑賞者は「エージェント(agent)」であり、「美的対象に対する関係の中で、鑑賞者その人自身を経験」します。演劇化とは、このような自己反省の形象とも理解できるでしょう。ミニマリズムは、鑑賞者が自身の(他者としての)役割・関係・解釈を反省する経験をもたらします。
フリードはむしろこうした二重構造の「演劇性」を不気味に感じた。その背景には、対象が「見られるためにある」という商品性・消費主義への批判がありますが、レーベンティッシュは、関係を開く美的緊張とそれを混同してはいけないと改めて釘を刺します。
美的対象はむしろ、この関係を特異なしかたで美的に開くようなものとして理解されなければならない。
非演劇的な芸術などない。
インスタレーション・アートは、鑑賞者を「包含」して、レーベンティッシュの意味で演劇的な経験つまり果てしない解釈のプロセスをもたらします。それは、作品を経験する者のパフォーマティヴな視点に「美的対象」が依存しているということでもあるでしょう。
この点でインスタレーションは、芸術の経験一般にある特徴を照らし出すものです。
2.間メディウム性(前半)
本章では、「間メディウム性(intermediality)」の概念をめぐって、前半は抽象的な分析、後半はより具体的な分析が展開されます。
伝統的に存在した芸術のジャンルは、1960年代以降の芸術にはうまく当てはまらないように見えます。「マルチメディア(複数のメディウム)」どころか、現代の作品では、彫刻であってまた映像、映像であって空間……と、「諸芸術(arts)」が混ざり合ってさえいるように見えます。インスタレーションがそうした「間メディウム性」の顕著な例であることは言うまでもありません。
それはジャンル分類以上に、伝統的な諸芸術の理念(絵画の絵画たるや)をも蝕むかのようです。しかしグリーンバーグは、この「固有性(スペシフィシティ)」の理念こそを特権的に重視していたはずです。
本章前半でレーベンティッシュは、前章で展開した「美的経験こそ美的な自律性の要」というテーゼを再度強調しながら、「メディウム」についての議論を展開していきます。
2.1. 形式とメディウムの違い(クレメント・グリーンバーグ、ニクラス・ルーマン)
モダニズム批評の要約から始めましょう。1960年代以降に増加した「間メディウム」的な芸術をグリーンバーグは「文化の掃き溜め」と言って否定しましたが、いっぽうそうした変化は「ポストモダニズム」の中では肯定的に受け止められました。
グリーンバーグは、芸術が「独自のまた固有の領域」つまり「メディウムの固有性(スペシフィシティ)」を、自身の物理的なありかた(絵画ならば平面性)として追究することをモダニズムの核心に据えました*10。間メディウム的芸術の隆盛によってモダニズムは頓挫したと言えるのでしょう。
ここで「メディウム・スペシフィシティ」概念を改めて再活性化しようと試みたのがロザリンド・クラウスです。クラウスは、物理的な性質よりも、それを取り巻く多くの慣習=約束事からこそ、メディウムの固有性は構成されると考えました。絵画ならば壁にかけたり、映画ならば暗室に観客が黙って座る後ろに映写機を置いて投影したり……さまざまな慣習のなかで作品ごとにそのメディウムは「自己差異化(self-differing)」するとクラウスは考えました。それはメディウムに「自己充足」を求めたグリーンバーグの考えを更新する立場でした。
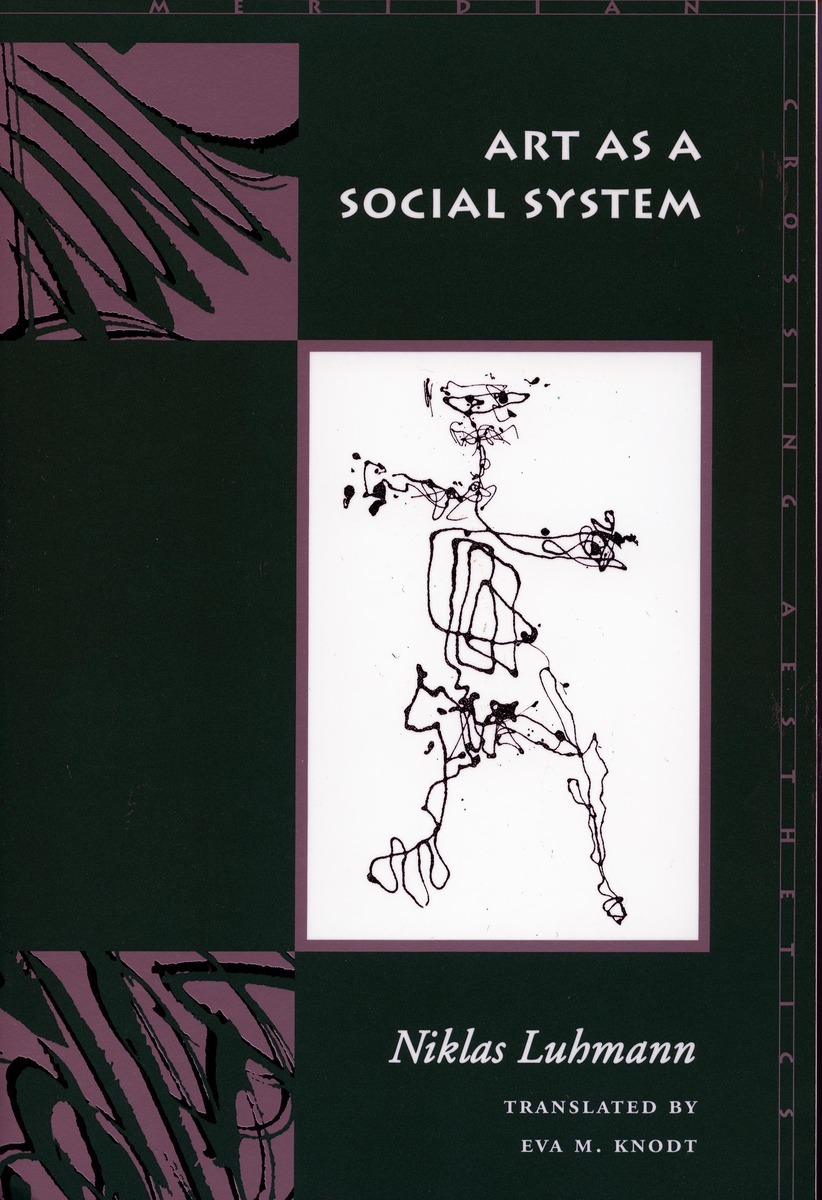
Niklas Luhmann, 2000, Art as A Social System, Stanford: Stanford University Press
レーベンティッシュは、クラウスの考えをより洗練したモデルとして、ニクラス・ルーマンの著作『ひとつの社会システムとしての芸術(Art as A Social System)』を参考にします。そこでは「メディウムの自己差異化」とクラウスが考えた仕組みが、「メディウム(medium)/形式(form)」という区別によって明快に定義されます。
ルーマンにおいてメディウムとは、「複数の組み合わせのための余裕」をもたらすような「要素のゆるいまとまり」です。絵画の平面性というメディウムにおいては、あんなこともできるし、こんなこともできる。たいして形式とは、個々の作品が達成するものです。ルーマンは形式を、「要素がしっかりとまとまることを通じて、メディウムの中で生成されるもの」と定義します。
すなわち、あらゆる形式は、メディウムとの関係においてそのたび偶然的にあらわれるものである。
あるメディウムの実践の中で、物質それ自体が形式となります。メディウムはあくまでその条件である……「メディウムは、人がそのメディウムによってできることを制限づける」だけで、形式のレパートリーはその制限のなかで模索されつづける*11。
ルーマンおよびレーベンティッシュの視点からすれば、従来メディウムと一致していたジャンルの境界が崩れるのはさもありなんです。むしろメディウムの「ゆるさ」の中で形式が創造されるなら、従来のジャンルは越境されるはずなのです。つまり1960年代の現象は、メディウムが「再発明」(クラウス)されるパラダイム(ポストメディウム的条件)に入ったというより、芸術本来の「美的メディウムと形式との関係のスペシフィシティ」の問題なのです。
メディウムとは、さまざまな形式の湧き出る可能性の空間と言えるでしょう。あるひとつの形式を創造することは、その空間の中で「印をつけること(有標とすること)」「分離画定すること(decision)」だとレーベンティッシュは表現します。
あくまでひとつの偶然的な「印づけ」として形式が現れることで、メディウムは可能性の総体であることをなお維持します。ルーマンの言葉で言えば、「より積極的な横断を〔…〕刺激するような」可能性の総体です。その無限の可能性の中から、作品は自身がもてる「美的な一貫性」を掴み取り、形式を成します。
ここからレーベンティッシュは批判します。
ルーマンは、そのように生まれた作品を鑑賞者が理解することを、制作・構成プロセスの再構築のようなものだと考えています。つまり、制作と受容は(逆向きの)似たプロセスだ、ということです。
しかし、芸術の経験にとって、芸術家の決定をたどり直して称賛することは別に必須のものではないとレーベンティッシュは主張します。あくまで経験とは、制作とは異なる何かをもつプロセスのモードである*12。なぜならそこでは、前章でミニマリズムについて論じたとおり、鑑賞者自身によって反省されることが不可欠だからです。対象との相互関係は、その解釈を通じて生成され、「自己反省的でパフォーマティヴ(self-reflective and performative)」であるゆえに、そのたび偶然的に起こるのです。
ルーマンが記すように、芸術は、「何か別のものを指す記号」でも「物質の単なる形」でもなく、むしろ美的経験における形式とメディウムのダイナミズムにおいてのみ存在する。
芸術家は、ある形式を創造することで、「可能なものの領域〔メディウム〕において、秩序の不可抗力を提示する」〔…〕。だがその経験の特異性のうちで、またそれを通じてのみ作品が展開するその自律性を、芸術家が予測することはできない――その経験は、メディウムと形式とののダイナミズムが、ここまで説明したような意味で不可欠となるような、「特異に美的な」対象関係の経験である。
芸術ジャンルの境界の「ほつれ(fraying)」は、メディウムの衰退どころか、メディウムを反省して形式を作り出した結実です。レーベンティッシュは、グリーンバーグやクラウスの立場を「メディウムの美学」と呼びます。たいして本書でレーベンティッシュが展開するのは、「経験の美学」なのです。
2.2. 芸術ジャンルの”ほつれ”(テオドール・アドルノ)
本節では、こうしたジャンルの「ほつれ」に反応したもうひとりの思想家、テオドール・W・アドルノを参照します。
「ほつれ」に対して、グリーンバーグらが保守的な反動を見せて伝統を固辞したのに対して、アドルノはむしろ芸術はその自律性のためにこそ伝統から解放されるべきだ、と言って「ほつれ」を肯定的に評価しました。
それは、あらゆる諸芸術は最終的にひとつの芸術に統合されるべきだというロマン主義的主張とも、「総合芸術(Gesamtkunstwerk)」を目指す傾向とも異なります。後者にあたるリヒャルト・ワーグナーの音楽劇は、むしろ詩と音楽とを無理に相互にあてはめようとして、互いの構造を破壊してしまった、とアドルノは批判します。
むしろジャンルの「ほつれ」は、そのような「収斂」よりも批判的な「進歩」として肯定されます。
アドルノにとって、芸術の美的な「物質=質料(material)」は、ただ物質そのものではなく、歴史的に展開する形式とともに語られるべきものです。この点は、ルーマンの形式観によく似ています。
こうした「歴史的な展開」を、アドルノは「美的進歩」と呼びます。アドルノにとって芸術作品は、メディウムと形式、美的質料と形式の間のダイナミズムの歴史に照らして、自分の位置を定めるものです。
アドルノによれば、その〔芸術作品の〕価値は、その時代において美的質料が達成していた状態にたいする、どのような反動的ないし進歩的な関係をもったかによって決まる。
重要な作品ほど、その美的質料(という歴史的なもの)に痕跡を残します。その時代における達成に照らして、芸術作品の価値は測定される。つまり、美的質料は時代の形式とセットで語られるべきもので、ただフェティッシュな感覚だけで「止揚」はできない。
「止揚(sublimation)」は、形式と内容のあいだで行われます。芸術は、道具的理性*13が支配する世界に抵抗するポテンシャルとして、芸術としての合理性をもつのだ、とアドルノは考えます。現実は道具的に支配できるものではなく、調停されておらず、自己分裂したもの。それを示すには、芸術は「見せかけの調停の領域」として振る舞わなければならない。
これはとてもひねくれた理屈です。芸術は、あえて調停するかのような美的統合のもとで現実を見せることで、調停されない現実を否定する。調停されるはずない現実を、あえて調停の光で見せてやるという自己矛盾したシステム。それが「現実の可視化」と「美的一貫性」つまり内容と形式との止揚において起こるものだ……とアドルノは考えます*14。
統合の否定を美的な意味とする……という点で、それは弁証法的な意味で「止揚」なのです。ここで芸術作品のうちに知覚される論争的な内容、質料が勝手にもつ欲望を形式が組み伏して組織していることこそを「美的精神」と呼ぶのだ、というのがアドルノの主張です。
ここからレーベンティッシュは批判します。
アドルノの「美的精神」における止揚、物質と制御の矛盾的関係とは一体何なのか。それは(調停されない)現実と(調停された)ユートピアと(あえて調停の見かけを作った矛盾たる)芸術という三者が、うまいことお互いに参照することを指します。
しかしこれをレーベンティッシュは、アドルノの歴史哲学の投影でしかなく、実際の美的理解のプロセスとは言えないと批判します(カヴェルに対する批判に似ています)。美的経験のプロセスは無限に解釈を広げるはずなのに、逆にアドルノは理念的な美的精神という「真理」をすぐに定めようとしてしまいます。結局そこでは形式について、受容主体が熟考することで再構築できる……という、ルーマンと同じ落とし穴にはまっているのです。繰り返せば、美的経験は、制作プロセスの再構築ではありません。
むしろ、鑑賞者の投影に左右される美的経験において、要素の相互関係ははなから保証されません。内容と形式は調停云々とは関係なく、もともと分裂しているし、そのため一貫した相互関係というものがつくづく明らかに見てとれないからこそ、芸術は「プロセス的」なのです。
アドルノがジャンルの「ほつれ」を評価したのは、(諸芸術ごとの)美的構築の否定こそ、芸術がもつ「美的な意味」だったためです。
たとえばシェーンベルクの音楽の無調・十二音技法に、従来の調性音楽の痕跡を耳が聞き取ってしまうことで、むしろそれがそこで否定されていると示される……という理屈です。これが内容と形式の止揚です。そこでは作品の構築を通じて、物質的な土台(音と聴取)が解放されています。
ジャンルの定義に安易に一致するのを否定し、全体的な意味の充満に抵抗することこそ、アドルノが考える芸術の重点です。ジャンルの定義と摩擦し、ほつれさせることでこそ、芸術は正に自律的なのです。『フィネガンズ・ウェイク』の単語が示す音声的側面、フランク・ステラが示す、カンヴァスの彫刻的な性質……メディウムは、作品の形式で反省されるごとに、そのスペシフィシティを、別のメディウムへと開いていくのです。
あらゆる芸術形式は、他の芸術との無数の本質的関係を――あらゆる芸術があらゆる芸術と結びつくわけではないにしても――もつ。
諸ジャンルは、溶け合って構造的な違いを失うのではなく、あくまでその構造的な違いゆえに「ほつれ」る。
こうしたアドルノの評価は、当時の(そして、今も)ブルジョワ社会を反映しています。アドルノは、芸術ジャンルの分割が、社会における労働の分割と関わっていると考えたのです。それらの調和しなさを参照するからこそ、芸術は芸術たりえ、「美的進歩」をなすべきだと。現実・ユートピア・芸術の三点セットです。
それゆえアドルノは、メディウムそれぞれの歴史に(批判的な)連続性・進歩をもたらす「一貫性」が必要と考えます。アドルノがマルチメディア(ハイブリッド)な間メディウム的芸術を評価できないのはこのためです。結局ジャンルごとにスペシフィックな技量を評価するアドルノは、グリーンバーグと似た保守主義に至っているとも言えるでしょう。
レーベンティッシュは、アドルノの理屈で言えば、そうしたハイブリッドな間メディウム的芸術も、同様に技量や歴史への反省を当然成す、と指摘します。
さて、このような対象との関わりから、レーベンティッシュは改めて「美的自律性」を定義します――といっても、ほとんどすでに論じた内容ですが。
この点で私自身は、われわれにとって美的自律性というものは、特異な形で美的であるような対象との関係の効果(effect)として知覚されるのであり、制作や作品の美学によって補完されるようなカテゴリーとして知覚されるわけではないと論じた。
芸術の本質に「異種性」だの「衝突」と言いながらも、アドルノはハイブリッドな芸術を擁護できなかった。アドルノは、現実・芸術・ユートピアの弁証法を目的論化するために、「ほつれ」は現実の調和しがたさの描写(ミメーシス)だとみなしてしまった。
結局、アドルノは作品が具体的にもつ地平を見落としたのです。
本章前半の主張を整理していきましょう。レーベンティッシュは、芸術が芸術たる「美的自律性」を、超歴史的なメディウムの美学(グリーンバーグ、フリード)や、歴史の中で技術的発明して位置を得るという進歩理論(アドルノ)からではなく、具体的な作品経験に置こうとします。
そうした経験は「把握不可能な構造」(ルドガー・ブブナー)です。具体的な解釈行為をどれほど向けられてもびくともせず、さらなる理解を駆り立てることにこそ芸術がもつ美的な自律性はある。
解釈・批評の起こる特殊な「プロセス的(processual)」関係ゆえに、美的対象は美的といえるのです。そうした経験を可能にするからこそ芸術は美的である。
その経験・判断は、もともと作品が備えている中身の再確認ではありません(客観主義的誤解)。むしろ、まず美的経験が先にあって、その経験について客観的に反省するプロセスが延々と続くために、美的・批評的なのです。この反省を、レーベンティシュは「結晶化(crystalize)」とも呼びます。
芸術作品はしばしば、期間を経て再評価されます。これは、超歴史性でも、一方向的な進歩でもありません。時代を経て解釈が続いていくという歴史的側面が、作品の経験自体にあるからなのです。
現代の芸術制作のポイントが、伝統の再確認だけのわけがありません。複数の基準をもち、異種的にスペシフィックな制作においてこそ「前衛」です。そうした芸術を芸術と判断するその試みの瞬間においてこそ、批評の挑戦があるのです。
レーベンティッシュにおいて、昨今の間メディウム的な芸術は、モダニズム的プロジェクトからの脱落ではありません。レーベンティッシュが「経験の美学」を提唱するのは、客観主義的誤解(対象には、制作の時点ですでに自律性が書き込まれており、経験はそれを再構築するだけという――パズルかのような想定)を拒否するためです。
ここまでが本書の前半部分です。簡単なまとめを挟んでから、本章後半(具体的なインスタレーションのデザインについて)と次章(サイト・スペシフィシティについて)に進みましょう。
(前半のまとめ)
冒頭で示したようにレーベンティッシュの主張は、芸術作品を前に解釈をつづけていく「経験」こそ美的なものだとみなす観点に立脚しています。
まず第一章でレーベンティッシュは、「演劇性」にたいするカヴェルのモラル的批判も、ミニマリズムに対するフリードの美的批判も、主体が受動的であることを批判します。主体は、苦しむ登場人物を漫然と眺めたり、見られるために存在する立方体やらに「包含」されたりする存在です。
しかし美的な対象とは、一方的に観客を包含するものではないし、またフリードが望むように充足した意味を一方的に与えるものでもありません。そうした勘違いは、主体と客体の関係を固定する形而上学を、芸術経験に不適切に投影してしまっています。対してレーベンティッシュは、美的経験というのは、その関係が不確かで、汲み尽くしえないプロセスだからこそ美的なのだ、と主張します。その意味であらゆる芸術は「演劇的」であり、特にインスタレーションはそれをよく照らし出しています。
続いて第二章でレーベンティッシュは「間メディウム性」を論じます。1960年代以降の芸術ジャンルの「ほつれ」を、メディウムは排他的にスペシフィシティをもつべきと考えたグリーンバーグが批判したいっぽう、アドルノはむしろその「ほつれ」がメディウムの歴史的進歩・止揚の結実であると評価しました。しかし、自身の歴史哲学が反映されたアドルノの観点は、現実とユートピアと芸術が弁証法的に総合するような「真理」をすぐに定めようとしてしまいます。それでは具体的な作品におけるプロセスを見ていません。
美的経験においては、そうした要素の関係ははなから保証されておらず、むしろ解釈・反省が果てなく不安定に続くからこそ、美的なのです。アドルノは歴史的進歩を重視するため、ジャンルにとっての前衛は評価できても、ハイブリッドな間メディウム性を擁護できませんでした。しかしレーベンティッシュの「経験の美学」は、そうした美的プロセスを促す点で、芸術一般を評価できるのです。
2.間メディウム性(後半)
2.3 空間芸術と時間芸術(G.E.レッシング、ジャック・デリダ)
後半2.3節では、ここまでの議論をもとに、インスタレーションという空間芸術(spatial art)が、演劇・映像・音楽という時間芸術(time-based art)*15とのあいだにもつ間メディウム的協働を考察します。
具体的な分析の前に、レーベンティッシュは芸術における「空間」と「時間」について、作品がもつ要素同士の関係から定義を整理します。
レーベンティッシュは、まずもって「空間芸術」であるインスタレーションを考えるために、18世紀の思想家G.E.レッシングの『ラオコーン』を参照します。
レッシングは「空間芸術」を「時間芸術」と対置させる際、空間芸術の特徴を、三次元的な広がりではなく、要素どうしの「並置性(juxtaposition)」と考えます。たとえば詩の要素は「連続的(consecutive)」に展開するけれど、絵画表面の要素は「並置」された形で認識される。つまりそうした諸要素は、続けざまに認識されるのではなく、「同時性(simultaneity)」のもとに認識されます。
絵画の上に並置された諸要素を同時に認識すると、それは、物語のプロットが一瞬止まったかのように見える。これをレッシングは「含蓄ある瞬間(pregnant moment)」と呼びました。つまり、配置によってたったひとつの瞬間(moment)だけを獲得するのが絵画だと。ただしこの「瞬間」を「一瞥」と考えてはいけません*16。並置された要素を、時間をかけて何度も見て検討・想像することで、その「含蓄ある瞬間」は訪れるのです。
この「含蓄ある瞬間」における、時間をかけた想像。レーベンティッシュは、「その内的構造は時間的である(temporal)」と考えます。この点で、空間芸術は時間と関係しています。レーベンティッシュは、絵画さえも、それは「〔鑑賞者の〕想像力のもつ生産力が媒介した時間性の残したもの(index)」を負っている、と考えます。想像力によって、作品の諸要素はプロセスへと解放されるのです。
〔…〕表象は、自身が呼び起こした意味が全体まで行き渡る(the totalities of meaning)たびに、繰り返し逃れるという本質をもつ。こうしてそれは美的な運動の中に置かれるのだ。
重要なのは、この時間的な「プロセス」は、音楽や映画を頭から終わりまで見たり、彫刻作品をぐるりと一周するのにかかる「時間」とは異なるという点です。むしろそれらを同じと考えると、前半で批判した、「作品のなかにあるもの(時間)を鑑賞が再構築して焼き直す」という客観主義的な誤解に戻ってしまいます。
ここで問題になっている〔空間芸術について確認したような〕時間性というものは、芸術作品それ自体のプロセス的な存在のありかた(processual existence)、美的経験がもつ根本的に際限のない(indefinite)プロセスのもつ構築的な役割に関係するのだ。〔…〕というのもこの時間性とは潜在的には無限のものであり(potentially infinite)、音楽や映画や演劇作品が成り立っている有限の時間とは、明らかに一致しないからだ。文学の場合も同様だ。その経験の時間は、読むという一直線の行為がもつ時間には、明らかに還元できない。
このようなプロセス的な時間性は、もちろん時間芸術にもあります。以降では、演劇・映画・音楽についての「プロセス」を賦活させるようなインスタレーションを見ていきます。
2.3.1-2 舞台のようなインスタレーション(ガートルード・スタイン、イリヤ・カバコフ)
Ilya and Emilia Kabakov – ‘The Viewer is the Same as the Artist’ | TateShots from Tate , YouTube
, YouTube
本稿ではスタインについての議論を省略し、イリヤ・カバコフ*17を中心にまとめていきます。本節はカバコフの「全体的(total)インスタレーション」概念を検討します。前節で引用した「意味の全体(totalities)を表象は逃れ続ける」という旨を思い出しておきましょう。
イリヤ・カバコフのインスタレーションはまるで「放棄された舞台」かのようです。もしくは、舞台の幕間にその上へ乗り込んでしまったかのようです。鑑賞者はいくつかの部屋を動き回ります。その動きは一見鑑賞者の思いついたルートに見えながら、作品にコントロールされています*18。
しかし鑑賞者はそうしたコントロールの仕掛けに当然気づきます――カバコフ自身が言うには、「『罠にかかったねずみ(victim)』であり同時に鑑賞者でもある」。
つまり複数の部屋にわたるインスタレーションでは、鑑賞者の動きは「指図(direction)」「採譜(dictation)」されていながら、実際は、自分の動きがそれと一致しないことも当然なのです。鑑賞者は、自分の動きがどう演出させられているかを反省し、この反省がプロセスとなり、美的経験を構成します。
さて、なぜこれが「演劇的」なのでしょうか。カバコフは、複数の部屋を鑑賞者が通り抜けることに、「一種の独特な戯曲として上演されるような」「ドラマティックな効果」を見出しています。
少々長いですが、レーベンティッシュの説明を引用します。いわゆるインスタレーションの間取りについて、とても基本的で重要な指摘だと思います。
インスタレーションのもつ空間的な論理が、演劇のもつ時間的な論理へ近づくのは、つまり鑑賞者がその個々の空間を「次々に(consecutively)」通り抜けざるをえないという点だろう。インスタレーションの中にある個々の空間は、それらが空間へどう配置されているか、が重要な意味をもつ。それは(インスタレーション)作品全体から見た要素の配置が大事だという一般的な意味というよりも、鑑賞者の動線に沿って置かれることで、差異をもたらすという意味で重要なのだ。つまり、すでに見たものや、これから見るものと関係しながら、それら要素は鑑賞者の前に現れる。複数の部屋にわたるインスタレーションでは、この時空間的な前後関係の効果がもたらされる。そうしたインスタレーションは、その全体が鑑賞者の目の前に現れることはない。〔…〕鑑賞者がその作品について行うような相互関係の形成においては、すでに見た要素やこれから見る要素が必ず参照される。
演劇と結びつくのはここです。演劇も、ただ時間に沿ってすべてが進むわけではなく、舞台上には同時に複数の要素が「並置」して現れます。
演劇は、舞台のうえで空間的な並置のなかで展開する演劇的記号と、時間的な連続のなかで発生する演劇的出来事とのあいだに緊張がある。カバコフの、複数の部屋にわたるインスタレーションも同様だ。インスタレーションがもつ要素の空間的並置と、鑑賞者の移動に左右される、要素への次々の出会いとのあいだに緊張が生じる。
カバコフは空間でストーリーテリングすることを重視しましたが*19、レーベンティッシュはむしろこの「緊張」のほうに注目します。鑑賞者は自身の動きが演出されていることに気づき、この緊張はますます高まっていきます。
インスタレーションへのプロセス的解釈をレーベンティッシュは「テクスト」とも呼びます。もちろんこれはインスタレーションに含まれる言語的要素とは違うものです。プロセスをテクスト(つまり書かれるもの=エクリチュール)と比喩することで、レーベンティッシュは際限ないプロセスの仕組みが「代補」(デリダ)的だと示唆します。ただテーブルがあるだけで、その「テーブルとしてあること(tableness)」は膨張し、果てしない解釈が引きずりこまれていくのです。
インスタレーションの物語(ドラマ)的全体性は転覆しつづけ、時空間的な統合は拒否されつづけます。それは「美的なふたしかさ(aesthetic uncertainity)」「美的なプレイ(aesthetic play)」なのです。
インスタレーションは単なる間取りや場面ではありません。カバコフのインスタレーションがしばしば不気味と呼ばれるのは、それが直に観察されるものにとどまらず、きりのない反省がぽっかりと口を空けているからでしょう。このようにドラマ演劇を模倣する点でカバコフのインスタレーションは「間メディウム的」であり、演劇とインスタレーション、さらにそこに含まれる絵画や彫刻とのあいだで構造的な違いが露わになるのです。
2.3.3 映画技術的なインスタレーション(ボリス・グロイス、ヴァルター・ベンヤミン)

Video still of Stan Douglas, 1998, Win, Place or Show
「映画技術的」というぎこちない訳から説明しましょう。英語では「cinematographic」で、もともと「cinematograph」とは「映写機・映画撮影技術」を指す言葉です。単に「映画的(cinematic)」ではないことに注意しましょう。
つまりレーベンティッシュが本節で扱うのは、映画の提示や受容の条件を重視したインスタレーションです*20。
映画技術的インスタレーションの先祖は、実験映画です。リアリズムや教訓、ドキュメンタリーやフィクションから離れ、映画という表象がどのようなものかを反省する方向に進みました。カメラや照明、編集、暗室、投影、客席といったものがモチーフになったのです。
映画技術的インスタレーションは、複数のモニターをもちいたり、その投影位置やサイズに工夫したりすることで、映画における空間の秩序を反省させます。1970年代の映像作家も「映画館」という存在を批評的に反省していました。現在のインスタレーションではさらに鑑賞者が動き回り、自身がいる位置や、映像の装置について反省します。
たとえば、そこにある映像素材をどのくらい長く観るか。
だがすぐそこにある対象――映像イメージがつねに変化している以上、美術館・ギャラリーの来場者はもはや、何か重要なことを見逃したのではないかという居心地の悪さなしには、その作品に出会ったりその場を離れたりすることはできない。
インスタレーションにどのくらい長く滞在するか、という「覚束なさ(insecurity)」。映画館のように上映時間に拘束されることもない(映像技術的)インスタレーションでは、「常に選択可能であるものがもつ、根本的な際限のなさ」が、作品における意味の形成や、個々の要素の時間的展開と緊張し、反省をもたらすのです*21。
レーベンティッシュは、二つの技法を取り上げます。ひとつは「ループ」、もうひとつは「ハイパースローモーション/定点長尺(duration)」です。
まずループは、映像の提示を「不自然」にするとレーベンティッシュは指摘します。物語映画と違って、終わったらまた始まるというのが自然な事ではないのは明白です。ループは、鑑賞者が映像素材の全部を見やすいためのものではありません。それではただの「これで一周見たからもういいや」という立ち去りの合図です。インスタレーションでループが重要となるのは、その反復構造が作品の一部となるときです。むしろ鑑賞者は、ループだからこそ、立ち去るのではなくそこに留まるのです。
レーベンティッシュは、クレイアニメとタイムラプスのループを並べたブルース・ヨネモト《The Time Machine 》(1999)と、二人の男性の口論の映像が毎周ランダムに変化するスタン・ダグラス《Win, Place, or Show》(1998)を紹介します*22。時間表象の違い、プロジェクターの露呈、デジャヴ……などをもちいて、インスタレーションは滞在時間と経験時間との緊張をあらわすのです。
》(1999)と、二人の男性の口論の映像が毎周ランダムに変化するスタン・ダグラス《Win, Place, or Show》(1998)を紹介します*22。時間表象の違い、プロジェクターの露呈、デジャヴ……などをもちいて、インスタレーションは滞在時間と経験時間との緊張をあらわすのです。
ハイパースローモーションの作品は、たとえばダグラス・ゴードンの《24 Hours Psycho》(1992)やビル・ヴィオラの《The Quintet of the Unseen》(2000)が例に挙がるでしょう。定点長尺は、アンディ・ウォーホルの《Empire》《Sleep》(1964)を挙げられます。個別の画像の連続、絵画との違いなどによって、動画と静止画との違いが反省されます。
物語映画のようには表象されるものとするものとの時間とを同期させないことで、これらの技法は美的経験を開くのです*23。この「同期」の理想は、本節冒頭で「客観主義的誤解」とすでに指摘しました。
2.3.4 サウンド・インスタレーション(アドルノ、カヴェル)
「音楽の空間化」という話から本節は始まります。本節冒頭で指摘したように、本章での「空間」はレッシング的な意味でも考える必要があります。つまり音楽の「空間化」は、音楽が三次元的に響くことだけではなく、「要素の並置」も指します。
音楽も劇のように要素が展開し、その瞬間瞬間を鑑賞者は聞きます。アドルノによれば、「理想的聴取者」はそこから、音楽が全体としてもつ時間を再構成・止揚します。これが、批判されてきた「客観主義的」な考えだということは言うまでもありません。
1945年以降の音楽の展開を、アドルノは「不定形の音楽」と表現しました。そこでは、「時間展開」の伝統的な聴取ができなくなっている。
音楽の伝統的な聴取は、その音において、時間そのものの流れとともに、部分から全体へと展開する。この流れは――言ってみれば、音楽的出来事の時間的な継続と、時間自体の純粋な流れととの間の並行性は――、もはや問題含みのものとなっている。それは作品のなかで、考え抜かれ、制御されるべき対象として現れる。
音楽とは流れに沿って聞いてわかられていくものだ……という理念は危うくなります。そのような状況でワーグナーは「有機性」理念によるてこ入れ、ジョン・ケージは主体の構築自体の拒否、あるいはヤニス・クセナキスは数学に頼りました。
いっぽうアドルノは、音楽全体がもつイメージと、音素材それぞれの並置との、ダイナミズムの進歩としてこれを考えます。演劇でいえばドラマ全体と個々の要素、(物語)映画でいえば物語全体と個々のショット、の対立と考えるとわかりやすいでしょう。さらにこの対は、第一章でフリードが主張した「シンタクス/客体性(そのままのもの)」の対立にも対応します。
伝統的な音楽のもつ調性的な造りから解放された「不定形の音楽」においては、この音楽的なシンタクスはもはや、アドルノによれば「批判的な解釈」によってのみ到達できるようになります。それが「楽譜(score)」「書かれたもの」と呼ばれるのは、2.3.2節での「テクスト」概念に対応するでしょう。もちろんそれは、スコアが暗号でそれを解読して終わり、という客観主義的な意味での「解釈」ではないことに再三注意しましょう。
いまや音楽は、鑑賞にかかるような時間を越えた音楽的な意味を聞き取らせるものであり、そうすることで「時間芸術として構成」されます。
音楽的意味がより完全な形で現れるほど、その見た目は単なる現前ではなくなる――より明確に言えば、その時間的地平、未来予持性(protentionality)と過去把持性(retentionality)によってますます極化され、単純に存在する瞬間においては自身を汲み尽くせなくなる。(アドルノ)
カバコフの演劇的インスタレーションについてのレーベンティッシュの分析を思い出す一節です。
音素材という「客体性(objecthood)」ではなく、聴く主体の生産力を通して、音楽の意味という「第二の客観性(second objectivity)」に至る。それには「訓練された耳」が必要で、それこそ「批評的進歩」である。
ここで改めてレーベンティッシュは批判します。つまり、また例の歴史哲学です。やはりアドルノは「進歩」のために美的経験を再構築に還元してしまっている。(楽譜の)作曲や解釈における一貫性の構造は、聴くという経験における一貫性の創造とは異なります。
やはり聴取は、主体がパフォーマティヴに為す経験であり、際限なき構造をもち、閉合に抵抗し、不安定な解釈によるものなのです。緊張が止揚するゴールとして「意味」を置くアドルノを、レーベンティッシュは支持しません。
さて、美的経験の際限なさ(interminability)が意味するのは、音楽という時間芸術の場合では、それを経験するプロセスの時間と、美的経験の時間とのあいだの構造的な緊張である。美的経験のプロセス性(processuality)は〔…〕ある音楽作品によってひとつにまとめられた(organized)時間という形に客体化されることはない。〔…〕アドルノによる美的なプロセス性の解釈とは対照的に、あらゆる芸術はプロセス的である。なぜなら作品における関係つまりその一貫性は、その美的経験の主体にとって最終的に明白にはなりえないからだ。むしろこれは、芸術作品のもつ諸要素を、それらが置かれる特有の文脈それぞれにとって生産的であったり破壊的であったりする刺激へと解放するのだ。〔…〕美的時間とみなされる「音楽的時間」は、測れる長さをもつような客観的な時間と同一のものではない。そして一貫した形式的構造へと制限されるものでもない。美的経験の主体的プロセスにおいて、それは繰り返し解放されるのだ。
聴取する主体がもつ役割を洞察するために、1960年代以降の音楽はその要素の並置つまり「空間」を目指します。音楽の時間は(アドルノのように)目的論的なものではなくなり、緊張において自律性をもちます。
要素こそ、サウンド・インスタレーションの問題です。まとまった単位や展開のない「音響(sound)」だけがあり、むしろ鑑賞者の滞在へと、そこで起きる出来事は還元されます。
サウンド・インスタレーションの「空間」は、主体が構成しつづけるべき要素の「並置」と、音が反響する三次元的次元という、二重のものになります。
鑑賞者がそうした並置に敏感になることで、反響空間が発見されたり、環境自体がもつ聴覚的表現、また日常空間における聴覚の反省などが行われます。そうした反省は「アンビエント」という語と結びつくでしょう。さらに聴覚と視覚のあいだで鑑賞者の注意が動いたり、インタラクティヴに音が変化することも、美的経験のプロセスに寄与します。
これは一般化すれば、展示空間自体がもつ表象のポテンシャルが反省されていると言えるでしょう。レーベンティッシュはカバコフのインスタレーションが学校や孤児院、居間を模していることに注目しました。テーブルの例と同様に、そこでは「ある特異な空間が、当のインスタレーションの提示の中にあるのか、それとも空間それ自体としてあるのかという問いが美的に反省される」*24。
本章をまとめます。
純粋な空間芸術も、純粋な時間芸術もない。
時間芸術は、要素の並置という空間的な性質を含み、空間芸術は、要素を構成する美的経験のプロセスに時間的な構造を含みます。このふたつには、「ノンリニアな時間性(non-linear temporality)」が内に共有されています。不一致をあからさまに作ることで、そこにおける創造のほうが主体を提示し返すような時間性です。これこそ、「同期と再構築」という、モダニズムの客観主義的な考えに対抗するアイデアです。
ハイブリッドな間メディウム的芸術は、この意味で「展示空間」という「メディウム的条件(medium condition)」を明朗に示すものです。それぞれの作品が(演劇的なり、映画技術的なり、音響的なり)形式を創造することで、このメディウムが照らし出されるというのは、本章前半で取り上げた、ルーマンの芸術観にも一致するものでしょう。
3. サイト・スペシフィシティ
本章では芸術の「場(site)」という概念から、インスタレーションを考察します。
インスタレーションが文脈に影響されることは、これまで見てきた通りです。かつて唯美主義は文脈から独立した作品という理念をもっていましたが、現在の芸術は、自身の文脈へ開かれ、それをテーマとして提示してさえあります。
インスタレーションは自身の「社会的」次元をつねに提示している。この社会的な「場」を、本章は二つの方向性から扱います。ひとつは、実際にインスタレーションが置かれた場について。もうひとつは、そのインスタレーションが社会のなかで占める場について。所与の建築や風景に介入するサイト・スペシフィックな作品は、その二つの意味の「場」、その絡み合いをテーマとします。
この二つの場所は、それぞれが現象学や社会学に還元するのではなく、主体によって、ともども参照されます。その参照のプロセス、美的経験が、作品を支えるのです。
3.1 芸術と、それがインストールされた空間との関係(マルティン・ハイデッガー)

パルテノン神殿
By Steve - File:O Partenon de Atenas.jpg, originally posted to Flickr as The Parthenon Athens, CC BY 2.0
ハイデッガー『芸術作品の根源』(1961)*25では、ギリシアの神殿が取り上げられます。岩の土台に載った神殿は、岩が、ぎこちなくも自然にそれを支えていること自体の「謎(mystery)」を示す。もしくは竜巻に耐える神殿は、その竜巻をその暴力のうちに示す。日光に輝く神殿は、昼の明るさや夜の闇を示す。そびえる神殿は、見えない空気を示す……。
このような空間への現象学が、後に見るように「真理(truth)の提示」と結びついていきます。
ハイデッガーは『存在と時間』で、生活の空間を考察します。それは長さや広さを数学的に測定できるような空間とは異なり、物の使用によって組み立てられたものです。人間の使用と結びついた物のありかたを「手元性(handiness)」とハイデッガーは言います。この「関わりの関係」こそ、空間においてまず存在論的に開かれたものだ、とハイデッガーは考えます。中立的な位置はあくまでその副産物です。道具は、ただ場所を占めるだけではなく、空間の「秩序」のうちにインストールされているのです。
神殿や橋といった建築は、それがあることで、環境を開き、「領域(region)」を画定します。橋が架かったことで、そこに使用があるようになり、「位置(location)」が打ち立てられ、領域は構成されるのです。
こうした「手元性」「領域」の考えから、再び『芸術作品の根源』に戻りましょう。ハイデッガーはこのように書きます。
作品は、ひとつの世界を立ち上げる(setting up)なかで、その大地(earth)をこちらへ立てる(sets forth)。〔…〕作品は、この大地を、世界という開けたところへ持ち出して、そこにキープする。(ハイデッガー)
「世界/大地」という用語は大仰ですが、神殿についての記述と合わせればわかりやすいと思います。神殿は、それが建っている環境を露呈することで、特有に美的なのです。
さて、便利な道具の「手元性」が、領域の「手元性」を作っているかぎり、それは現象学的には「目立たないなじみ深さ」をもっています。物はあるべき「位置」で自然に使われている限り、ほとんど透明で見えない。むしろ本来の位置から外れたとき(壊れたハンマーをいつもどおり振ろうとする)のほうが、「領域」は露わになります。
芸術はこうした露呈をむしろ引き起こすのです。たとえば神殿を支える岩という「大地」は、もとより不自然で、不気味、なじめないものとして、世界の外へと現れてくるのです。作品が大地を「こちらに立てる」とは、こういうことを言います。またハイデッガーは、大地が手元性の外に出ることを、「世界から退隠する(withdraw)」*26とも表現します。
芸術は、世界と大地とが「闘争(striving, Streit)」する地点へと、わたしたちを連れていくのです。この闘争の中にこそ、芸術作品はあるのです。
芸術作品は、何らかの物質としての性質(materiality)をもちます。そのほうが一般的には、作品にとって「大地」にあたります。物質が便利な物となりうる機能は、芸術においては消し去られます。
しかし物質をただ物質とみなすのは、絵画の色をただ色をみなしたり、音をただの音とみなしたり、立方体を立方体とのみ捉えて切り上げるような、再三批判されてきた「実証主義」です。
芸術作品がもつ物質性は、そこでパフォームされる意味との相互関係を形成するのを目指す自身の関係の中でのみ、美的である。〔…〕意味のいかなる可能な形成も、その物質がもつ事実性を参照し返す。物質がもつ事実性の役目とは、つねにすでに潜在的な意味の充実を示唆して、新たな意味の形成を招き入れることなのだ。
世界と大地との果てしない闘争に作品が存在する――まさにプロセスです。この闘争がもつ「形(Gestalt, figure)」を考えるために、作品という「ゲシュテル(Ge-stell)」が必要だ、とハイデッガーは言います*27。それはつまり作品がそこで真理を位置づけるためにもつ「枠づけ(framing)」なのです。
ところでこの「ゲシュテル」は、『技術についての問い』という著作にも現れる語です。主体が生活の「領域」のなかで、道具的な合理性によって能力を広げていく理解のしかた、それがゲシュテルなのです。
主体が客体を支配するという近代的(デカルト的)な形而上学にも見える後者と、芸術についての前者とで、あえて共通した語「ゲシュテル」を用いることで、ハイデッガーは芸術を、そうした主客の存在論的関係を超えるような「場」と考えようとします。ハイデッガーにとっては芸術も技術も「テクネー」であり、「作る」ことではなく、隠れた存在を明るみに出すという「知のひとつのありかた(mode)」、「露呈(revealing)の方法」*28なのです。
つまり、技術的なゲシュテルが生活を支配してしまうのにたいして、芸術もまたゲシュテルであると置き、むしろそちらのほうが「真理」を露呈させる、とハイデッガーは考えました。
ここからレーベンティッシュは批判します。
ハイデッガーのこうした議論は結局、真理がどうこうという「本来性という隠語(jargon)」(アドルノ)に陥っています。ナチズムをゲシュテルの支配だと解釈していたハイデッガーにとって、その芸術的・「詩的」な反転が必要だったのです。人々が本来の「約束された任務」へ新たに戻るべきとハイデッガーは考えていました。
芸術は〔…〕本質的に歴史的である。〔…〕芸術が歴史であるというのは、それが歴史を根拠づけるという本質的な意味でそうなのである。(ハイデッガー)
ハイデッガーはその歴史観によって、芸術を「詩的な露呈」とみなします。
しかしレーベンティッシュは、「露呈」よりも、そもそも芸術が置かれていた「闘争」のほうを重視します。仮に「真理」と呼ばれうるものがあるとすれば、それはこの闘争において、主体と対象のあいだの際限ないプロセス、「プレイ」のほうです。それはおなじみの、持続的に変化する美的経験、対象との距離、運動です。レーベンティッシュはこの闘争を「敵対的構造(antagonistic structure)」と言い換えています。
さてこのような芸術観のもとで、芸術作品を取り巻く空間は、ハイデッガーにとってどのように考えられるでしょうか。
彫刻論『芸術と空間』が参考になります。ここで作品にとっての空間とは、単に「この作品はここに搬入できるだろうか」というような中立的な体積の話ではありません。
ハイデッガーにとって芸術作品と空間との関係は、そのような「領域」の流儀で位置づけられるものではなく、「相互作用(interplay)」なのです。彫刻作品は、空間のために「空きをつくりだし(make room for)」ます。芸術作品は、領域においてともに緊密な秩序にある物同士に距離を「空け」るのです*29。そこにプロセスなくては芸術作品の論理はありません。
何が美的経験を構成するのか。作品を取り巻くどのような環境が、その環境に「空きをつくりだす」という美的経験をもたらしたのか――このダイナミズムこそゲシュテルです。空間の「からっぽさ(emptiness)」においてこそ、彫刻は場所を探しながら「プレイする(play)」のです。
(サイト・スペシフィックな)インスタレーション・アートは、このようにあらゆる空間芸術に根本的なもの、自己反省的な彫刻の実践を、そのテーマとした芸術です。ヘンリー・ムーアの彫刻よりも、ジェニー・ホルツァーのLEDパネルのほうが、それを達成している……とレーベンティッシュは例を挙げます。「包含」された鑑賞者は、身体のもつ空間、自身の動き、「どのような行為ができるか(possible actions)」という「場」を自覚していき、美的対象への「定まっていない(undefined)」関係のなかで自身を知覚・反省するのです。ミニマリズムにも影響を与えたメルロ=ポンティの『知覚の現象学』を、レーベンティッシュは紹介します。
さて、空間や身体についての現象学的な「サイト・スペシフィシティ」は、同時に中立的なものではありません。なぜなら、空間や身体は、生活世界のなかでつねにすでに意味の染み込んだもの、配置された「領域」、いわば「社会」であるからです。ホワイトキューブが中立的な空間ではないことはもはやおなじみでしょう。
次節では、「サイト・スペシフィシティ」のそのような批評的・政治的な側面へ注目します。
3.2 インスタレーションが介入する政治的・社会的な文脈

Daniel Buren, 1987, 4 Tore in Münster, 大岩撮影
芸術は空間に「空きをつくりだす」。その相手となる空間は、現象学的なだけでなく、公的・制度的な「領域」の空間なのです。サイト・スペシフィックなインスタレーションは、そうした社会的空間に介在し、意味がプレイする「仮想空間(virtual space)」を重ね合わせるのです。
1970年代の「制度批評」は、芸術作品を取り囲む空間自体をテーマとしていました*30。そこでは、ホワイトキューブという「慣習」(ブライアン・オドハティ)やその社会的機能、ギャラリーという「取引の場所」が槍玉に挙げられます。部屋の角にモルタルを流したリチャード・セラ《Splashing》(1968)は、具体的な場所に固着することで「商品としての流通を拒否する」点で、サイト・スペシフィックな作品といえます。
しかし、市場にはサイト・スペシフィックな作品の派生物が出回り、美術館もそうした作品のコピーを購入するようになります。結局、流通を拒否するという当初の理念はなし崩しになっていました。「ただそうした関係から逃げているふり」でしかなかったのです。そのうえ、市場ではなく今度は「助成(コミッション)」に芸術家は依存するようになります。
この助成(コミッション)というものは、芸術家にたいする静かな要求をしばしば含んでいる。ちょうどよく「批評的」な態度と、投資家なり美術館なり封建政府といったパトロンとをうまいこと釣り合わせることを受け入れろ、というものだ。
現在のサイト・スペシフィックな作品は、そうした関係から逃げるのではなく、むしろそうした関係を反省させ自覚させるものになります*31。その意味では初期の作品がもっていた効果を、ビジネスの仕組みに投げ込み得たと言えるでしょう。
美術館にたいしてもおよそ同様です。美術館という権力から逃れられない以上、サイト・スペシフィックな作品は内側からそれを批判します。マイケル・アッシャー、メル・ボフナー、マルセル・ブロータース、ハンス・ハーケ、ゴードン・マッタ=クラーク、ローレンス・ウェイナー……そして本節で詳しく取り上げられるのはダニエル・ビュレンです。ビュレンの作品は、縦縞をもちいて美術館の建築的特徴を強調します。
この、作品がそこに置かれる新しく異なった文脈が、そのたびすこしずつ作品それ自体を明らかにしていくのだ。(ビュレン)
繰り返して言いますが、芸術は文脈から独立して自律しているのではなく、文脈を巻き込んだ解釈プロセスにおいて自律しています。生活空間・制度空間の「領域」にこのように介入し、その印となることで、それを経験する主体がもつ反省的な生産性を示します。
その点で、制度を批判するという「メッセージ」へ作品を帰属させるのは間違っています。ビュレン作品にキャプションが添えられるとき、それは作品の理解を左右するどころか、むしろ作品によってキャプションというもののほうがしるしづけられているのです。「ふだん見えないもののなかで、その場こそが見るべきものであるということ(there is to see in which is usually invisible)」(リオタール)を、ビュレン作品は「不確かに言う(not clearly say)」のです。
そして芸術は、そうした批評的な認識からも繰り返し「退隠」しつづけ、そのたびに新たに解釈の可能性を表します。作品は、理論的主張(これは批評だ)にも、形式的性質(これは形式的な遊びだ)にも還元されません。批評は密接な美的経験に巻き込まれており、作品と解釈の明確な区別などもはやありません。
むしろわたしたちは、フォーマリズム=形式主義(formalism)と内容主義(contentism)という二者択一をこそ拒絶しなくてはいけない。〔…〕ビュレンについて、ストライプ柄の形式的な性質からだけで価値を決めるような批評家は、明らかに彼の作品について誤解している。しかし、彼の理論的な主張によってのみその価値を査定するのも同様に誤っている。〔…〕ビュレンの作品は、鑑賞者が反省のなかでもつ意志、また関わろうとする能力をこそ、積極的に目標としている。
この美的経験の核心にとっては、もはや制度批評云々は本質的なものではない。それは開かれているという点で重要だ。
しかしこの開かれは、鑑賞者のもつ文化的な力量、反省の能力に限界づけられている。美的経験は、万人のもの(universal)ではなくて、物質的・象徴的な特権の相互作用なのだ。こうした共謀性をアドルノは「芸術の罪深さ(culpability of art)」と呼びました。「違う鑑賞者(different audience)」の探求こそ、支配的な芸術概念にたいする批判と考えられるのです。
芸術が依存している「場」を露わにしようとする展開は、1990年代にさまざまな運動に結実しますが、1970年代からすでにその萌芽があったと言えるでしょう。そのようにして1980年代以降には、サイト・スペシフィックな作品は、その具体的に置かれた場所よりも、美的なものの外に何があるかを反省することをテーマとしました。この意味で「こんにち、ソーシャリー・エンゲージド・アートへの転回を明快に象徴している芸術は、インスタレーションを措いて他にない」。アーサー・ダントーはこの特徴を捉えて「利益関心にもとづく芸術(interested art)」と呼びました*32。
インスタレーションはこのようにして、文字通り置かれた場所と、社会的に置かれた場所という二重の「サイト・スペシフィシティ」をもちます。
今日ではそれはアイデンティティ・ポリティクスと関わりますが、レーベンティッシュは、芸術が政治的なステートメントに回収されかねない動向に釘を刺します。
芸術は、直接の政治的なステートメントを言うために、芸術にとって特有な論理を抑え込むようではいけない。そんなことをしてしまうと、美的な意味でやがて致命傷になる。それだけではおさまらない。結局何も政治的な結果などもたらさないのに、献身的な芸術として自らを誤解してしまう。
重要な部分なので、一節をまるごと引用します。
芸術が、直接に政治的なステートメントの名のもとで、その形式的側面をないがしろにすることをモラル的に褒めそやされたりするならば〔…〕、それは――歴史上幾度となく繰り返されてきた――形式主義と内容主義という悪しき二者択一を再生産してしまう。そればかりでなく、ただ内容からその作品の重要性を無理にもちあげようとするようなものは、芸術の概念に値しない。それはほとんどの場合、作品が翻訳しようとしている、当の社会的また理論的な問題のもつ複雑さを、たたき売りするようなものだ。そうした説明芸術=御託芸術(illustrative art)は、最悪の場合、独立して理解することのできない、多くの場合ひどい差別さえ含むその〔政治的〕実態を伝えることは――理論上、ない。むしろ対照的に、その中身(material)(そこに自明な意味がある、とその類の芸術はナイーブに信じているのだ)が伝えるとされているメッセージは、煎じ詰めれば、もともと鑑賞者が持っているだろう常識にすぎない。その非常に単純化された内容からして、この種の「批評」は合唱隊に説教するようなもの、つまりは同じ意見をもつ人間を説得するようなものにすぎない。「芸術らしい」装飾性を排除して――まるで形式というものが、内容への単なるガワであるかのように――大層ご正確にコミュニケーションされえる内容を運ぶことで、芸術が社会的に意味あるものになるわけがない。結局ある対象が美的に、芸術として経験されるためには、それらは必ず、それ自身の形式主義(their own formalism)――その自身のためにあつらえた形式への着目――をも引き起こす必要がある。〔…〕形式は、それがあくまで要素として、意味との緊張関係に入るときのみ、それ自体で美的なものになる。言い換えれば、物質と意味とのあいだであちらこちらへとプレイするような美的経験のプロセスを反省するときにこそ、形式は美的なものとして構成される。すなわち、美的な形式は、一時的な要素をもつ――それはプロセス、生成だ。面倒を避けてその中身へ政治的な内容を読むことは、〔…〕展覧会タイトルが示してくれるキーワードの薄っぺらさのもとで、うんざりするほど繰り返したメッセージを披露するような表現手段へと、多様な作品をまとめて還元するようなものだ。
知覚がすでに意味づけられてある以上、それはすでに政治的でもあるのです。芸術の経験は、自己反省的でパフォーマティヴであるという自律においてのみ、社会的に価値がある。
それはいわゆる「政治的介入」ではなく、むしろそのような実践を中断させて反省させることでこそ、社会的なポテンシャルをもっています。制度批判にせよ、アイデンティティ・ポリティクスにせよ、具体的な内容がプロセスのなかで役割を得るのです。
芸術は、直接に行動へ変換されたり、認識に変換されたりしえないプラクシスと本質的に結びついている。だがそれは恥じるべきことではない。芸術が可能にするスペシフィックな経験とは、距離の経験――美的対象へのいかなる直接なアクセス可能性をも不安定にする経験なのだ。〔…〕美的経験はそのような強度をもつことができるし、そのために、美的なプレイに入り込んだ何かの内容が、経験する主体にとって重要なものであるとき、それは強度と質(quality)を得る。
主体的経験を通じて芸術の経験が構成される以上、そこには必ず社会的な内容があります。インスタレーションはその主体の社会的な起源を示すのです。インスタレーションはその「場」において、具体的な社会的主体に働きかけているのであって、モダニズムが考えるような作品の「超個人的な主体性」とはまったく異なります。
インスタレーションの本体は、具体的なアイデンティティ・ポリティクスと関わり、ジェンダーや民族、階級などによって鑑賞者を分轄します。
利益関心にもとづくいかなる芸術でも、その作品は必然的に、鑑賞者を分轄する=分断する(divide spectators)。(ダントー)
ネットワークのなかで自分がどこに位置するか――ということに、インスタレーションを鑑賞する主体の経験は動機づけられます。しかしそれはあくまで「個人」を目指すのであり、何かに同化させたり、反同化させるものではありません。むしろそうした単純な同化が挫折するような、反省的なパフォーマティヴな経験に置くのです。美的経験は具体的な主体性をスペシフィックに反省し、そうして「美的な主体性(aesthetic subjectivity)」が現れます。真理や倫理に解放されるのではなく、美的な反省のプレイを続ける「場」こそ、芸術の経験なのです。
後半のまとめ
本書後半では、緊張における解釈・反省のプロセスとして進行する美的経験が、「間メディウム性」と「サイト・スペフィシティ」という観点から検討されました。
演劇や映画、音響をモデルとした間メディウム的芸術においては、要素の並置(空間性)が、要素が全体的にもつイメージと緊張することで、解釈・反省のプロセスを賦活しました。またサイト・スペシフィックな芸術は、必ず社会的であるような、作品のもつ場についての反省が、制度批判にせよアイデンティティにせよ、何かの内容を巻き込むことで、主体の自身についての解釈・反省のプロセスを作り出しました。こうしたプロセスをレーベンティッシュは、理論や倫理に回収されず、客観主義的な誤解も免れた「美的経験」と呼びました。
本書について二点付言しておきます。
レーベンティッシュはプロセスとしての「美的経験」を重視するあまり、内容を二の次として軽視しているように見えるかもしれません。プロセスの「構造」という言い方は、やはり形式主義的な態度にも一見みえます。
たとえば2.3.3節の中でレーベンティッシュは、映画技術的インスタレーションがベンヤミン的「アウラ」を復活させているのでは、という考えを、「芸術は大衆文化への単純な対立にはもとづいていない」と退けます。ここでも、アウラ的なものがあるならそれは経験一般だと主張します。こうした議論は、芸術の実際的な文化政治性を無視しかねないように思えます。現代の文化の状況を見るかぎり、レーベンティッシュの考えはあまりに象牙の塔にこもったように思えるかもしれません。
しかし、本書最終節にもあるように、内容は、経験の主体が自身という「場」についての反省を活性化し、「美的主体性」となるために明らかに重要なものです。レーベンティッシュは「内容主義」を拒否します。ある芸術が政治的であるのは、それが直接に(アイデンティティ・ポリティクスや文化政治という)政治的な内容を含むためではなく、その内容によって、主体が自身の政治的なありかたを美的に考え直すためなのです。そのためには、内容が直接に政治的である必要はないし、そこに作品の政治性は求められないのです。
また、レーベンティッシュは「美的経験」を、否定神学的な語彙(汲み尽くせない、果てしない、不定の……)でばかり基礎づけているため、むしろそうした経験をもたらす作品がどう作られるか、という議論には接続しづらいかもしれません*34。それは、作ったとおりに経験されるという客観主義的想定を退ける以上当然ともいえます。
そこで、ビショップの『ある批評史』の結論と比較してこの記事を締めくくろうと思います。レーベンティッシュの経験の不安定さは、定義上、解釈する安定とその反省的不安定化を往復するものでしょう*33。この往復を、ビショップは「抽象的なモデル」と「リテラルな鑑賞者」との緊張である、と擬人化して捉えています。この緊張をビショップは「敵対性(antagonism)」と呼んでおり、レーベンティッシュも3.1節で、大地と世界との「闘争」を「敵対的」と言い直しています。
ビショップはこの二者が「重なり合う」と考え、レーベンティッシュがこの二者の往復を「プロセス」とみなしました。それはまさに、インスタレーションの時空間的なありかたを反映していると考えてよいでしょう。