キャサリン・エルウェスの『インスタレーションと映像(Installation and the Moving Image)』(2015)*1の各章をまとめました。
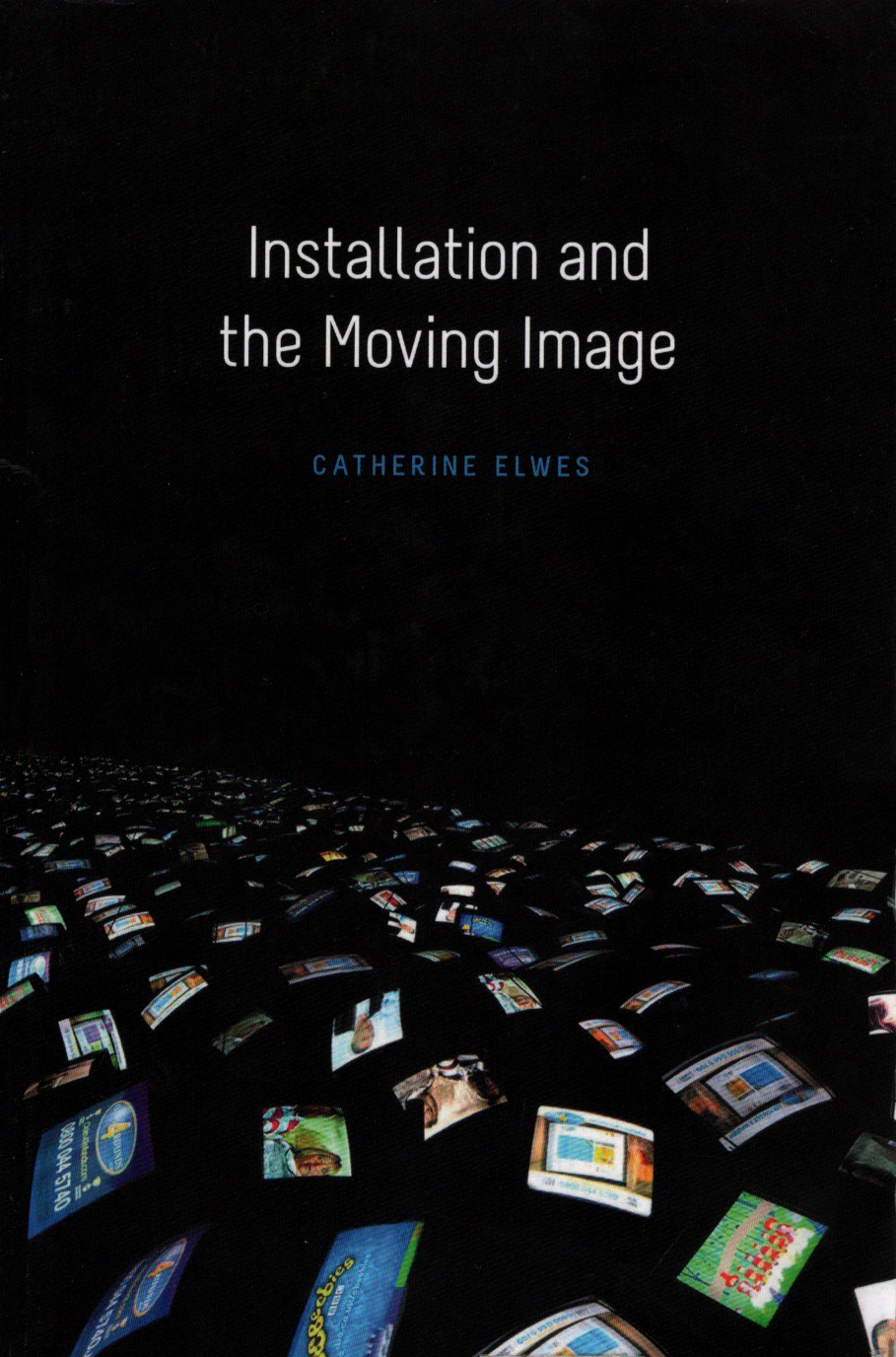
書影
この記事は、インスタレーションに関する文献の要約を公開していくシリーズです。すでにクレア・ビショップの『インスタレーション・アート:ある批評史』と、ユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーション・アートの美学』を紹介しています。
ひとつの理論を検証するレーベンティッシュの著作にたいして、エルウェスの本書は、より事典的な章立てになっています。全12章それぞれに「建築」「絵画」などのトピックが割り当てられ、インスタレーションの形式を含む映像*2表現との類比関係を扱います。
ビショップの著書も4つのテーマ史に分かれていましたが、本書は各章もまた複数の節から構成され、通貫した主張があるというより、幅広い実践を紹介する性格が強くなっています。
その点では、12講義ぶんの大学の通年授業のような本だと思います。
各章の目次は以下の通りです。非常に簡潔です。
本書は第7・8章あたりを境にして、前半と後半で印象の変わる本です。
導入部でエルウェスは、空間的な気づきをもたらすインスタレーションにたいし、しばしば別の時空間へ没入される機能をもつ映像を「本質的な敵」と位置づけます。これは、イメージへの没入と支持体への反省という二重性(doubleness)というテーマで、前半の各章ではよく現れます。この点はビショップやレーベンティッシュにも通じる点だと思います*3。
インスタレーションが、ギャラリー空間を定めている天井や壁などへの注意をうながすいっぽうで、そこで投影されるイメージは、それがぶつかっている所与の表面の存在をまさに強めながらも、色とりどりの光の万華鏡をもちいて、具体的なオブジェクトや取り付けられた仕切りを、溶解・消散・脱物質化させる。
以降論じたいのは、映像インスタレーションが、鑑賞者のもつ知覚的な二重性、不信を宙づりにして二つの現実を同時に楽しむ人間の能力を具体的に示してくれるものである、ということだ。
いっぽう後半では、構造映画やエキスパンデッド・シネマ、またそれを踏まえたビデオ・インスタレーションなど、主流映画・テレビにたいして現れた、カウンターカルチャーや支持体への反省を主に重視した映像表現の潮流が中心的な話題になります。同時に映像におけるフェミニスティックな形式的な実践もこまめに触れられています。映像作家・キュレーターでもあり、また映像学科の教員でもあるエルウェスの専門といってよい領域です(本稿は章の順に紹介しますが、正直前半よりも後半のほうが充実しています)。
その点で本書は、実際に制作をする方に刺激や益のある本だと思います。
映画的な本物らしさのトリックの中心にあるのは、その動画の中や周りにある、現実のイリュージョンを作り出している当の技術的な手段の隠蔽である。
映像インスタレーションは、物質的な現実と、現実ではないと理解されながらも感覚と想像に現れるものとのあいだの境目の空間を占めることで、ある曖昧さのなかで営まれる。
本書の美点は、特に後半、非常に多くの、かつ国内ではまだあまり紹介の進んでいない作家が紹介される点です。ミニマリズムや関係性の美学といったおなじみの領域より、20世紀後半の実験映像史にもとづいており、インスタレーションの一ジャンルというより、映像装置をもちいた表現のひとつの様式として捉えられるでしょう。ビショップの著書ではテーマになぞらえるあまり不十分で恣意的な作品紹介も少なくありませんでしたが、エルウェスの本書はより丁寧に作品のディテールを伝えています*4。また、白黒ですがある程度図版が充実しています。
同時に、ビショップにおけるテーマ史や、レーベンティッシュにおける美学理論のような、あえて各章単位でまとめあげるもののない著書でもあります。本稿は各章のおおまかな中身と、目立つトピックに重点を絞って紹介します。
1 建築

Neue Nationalgalerie, (c)Staatliche Museen du Berlin/Maximillian Meisse, berlin.de
インスタレーションでは、ある領域の中を鑑賞者が歩き回る、という点でエルウェスは「建築」をはじめのトピックに置きます。形状だけでなく、その素材や耐久性、換気・照明・経路・外観、さらに建物の文化的な位置づけなどが影響すると前置きしてから、本稿では主に物理的な様相を取り上げます。
たとえばマリー=ジョー・ラフォンテーヌ《We Have Art so that We Do Not Perish by Truth》(1991)は、ドーム天井の凹んだ部分に炎の写真を貼ることで、建物が燃え上がっているように見せるインスタレーションです。他にも窓やドアに映像を投影するなど、映像と建築との関係に注目した作品を紹介しつつ、同時に建築が身体の動きを傾向づけていく点をエルウェスは取り上げます。第二帝政パリは軍隊の動きを優先した都市計画だったように、映像インスタレーションもまたそのホストである建物からの商業的な要請と切り離せない点が指摘されます。
エイゼンシュテインが映画の先祖に、古典建築がつくりだすモンタージュを置いたように*5、そうしてデザインされる「創造的幾何学(creative geographies)」(フェイ・フーラハン)は、(映像)インスタレーションだけでなく、教会の身廊に並べられる絵画とも比べられます。「スクリーンにもとづく情報から組み立てられる」物語と、「空間それ自体」がもつ筋運動感覚的な物語とのあいだの「認知的な二重性」をエルウェスは強調します。さらにそうしたデザインは、新築にせよリノベーションにせよ、近代の美術館やギャラリーにおいて動線と効率を確保する「順序性=秩序性(orderliness)」の構築にも繋がります。エルウェスはミース・ファン・デル・ローエがベルリンに設計した新国立ギャラリー(Neue Nationalgalerie) の透明な構造が、鑑賞者自身による作品関係の編集を促す点を指摘します。そうした断片の組み合わせという空間についてよく表している作品が、フッテージがコンピュータでランダムに組み合わされるスタン・ダグラスの映像作品《Journey into Fear》(2001)です*6。
の透明な構造が、鑑賞者自身による作品関係の編集を促す点を指摘します。そうした断片の組み合わせという空間についてよく表している作品が、フッテージがコンピュータでランダムに組み合わされるスタン・ダグラスの映像作品《Journey into Fear》(2001)です*6。
動画インスタレーションの作家は、作品のあいだを鑑賞者がどう動くかを、物理的な障壁や、身体の通る狭い通路によって、どの程度までコントロールするかを考える必要がある。仕切りのない(open-plan)展示においては、作品のあいだに漏れる音響・照明まで考慮に入れる必要がある。それらの相互浸透が個別の作品の解釈や、展示全体の性格にどこまで影響するかを予測しなくてはならない。この問題はしばしばグループ展の悩みの種になっている。サウンドトラックのふいの重なりがあると、作品どうしはたがいに敵対関係をもってしまう。物語的な要素やドラマ化、インタビューに依存した作品、あるいは静けさを必要とするより形式的な作品は、しばしば他の展示物からの照明・音響の干渉に影響を受ける。その結果、ますます現代の実践者たちは、ギャラリーのなかに隔絶された映画館=上映室(sealed cinema)を作りつけるようになる。
2 絵画
"The Quintet of the Astonished" by Bill Viola (excerpt) from Urban Video Project on Vimeo本章では、映画(映像)と絵画との比較を中心に組み立てられます。たとえば映像も絵画も、インスタレーションのなかで複数置かれれば、フレームを越えて空間的な関係をもつ。あるいは逆に、絵画も映像も正面性をもっており、そこでパースペクティヴ(遠近法)をもって表される空間は、インスタレーションの身体経験になかなか侵入しない。
絵画にインスタレーションの性格が現れ始めるのは、他人の生活を覗き込むような「活人画(tableau vivant)」です。マルセル・プルーストが小説にもしたように、窓越しに人々の暮らしを覗き込むような経験が、映像インスタレーションにおける、映像に直面したときの「身体的な離脱感(physical detachment)」と結びつくでしょう。
鑑賞者の身分が問題になれば、絵画における視覚的な奥行きと、絵の具のある表面とのあいだの二重性がここでも問題になります。クロード・モネ《睡蓮》(1899)にあるような、イリュージョンと現実の同時の知覚について、エルウェスはリチャード・ウォルハイムの「二重性の経験(twofold experience)」概念を紹介します。
もはや鑑賞者は絵画にたいして理想的な立ち位置をもたず、自由に動き回ります。解読しやすいイリュージョン(ミメーシス)から表面の現実まで、鑑賞はグラデーションをもち、これはインスタレーションの前触れになります。印象派絵画以降における「表面」の問題は、スクリーンとブラウン管とのあいだにもなお横たわっています。キュビスムや未来派の絵画における「運動の分析」の問題も、エドワード・マイブリッジの連続写真からビデオにおける残像効果(tracer effect)にまで関わります。
そうしたイメージに作られるものとイメージを作るものとの二重性は、そもそも非識字層にも歩くだけで物語が伝わるようデザインされた教会絵画と結びつくものでした。ビル・ヴィオラの《Passion 》シリーズ、《Catherine’s Room
》シリーズ、《Catherine’s Room 》(2001)が紹介されます。
》(2001)が紹介されます。
あるいはジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングをアラン・カプローが「環境」と評したことを引き、絵画におけるフレームという、イメージの(再)構成のための制限の後退をエルウェスは取り上げます。20世紀には画家から映像作家に転化したものも多く、そうした違いをアンドレ・バザンも、自己充足した「求心的(centripetal)」な絵画にたいする、限界づけられず転回する「遠心的(centrifugal)」な映画、という対照をします。1920年代・1930年代には抽象映画が登場します。同様に抽象表現主義絵画も、奥行きよりも平坦な表面上の、線や形、テクスチャ、色などの流れを積極的に使用します。
何が動いているか。それは観客だ。スクリーンの前でじっとしている観客が、結局動いている当のものなのだ」(スティーブン・ヒース)
ここ50年の映像インスタレーションは、絵画から引き出された表象のレジームを何度も繰り返している。盛期ルネサンスにおけるジョット、ジャクソン・ポロックの抽象表現主義や、ケネス・ノーランドのカラー・フィールド、ブリジット・ライリーのオプ・アートといった作家からインスピレーションを得ている。フレームとフレーミングの魅惑は、1960年代と1970年代のデイヴィッド・ホール、タマラ・クリコリアン、トム・シャーマン、さらに後の時代ではパトリック・ケイラーやフランシス・アリスといった初期のビデオ作家の作品にも見いだされる。
3 彫刻
Anthony McCall: Solid Light Works / Pioneer Works, New York from VernissageTV , YouTube
, YouTube
ここまで見たように、あくまでエルウェスの専門は映像で、映像インスタレーションを扱うさいにも、映像と建築、映像と絵画の関係越しに論じている節があります。そのため建築や絵画史の扱いはややステレオタイプ的で物足りないところがあります。本章も彫刻との類比を論じるにはややぎこちなく、むしろモダニズム批評の枠組みが色濃く出ています。
クレメント・グリーンバーグが絵画や彫刻から物語のイリュージョンを取り除こうとしたことと、同様に映像においてイリュージョニズムを支えるメカニズムを暴露しようとした1960年代・1970年代の構造映画作家が比較されます。とはいえ、スクリーンにもとづくインスタレーションでは、グリーンバーグ的なメディウムの純化は難しくなっています。
エルウェスは、1920年代以降の「彫刻」カテゴリがだんだんと「遺漏(erosion)」したことが、映像表現にも関わっていると論じます。エル・リシツキーやラウシェンバーグ、ドナルド・ジャッド、ロバート・モリスというおなじみの名前を出しつつ、彫刻もまた「求心的」に意味を作るのではなくなったことを指摘します。彫刻的オブジェクトの唯一性・自律性の瓦解は、20世紀初頭から起きていたことで、古くはマルセル・デュシャン《泉》(1917)から、アプロプリエーション、1960年代におけるハプニングやアッサンブラージュ、エンヴァイロンメント、メディウム同士のハイブリッド化などが挙げられます。
たしかに、マイク・ケリーやフローレンス・ピークの作品など手で作ることの彫刻的要素はなおも残り、フェミニズムの文脈でもそれは「ホームメイド、アイムアフレイド」という概念のもと工芸とも接続しますが、しかしいっぽうで、古くはクルト・シュヴィッタースの《メルツバウ》、さらにヘリオ・オイティシカやトモコ・タカハシらのインスタレーションにおいて日用品が彫刻同様の重要性をもつようになった点で、人工のオブジェクトという点を彫刻のステータスとして維持するのは難しくなりました。さらにアヴァンギャルド映画やビデオの登場はそれに追い打ちをかけたと言えます。
彫刻(オブジェクト)との関係でいえば、映像やインスタレーションが、市場で販売されるという資本主義的な命運を拒否するという点で、マルクス主義的理念をもつ、としばしば言われます。映像は無限に複製される点で、やはり市場価値に抵抗するとされました。
いまや芸術家が作るインスタレーションは、そのなかのいかなる彫刻的な構造も、一時的で、廃棄可能で、そして制度的にも収蔵不可能であるようなものであり〔…〕
いっぽうで、彫刻がある空間に置かれることと、映像がいかにプロジェクションされるか、あるいはどのようにモニター上映されるかということは似た問題を持っています。「見ることの、中心化と分散のあいだの不安定な振動」(アレックス・ポッツ)というインスタレーション的な二重性は、彫刻のインストールにおいてすでに準備されていました。マイク・ネルソンやクリストフ・ビュヘル、ヨーン・ボックらの迷宮のようなインスタレーションが映像作家とともに展示された「Dylaby」展(1962, アムステルダム市立美術館)を引き合いに、ギャラリー空間自体が以来問われるようになったことをエルウェスは指摘します。鑑賞者の情動を動かし、また人体を問題にすることで、彫刻は展示された空間と美的な関係を結びます。アンソニー・マッコールのインスタレーションにおける光の円錐のサイズもまた、人体との比率が重要です。
映像インスタレーションはこのような「演出された注意の特異なパターン(particular pattern of directed attention)」(ダニエル・ミラー)「鑑賞者のための振り付け(a choreography for the viewer)」(フィリダ・バーロウ)を設計する点で、建築や彫刻と通じるところがあります。
このように彫刻は、物理的な要素の安定した配置の結果である――それが静的であろうと、予め定められたキネティックな運動をループするものであろうと。それは美的に、コンセプチュアルに、歴史的に重要な点を具体化するように知覚される。彫刻は、現前することで鑑賞者を関係をもつ。鑑賞者自身の身体と関係するそのオブジェクトと、またそのなかに彫刻・鑑賞者両方を囲い込んでいるような延長した境界とを同時にみてとることで、その空間において、鑑賞者は方向づけられる。
本章終盤はかなり話が散らかります。映像の持続時間を彫刻のボリュームに比喩したり、また音響や、映像装置の話が取り上げられいます。映像装置については以降の章でくわしく取り上げられます。また思弁的実在論への参照は、別の章にもありますが、ややミーハーな言及にとどまり、実質的な議論になっていない印象があります。
4 パフォーマンス
ここまで準備されてきた、鑑賞者(性)をデザインするというテーマが、本章で、パフォーマンスにおける、パフォーマー(アーティスト)と鑑賞者との関係という点で、より重要になっていきます。
どんな種類のインスタレーション・アートも、参加者でありまた芸術に精通した消費者でもある、という公衆(public)の役割を強調する。パフォーマンス・アートもまた同様に、鑑賞者との協働したインタラクションを強調するが、しかし美的な意味が具現化する焦点として、芸術家ないしその代理人が特権化されている。芸術家は、参集した人々(company)を迎え入れ、人間的で関係的な反応を要求するあきらかなプレゼンスとなる。
この観点は後の記述で「演劇性(theatricality)」の議論に結びつけられますが、アーティスト自身の現前も問題とする点で非常にクリティカルだと思います。
1960年代、従来の演劇の伝統から外れ、ギャラリーで行われるパフォーマンスでは客席と舞台の分離はなく、鑑賞者とパフォーマーは同じ空間にいます(もちろんこの問題は演劇の内部でも別の形で取り組まれてきました)。鑑賞者がこのように「アクティベーション」されると同時に、パフォーマンスもただ役を演じるというより、そこで生成する行為となります。スチュアート・ブリズリーやローリー・アンダーソン、マリーナ・アブラモヴィッチらがその例に挙げられます。
たいして映像インスタレーションでは、パフォーマンスのもつレトリックにたいして、鑑賞者の分離が維持されています。アラン・カプローのように環境のなかへの没入をもたらすわけではなく、実際の身体の空間と、ビデオの中の空間とは、やはり「二重の意識(double consciousness)」(アンドリュー・ユロスキー)を引き起こします。
たいしてライブのインスタレーションでは鑑賞者の参加が重要になります。「関係性の美学」(ニコラ・ブリオー)は作品における鑑賞者や共同体の社会的なインタラクションにもとづきます。
そもそもパフォーマンス・アートは演劇の外にも、1910年代のダダや未来派、シュルレアリスムの実践において群発し、1960年代のフルクサスにも残響していたイコノクラスムにも源流をもちます。あるいは、テクノロジーの発展とそのイメージ、そしてまた婦人参政権運動をはじめとした政治的パフォーマンスにも源流をもちます。コンスタンス・リットン の自傷パフォーマンスは、アントナン・アルトーの残酷演劇とも響きながら、アブラモヴィッチやレティシア・パレンテ《Marca Registrada/Trademark
の自傷パフォーマンスは、アントナン・アルトーの残酷演劇とも響きながら、アブラモヴィッチやレティシア・パレンテ《Marca Registrada/Trademark 》(1974)、ジーナ・ペイン《Psychic Action》(1974)、ソニア・ノックス《Echoes from the North》などの身体的痛みを伴なうパフォーマンスにも結びつきます。
》(1974)、ジーナ・ペイン《Psychic Action》(1974)、ソニア・ノックス《Echoes from the North》などの身体的痛みを伴なうパフォーマンスにも結びつきます。
パフォーマンスにおける、芸術と生活や政治との融合は、1950年代のフルクサスのハプニングや、1960年代・1970年代におけるギルバート&ジョージやジュディ・シカゴ、カプローらの運動によって推し進められます。そこでもアーティスト自身の身体が提示されることが、鑑賞者どうしの自覚・緊張を促します。オノ・ヨーコ《Cut Piece》(1964)のように、女性アーティストの参加はフェミニズム運動とも結びつきます。マイノリティの身体の問題にも触れたうえで、ペギー・フィーランやジュディス・バトラーの「パフォーマティヴィティ」概念を紹介しつつ、個人のエージェンシーを賦活させる力が、リアリティ・ショーやSNSなどのテレビ番組においては社会的な抑圧の一種にも転化していることをエルウェスは指摘します。
そして、1990年代のトレイシー・エミンらYBAs、2000年代のティノ・セーガルらパフォーマンスの再興に触れつつ、「耳目を惹くパフォーマンス・イベントは、資金難の公共機関のために、相対的に安っぽい評判を稼ぐ。国際的な美術館・ギャラリーのネットワークのなかでたしかにこれは近年の成功していることがいえる」と、そのメディアジェニックなプロモーションの側面も指摘します。
最後に、映像インスタレーションとの結びつきとして、人間を含む一時的な組み合わせ、建築・社会・制度にささえられたライヴ性、直接のインタラクションなどを挙げます。しかしインスタレーションではアーティスト(やその代理人)が脚光を浴びるわけではありません――ヤネス・クネリスの馬にせよ、ヴァネッサ・ビークロフトの裸のモデルにせよ。アーティストはせいぜい、映像のなかにシミュレーションされた存在になります。後の章でも取り上げられるジリアン・ウェアリングや、あるいは1970年代のケヴィン・アサートン、モナ・ハトゥムら中継やビデオを用いた映像作家などがその例に挙がります。ローズ・ガラード《Beyond Still Life 》(1980)は、映像機器をもちいたパフォーマンス・インスタレーションで、自身の頭部や肩からとった石膏像と、作家自身とが、ライブカメラで中継されたイメージにおいて混ざり合う…といった内容です。パフォーマンスにおける映像イメージの複製や歪曲・再文脈化は、先述したようなパフォーマンスにおけるフェミニズムとの関係とも呼応します。
》(1980)は、映像機器をもちいたパフォーマンス・インスタレーションで、自身の頭部や肩からとった石膏像と、作家自身とが、ライブカメラで中継されたイメージにおいて混ざり合う…といった内容です。パフォーマンスにおける映像イメージの複製や歪曲・再文脈化は、先述したようなパフォーマンスにおけるフェミニズムとの関係とも呼応します。
5 映画史
The Influence Machine - Tony Oursler from MAGASIN III Museum on Vimeo本章は前半のなかでは最も長い章です、以降の章がすべて基本的に映像や映画を主題とする点からも、むしろ前章から本章にかけてを本書の「遅いオープニング」と位置づけてよいでしょう。
エルウェスはまず、映画の前身となるものを一挙に取り上げます。プラトンの洞窟の比喩、カメラ。オブスキュラ、マジック・ランタン、初期のカメラ、さらに初期の映画カメラなど……そうした映像の先祖ではしばしば影や幽霊による異界のイメージがもたらされますが、たとえばギル・イーザリー《Aperture Sweep》(1973)ではプロジェクターの光によって作る、その前にモップを持って立つアーティスト自身のシルエットを用いています。あるいはトニー・アウスラー《The Infinite Machine 》(2000)では、ドライアイスの煙に、ファンタスマゴリー興行主エティエンヌ・ロベールソンや、テレビ放送の発明家ジョン・ロージー・ベアードらの顔を投影する映像インスタレーションです。また書割のなかを小舟で移動する「プレオラマ」のような19世紀のパノラマ娯楽は、現代のフライトシミュレーターや、ビル・ブランド《Masstransiscope
》(2000)では、ドライアイスの煙に、ファンタスマゴリー興行主エティエンヌ・ロベールソンや、テレビ放送の発明家ジョン・ロージー・ベアードらの顔を投影する映像インスタレーションです。また書割のなかを小舟で移動する「プレオラマ」のような19世紀のパノラマ娯楽は、現代のフライトシミュレーターや、ビル・ブランド《Masstransiscope 》(1980)にも結びつきます。あるいは19世紀前半の、ゾートロープやプラクシノスコープ、ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールのジオラマなど視覚玩具が現れ、そのスペクタクルは「アトラクションの映画」(トム・ガニング)にも引き継がれました。いっぽうでパノラマを含む装置のライブ性はその後の実験映画・ビデオ作品でも登場しました。ゾートロープの再創造ともいえるマット・コリショウ《The Garden of Unearthly Delights
》(1980)にも結びつきます。あるいは19世紀前半の、ゾートロープやプラクシノスコープ、ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールのジオラマなど視覚玩具が現れ、そのスペクタクルは「アトラクションの映画」(トム・ガニング)にも引き継がれました。いっぽうでパノラマを含む装置のライブ性はその後の実験映画・ビデオ作品でも登場しました。ゾートロープの再創造ともいえるマット・コリショウ《The Garden of Unearthly Delights 》(2009)のように、そうした系譜を踏まえたインスタレーションでは、イメージの没入と、装置への気散じが同居します。
》(2009)のように、そうした系譜を踏まえたインスタレーションでは、イメージの没入と、装置への気散じが同居します。
エジソン、アリス・ギー・ブラシュ、リュミエール兄弟や、ジョルジュ・メリエス、ジェンキンス&アーマット、バート・エイカーなどごく初期の映画作家に見られる「瞬間の映画」(ガニング)の性格は、20世紀後半の映像やインスタレーションにおいても好まれます。しかし、それはたしかに鑑賞者に驚異の感覚を与えますが、《ラ・シオタ駅への到着》で観客が逃げ惑ったというエピソードに象徴される鑑賞者の受動的受容のモデルは、鑑賞者を見くびっているとガニングは釘を指しています。実際リュミエール兄弟は、コマ送りから加速して映像にしたり、逆再生で見せたり、その人工性を明示していたとあります。
とはいえマリオ・スルガンによれば鑑賞者は映像的驚異より物語を好むようになり、たしかに現在のCGI効果などにも「美的な驚愕(aesthetic astonishment)」は残りますが、主流は物語映画が発展していきます。1910年代から1920年代にかけて軌道に乗り、ショット同士は照明やモンタージュによって「壊れない繋がり」を保ちます。D.W.グリフィス『淋しい別荘』(1909)のマルチショットの登場や、その後の移動カメラの登場、撮影スタジオの拡大、音響の導入が、自然主義的な映画を成立させます。そうした映画の文法は、クリスチャン・メッツによる鑑賞者性の批判的研究に影響されながら、1960年代以降実験映画・ビデオ作家のイデオロギー的な標的ともなります。とはいえ反物語性は、20世紀を通してヨーロッパの芸術映画にも現れ、フランソワ・トリュフォーや「カイエ・デュ・シネマ」誌をつうじて、ファイン・アートにも通ずる「作家(auteur)」概念に支えられます。ドイツ表現主義やダダ、シュルレアリスム、印象派などの映像作家が登場します。ルイス・ブニュエルやマヤ・デレンらが挙げられます。
この時期の映画製作のプロセスが、ハンス・リヒター《Rhythmus 21 》(1921)のような1920年代の抽象映画をつうじて、1960年代・1970年代のエキスパンデッド・シネマの実践を準備します。これは第9章で詳しく取り上げられます。左派イデオロギーが文化労働者の多くを奮起させるのは1960年代・1970年代以降ですが、とはいえソビエトロシアにおいても(映画製作)技術者は革命性をも併せもっていたことが指摘されます。第1章で援用されたエイゼンシュテインの映画観を思い出します。
》(1921)のような1920年代の抽象映画をつうじて、1960年代・1970年代のエキスパンデッド・シネマの実践を準備します。これは第9章で詳しく取り上げられます。左派イデオロギーが文化労働者の多くを奮起させるのは1960年代・1970年代以降ですが、とはいえソビエトロシアにおいても(映画製作)技術者は革命性をも併せもっていたことが指摘されます。第1章で援用されたエイゼンシュテインの映画観を思い出します。
インスタレーションはその定義からして、ほとんどモンタージュの一例といえる。それは、押し出され空間化された全体性のなかに含まれる要素が隣接したことによる相互作用である。
だがすでに強調したように、インスタレーションにおける出会いのドラマはしばしば、フレームのなかの要素の対照から、物質的・建築的現実の異化効果とスクリーン上のイリュージョン的な現象とのあいだの緊張へと移っていく。
『ナポレオン』(1927)のマルチスクリーンをはじめとして、アベル・ガンスはさまざまな撮影技法を試した映画監督ですが、こうした実践は内視鏡を用いたモナ・ハトゥム《Corps Étranger》(1994)と比較できるでしょう。実験的な作風においては、撮影技師はリアリズムのために隠されるのではなく、その身体によるイメージであることが強調され、むしろ共感的な同一化のための「空間」を開きます。
撮影において、カメラと主体、さらに目・身体との三者関係が作られます。映画の鑑賞者はそのような空間的な要素を把握したうえで、そうした装置もろとも無意識に追いやっています。映像に合わさるオーディオトラックも同様です。このような「意識的な幻覚」(ジャン・グーダル)を引き起こす不信の宙吊りが、映画の空間的パラメータにこそもとづいている、とエルウェスはまとめています。
インスタレーションには、2つの対立する力が戯れている。断片化と一貫性だ。空間の連続性は、その作品が内的なドラマをもち、またそれが舞台に上がるために用いられる。そのようなドラマは、広い領域から引き出されるばらばらの要素から成り立っている。音響は、音楽や語りといった形でも同様に、アンビエントなものとして、映画、インスタレーションいずれもにおいて、その統合的な性格のためにしばしば動員されている。音響は、インスタレーションにおいて物理的に離れた要素を引き結ぶし、映画のオーディオトラックは、あるシーンを次のシーンに結びつける。場所や登場人物の、潜在的には非論理的なはずの並置を合理化させてなめらかにつなぐ装置として用いられる。
ばらばらの要素を繋ぎながらもそこには「絵画的な流れ」がある、という映画の「二重の性質」をエルウェスは指摘します。映画のイリュージョニズムはつねに実験の対象であり、「知識の条件」や「経験の直接性」について(アネット・ミケルソン)、鑑賞者に反省させます。
6 フィルムとしての映画
24 HOUR PSYCHO from
KunstmuseumWolfsburg , YouTube
, YouTube
本章は前章から連続して、のちのエキスパンデッド・シネマ(第9章)やインスタレーションへつながるような、1960年代の実験的な映像作品について扱います。広く左派・フェミニズムのイデオロギーのもとで、映画の文法を脱構築する向きがあります。
まず「自然主義」が主題になります。初期映画では映画がイリュージョンでしかないことは意識されながら、物語映画ではそうした自己反省的なショウマンシップは後退し、照明が暗くなって投影機が見えなくなるように、注目はスクリーン上のイメージに集中されました。クリスチャン・メッツやジュリアーナ・ブルーノ、ミーケ・バルらの研究によって、イメージにたいする鑑賞者の位置・態度が研究されました。「空間と物語とが統合されているという知覚への欲望」(ティム・オライリー)に駆られた鑑賞者は、シーンに次々一貫した意味を読み込むよう動機づけられます。そうした黙って座っている「受動的な鑑賞者性(passive spectatorship)」は、イデオロギーの影響を受けやすいとされ、主流映画やテレビはマジョリティによる教化を密輸するとして批判されました。それは2000年代のスラヴォイ・ジジェクによる批判まで続いています。
そうした状況は精神分析をつうじてモデル化されたり、またフェミニズムの観点から、男性の窃視症的な視線として批評されます。その代表的な議論にローラ・マルヴィのエッセイ「視覚的快楽と物語映画」(1973)が挙げられます。女性の鑑賞者は、窃視症的な男性の視線に能動的に関わりながらも、そこで対象化・性化されたヒロインへも受動的な同一化をもちます。ここでもイメージへと装置へとの鑑賞の「二重性」があることに注目しましょう。
1960年代から1980年代は「脱構築」批判が援用され、西洋の文化的慣習・二元対立・本質主義が批判されます。鑑賞者をイデオロギーに従順な消費者から「政治的な主体」へ変容させることを芸術家はもくろみ、単線的なストーリーテリングや娯楽性は放棄されます。誇張した素人の演技を用いたり(スチュアート・マーシャル)、全方向ショットをあえて用いたり(マルヴィ)した作品が登場します。あるいはジェイン・パーカー《I Dish 》(1982)やリズ・ローズ《Light Reading》(1978)がスクリーンに映る女性が鑑賞者を見返すような「視線を去勢する」戦略もとられます。そういった作品は、実験的作品によくあるわかりづらいものではなく、物語や視覚的情景によって見やすく仕上がっていました。
》(1982)やリズ・ローズ《Light Reading》(1978)がスクリーンに映る女性が鑑賞者を見返すような「視線を去勢する」戦略もとられます。そういった作品は、実験的作品によくあるわかりづらいものではなく、物語や視覚的情景によって見やすく仕上がっていました。
映画の装置やその機能を見せ、文法を破るような作品が、1960年代末からこのように積極的に作られることになります。流れの寸断、画と音の分離、不快なオーディオ、セットやカメラ操作、さらにフィルムや編集過程、プロジェクションの暴露……。
〔…〕映画というものの理念は、技術、空間(社会的・物理的)、そして特にエキスパンデッド・シネマやインスタレーションのプロジェクトとの協調点である鑑賞者の経験などを巻き込んだ、タイムベースドな投影の出来事をいうに等しいとされた。
映画の記号は指示対象から引き離され、「フィルムとしての映画(film-as-film)」に直面した鑑賞者は、みずからの知覚のプロセスや認知のメカニズムを反省するようになります。アメリカやカナダの構造映画、イギリスの物質主義映画は映画の物質性やその形式に注目し、また前章でも触れたように、カメラ・編集の技術を活用して、ストップモーションやタイムラプス、長尺映像など、物語の時間の一貫性が破壊されるような実践も増えました。クリス・ウェルズビー《Park Film》(1972-1973)やアンディ・ウォーホル《Sleep 》(1964)がその例に挙げられるでしょう。ダグラス・ゴードン《24 Hour Psycho
》(1964)がその例に挙げられるでしょう。ダグラス・ゴードン《24 Hour Psycho 》(1995)やクリスチャン・マークレー《The Clock
》(1995)やクリスチャン・マークレー《The Clock 》(2010)、ヴィオラ《The Passions》(2003)もその系譜にあります。さらには反復や逆再生、重ね焼き、ループ、またフィルムを直接擦ったり着色したりする実践もありました。
》(2010)、ヴィオラ《The Passions》(2003)もその系譜にあります。さらには反復や逆再生、重ね焼き、ループ、またフィルムを直接擦ったり着色したりする実践もありました。
このような実験的な検討が映像インスタレーションにも持ち込まれることで、文字通りの空間や時系列的な時間から鑑賞者を抜け出させる点をエルウェスは指摘します。
7 構造映画:凋落と再評価
前章でとりあげた構造映画について本章はクロースアップします。あくまで映像メディアに収まる構造映画(本章)と、よりインスタレーションに近しい実践となるエキスパンデッド・シネマ(第9章)とのあいだに、鑑賞者性の問題(第8章)が挟まれていることから、この3章にわたる構成が、本書において中心的な、映像インスタレーションについての議論になっています。
テレビやインターネットに比べて長く観られ、また物語をもつ映画は、つねにその物質的現実との緊張によって、鑑賞者を自己反省的にさせやすいものです(主流物語映画が受動的な鑑賞者性を促進したとは論じられたとはいえ)。映画のリアリズムは、音楽や演技、字幕のちょっとした失敗によってすぐに解けてしまいます。そうした効果による反省が、1970年代・1980年代のテレビでもあえて自己反省されたように、鑑賞者が自身の「鑑賞者性(spectatorship)」に気づくような*7、実験的で反イリュージョン的な要素の利用は、従来の映画史でもつねに存在しました。たとえばバスター・キートンの作品や、あるいはパウエル&プレスバーガーによる映画『A Matter of Life and Death』(1946)がその好例です。
いっぽう、主流映画のリアリズムの閉塞を前提にした構造映画のほうこそ、いくらかユートピア的な楽観性が見受けられるといえます。ただ部屋を映したピーター・ギダル《Room Film》(1973)、何も映っていないナム・ジュン・パイク《Zen for Film 》(1964)などは、ただ快楽から退隠することで鑑賞者に政治的な行動を促すという楽観的なもので、実際にはむしろそのほうが独裁者的で、裏目に出ました。
》(1964)などは、ただ快楽から退隠することで鑑賞者に政治的な行動を促すという楽観的なもので、実際にはむしろそのほうが独裁者的で、裏目に出ました。
快楽のエリート主義的な禁止に支えられたそうした様式は、映画の装置へのフェティッシュもあいまって、もはや商業的搾取への対抗にもなることはなく、ポストモダン前夜の文脈において、結局表層的な装飾へと溶解しました。むしろそれは、主流映画・テレビによって逆にアプロプリエーションされ、ハリウッドでは抽象や手持ちカメラ、断片化を物語のために活用した作品が登場しました。結局構造映画や物質主義が望んでいた鑑賞者の政治的反応とは、主流文化がむしろ完全に望んでいるわけでもなかった鑑賞者の反応のコントロールと、同じ穴のむじなだったのです。
いっぽうで、その形式的発展への貢献を、ティム・マクミランやニッキー・ハムリンら後出の作家に再評価され、1980年代には第2世代の作家を輩出しました。反物語性よりも、アイデンティティ・ポリティクス、カルチャーアイコンと情動、個人的記憶などが主題となり、ストーリーテリングや絵画主義なども拒否されませんでした。映画史や絵画・写真、広告などを素材に、性や民族性を負った身体が重要な要素として採用され、「色々背負った(loaded)」メディウムとして映画は捉えられました。とはいえ現在では、かつてのラディカルな政治性は色薄くなり、視覚的なスタイルをめぐるようになったとエルウェスは注記します。
形式への批評的着目が欠如すれば、それは政治的な関わりへの貧しさを伴い、倫理的な中立性の強要へと至る。
8 鑑賞者性の弁証法
わたしの作品は冷蔵庫の明かりのようなもので、つまり人がそこで冷蔵庫のドアを開けるときだけ機能するわけです。(リアム・ギリック)
冒頭すぐクレア・ビショップを引用して*8エルウェスは、鑑賞者が、作品とその空間のなかでインタラクトするときの反応を主題に挙げます。すでに第6章で触れた精神分析的モデルや、心身二元論的なデカルトのモデルを避けて、本章では心理的なアプローチを採用します。これは第12章で紹介される認知科学的なアプローチにも結びつきます。あるいはリチャード・ドーキンス的なバイラル理論や、フェミニズム唯物論、アルチュセールなどに目配せしつつ、本章では映像インスタレーションの主体を、「歴史・社会政治的な状況にフレーミングされ、〔作品の〕経験に抵抗したり変化させられたりするような多様な傾向をもつ、物理的・心理的な属性がユニークなしかたで同時発生するものの例化」ととらえています。
マルコム・ル・グリスはインスタレーションにおいては映像の時間的展開は集中して観られることがなく、鑑賞者の関心は「コンセプトとアイデア」にばかり向けられると指摘します。こうした注意散漫の「不完全な鑑賞者(imperfect spectator)」が、テレビのような「気散じの受容(distracted reception)」*9とも結びついていることをエルウェスは述べ、ジークフリート・クラカウアーやギー・ドゥボールによる批判、またミシェル・ド・セルトーによる擁護を紹介します。ド・セルトーによれば、気散じの鑑賞者は、むしろポピュラー文化の目的をみずから書き換えるような積極的なユーザーであり、エルウェスは映像インスタレーションの可能性をそちらにベットしています。そのような鑑賞はエルウェスにおいて、イリュージョン以外のものを同時に認知するという「二重性」*10をもつのです。
ここまで論じてきたように、インスタレーションにある映画的要素をわたしたちが鑑賞するとき、イリュージョン的な奥まった空間のなかにある『別の』現実としてと同時に、動画を物質的な現象としても読む能力が動員される。わたしたちはこの、知ることの二つの形式を同時に維持して、その理解の編み上げられた状況から結論を引き出す。
ここまで触れたような「二重の意識」(アレン)「二重性」(ウォルハイム)やケイト・モンドリアンの「鑑賞者の二重性(spectorial doubleness)」、またロラン・バルトが映画について論じた「二重の魅惑(dual fascinations)」と類比したアイデアです。目と脳が騙されていると知って平静でいることで、この二重性は保たれます。ちなみにエルウェスは「幽霊」を「二重性を失った映像のよう」と述べています。
映像インスタレーションを観ながら、どこを通ったり座ったりできるかをわたしたちは判別しているのであり、このような空間の把握は、第3章で扱った彫刻の議論と結びついています。
構造主義的体制で批判されていた受動的な鑑賞者性にたいして、エルウェスはここでは鑑賞者の(ある程度の)自律を主張します。たしかにスクリーンへの没入からモラル・規範が守ってくれるというのは楽観的ですが、しかしわたしたちはいまやデフォルトで映画文化に社会化されており、没入は一時代的な逸脱であるどころか、むしろ人間は「スクリーン主体(screen subjects)」として、日常からインタラクションしています。キャロリー・シュニーマン《Snows》(1967)は、ベトナム戦争のイメージを用いながら、自身の身体にそうしたイメージが入り込むことを描き出しました。あるいは、テレビの影響で、警官が銃を構えるまでの時間が実際に短くなっている、という研究もエルウェスは紹介します。
もはや消費者も制作者も、主流映画・テレビ、さらにインターネットの経験の蓄積を経由しているのであり、鑑賞者はこの環境に参加するしかたを探求している、とエルウェスは主張します。
1960年代から1980年代には、芸術家の非標準的な主体性(ジェンダー、人種、年齢、文化、性的指向)などが正当に扱われました。同時に鑑賞者ももちろん複数的・異種性であり、もはや「白人中流階級異性愛男性」の鑑賞者という慣習は批判されていきます。リンダ・ウィリアムズらの実践や、メアリー・アン・ドーンの議論がその例です。むしろハリウッドの極端な表現にも、ステレオタイプから引き離される例があることをドーンは分析しています。
映像はむしろ、鑑賞者が安全な距離をもてるように不安や欲望を演じる「代理のプロセス(process of surrogacy)」の性格を強調されます。あるいは逆に、鑑賞者は作家の意図に反して映像を「解読」しうるという点も指摘されます。エルウェスはスティーヴ・マックイーン《Bear》(1993)の被写体である黒人の身体を例に、さまざまな意味がそこに投影される点を論じます。結局作品の解釈は、鑑賞者の見方や背景、また上映自体の文脈に大きく依存します。
同時にエルウェスは、ジャック・ランシエールの「解放された観客」や、レイモン・ベルールによる「動かない鑑賞者」の擁護といった、鑑賞者の反省や批判のポテンシャルの過大評価については、楽観主義だと注意を促しています。
鑑賞者はただ受動的でもなければ、十分に批判的でもない。エルウェスは、作品にたいする鑑賞者の「避けがたい共謀性(inevitable complicity)」(ミシェル・アーロン)を指摘します。作家がアルコール中毒者をスタジオに招いて飲酒させる様子を撮影したジリアン・ウェアリング《Drunk 》(2000)について、それを「中立的にそれを観ることの無責任さ」を鑑賞者はかわせるのか、とエルウェスは論じます。わいせつ・暴力・非倫理的な映像にたいしてこそ、鑑賞者性は不快なかたちで前面化させられるとアーロンは考えますが、しかしアーロンの挙げる例は十分ではなく、娯楽のなかの残酷さに、わたしたちはなおも捉えられています。
》(2000)について、それを「中立的にそれを観ることの無責任さ」を鑑賞者はかわせるのか、とエルウェスは論じます。わいせつ・暴力・非倫理的な映像にたいしてこそ、鑑賞者性は不快なかたちで前面化させられるとアーロンは考えますが、しかしアーロンの挙げる例は十分ではなく、娯楽のなかの残酷さに、わたしたちはなおも捉えられています。
鑑賞者の当惑はたしかに達せられた、しかし、唯一まっとうな倫理的態度には、目をそらすことも含むと私は論じたい。
エルウェスは《Drunk》について、アルコール中毒者のほうより、むしろ作家とのあいだに、鑑賞者は間人格的な呼応をもつとみなします。そのあいだの、共感的ならぬ「異感的(heteropathic)」な感情移入(empathy)を鑑賞者はもち、作家と被写体とのあいだの搾取的関係のあいまいさについて考えるようになります。ウェアリング自身は、同情しながら中毒者たちをスペクタクルに変容させたのだろうか?
映像を国家イデオロギー・資本主義の形式として批判していた1960年代・1970年代の実験映画・ビデオに比べ、映像インスタレーションは、鑑賞者を座席・沈黙から解放したとしばしば論じられました。しかしエリカ・バルソムは「動かないことに神秘化を、歩き回ることに批評をあてがって考える」のは馬鹿げていると一蹴し、むしろ移動は知覚経験にかかわるものだと考えます。
ギャラリー内で動き回る鑑賞者は、ひとつの映像の前にとどまったり、あるいは映像全体に付き合わずに立ち去ったりします。この意味で遊歩者的な「解放された」「気散じ」の鑑賞者がここではモデルに挙げられます。ギャラリーの空間は「気散じが可能だという安心を提供する」(ピーター・オズボーン)のです。マルチスクリーンや巨大・高解像度投影。小型化、インタラウティヴィティなどにも関わらず、ますます映像は一瞬で消費されるようになり、ネットストリーミングの隆盛は、インスタレーションの感覚を鈍らせているとさえエルウェスは指摘します。芸術家はそうした、ぶらつく非反省的な鑑賞者を引き止めなければならないが、映画館もインスタレーションもそうした注意深さを保証はできない。いっぽうでオズボーンは、むしろこの断片化による、没入と気散じとの反省のリズムこそ、芸術家にとって豊かな場所だと主張します。
ともあれそうした状況のなかでは、プロフェッショナルの音楽家・ダンサーとの協働や、シネマスコープの採用、壁や天井に投影した没入的な演出、ナム・ジュン・パイクのようなモニターの複数使用、商業映画の技術や豪奢さの流用、ギャラリー内映画館、動画の尺の切り詰め、単線的な物語、インタビュー形式などが採用されます。アルコール中毒者やトランスジェンダー、マイノリティ、犯罪者などの人生を扱ったドキュメンタリーすら、近代的なギャラリーのデザインにパッケージされます。
鑑賞者の関心を引きつけるため、クトゥルー・アタマンやアン=ソフィ・シデンは複数のモニターや投影を用いることで、テレビをザッピングするような効果を作ったり、あるいはゲイリー・ヒルらは鑑賞者自身を投影に巻き込んだりします。さらにライアン・トレカーティンやリジー・フィッチなど、ポップカルチャーのパロディを用いる作家もいます。リアリティ・ショーやSNSなど、「ネオリベラルのネットワークと流れ」(リサ・アカヴァル)に駆られた文化空間では、もはや主体の商品化に抵抗しようともその外部にいるとは主張できず、むしろそのモードを無意識に再生産してしまうことをエルウェスは指摘し、芸術家が鑑賞者の注目を引き止めるときに、そうした自己誇張の中に批判を埋め込んでいると論じます。
9 エキスパンデッド・シネマ
Borrowed Time from David Cotterrell , YouTube
, YouTube
Horror Film 1 from
Malcolm Le Grice , YouTube
, YouTube
以降の章は、ここまでの章よりも、より個々のトピックの実例を挙げるような構成になります。本章では、映像技術を利用した空間的表現(エキスパンデッド・シネマ)、次章ではサウンド、第11章ではテレビ・ビデオを扱います。
ジーン・ヤングブラッドが1970年に提唱した「エキスパンデッド・シネマ」は、テレビなどの隆盛した時代における間メディア的な実践を指します。ここまで挙がったようなヨーロッパの主要国だけでなく、ポーランドやスペイン、ドイツの作家、さらに日本の「具体」グループも実践者に挙げられます。
プロジェクターやスクリーン、フィルム、投影光線、また上映している時間といった、映画の「原初的な経験」(ダンカン・ホワイト)がモチーフ・主題になります。たとえば鑑賞者を映したプロジェクションが重ねられていくウィリアム・ラバン《2’45’’》(1973)が挙げられます。映画イメージがまずもっている「知覚の環境」「心理的なかかわり」に焦点を置くことで、鑑賞者の批評的な機能は刺激されます。それは素材の広範な利用を特徴とするインスタレーションより、さまざまな装置や制度に依存した古典映画や、「エキスパンデッド(拡張された)」といいつつ要素を切り詰めている点ではミニマリズムのほうが共通するところが多いともいえます。
以降は、フィルムストリップそのものを題材としたものでは、フィルムを黴びさせたヴェルナー・ネケス《Standing Film/Moving Film》(1968)や、海に漂流させたベン・リバーズ《Two Years at Sea 》(2011)、安い乳剤を40年かけて黄ばませたトニー・コンラッド《Yellow Movie
》(2011)、安い乳剤を40年かけて黄ばませたトニー・コンラッド《Yellow Movie 》(1973)が紹介されます。
》(1973)が紹介されます。
また「暗闇」というトピックでは、裸電球とプロジェクションとを対置させたロバート・ホイットマン《Prune Flat》(1965)、点滅させたル・グリース《Castle One 》(1966)、口内から撮った映像を暗闇で上映したスミス&スチュアート《In Camera
》(1966)、口内から撮った映像を暗闇で上映したスミス&スチュアート《In Camera 》(1999)などが挙げられます。
》(1999)などが挙げられます。
「光」については、第3章でも紹介したアンソニー・マッコール《Line Describing a Cone 》(1973)《Long Film for Four Projectors
》(1973)《Long Film for Four Projectors 》(1974)《Between You and I
》(1974)《Between You and I 》(2006)、第5章で触れたトニー・アウスラー《The Influence Machine》(2000)、また部屋に満たした煙に、初期映画を思わせる汽車の映像を投影したデヴィッド・コテレル《Borrowed Time
》(2006)、第5章で触れたトニー・アウスラー《The Influence Machine》(2000)、また部屋に満たした煙に、初期映画を思わせる汽車の映像を投影したデヴィッド・コテレル《Borrowed Time 》(1997/2002)などが紹介されます。
》(1997/2002)などが紹介されます。
さらに、投影光線をあえて遮るような作品として、第4章で触れたイーザリーや、裸の作家がプロジェクションに立ちはだかるル・グリス《Horror Film 1》(1971)、被写体実物にそれを映したスライドを投影したティム・ヘッド、シャボン玉を吹いたシュニーマン《Ghost Rev》(1965)、苦悶の姿勢をとったラグドールに表情を投影したアウスラー《System for Dramatic Feedback 》(1994)が紹介されます。
》(1994)が紹介されます。
光や時間そのものの提示へとさらに肉薄する「パラシネマ」概念として、カールステン・ヘラーやエヴァ・コッチ、リューク・ジェラムらの作品が紹介されます。点滅する光や色のついた光というトピックでは、クリス・ウインライトやタシタ・ディーン、スーザン・トラングマー、グラハム・エラルド、クリス・メイ=アンドリューズ、スティーヴ・マックイーン、また再びマッコールや、マーティン・クリード、ブライアン・イーノ、アンジェラ・ブロック、草間彌生、ジェームズ・タレル、アニッシュ・カプーア、オラファー・エリアソン、デレク・ジャーマンが紹介されます。
あるいはスクリーンについて、片面が鏡になったスクリーンがゆっくり回転しつづけるビル・ヴィオラ《Slowly Turning Narrative 》(1992)、影絵を用いた諸作品や、スクリーンを両面に女性の正面と背面を投影したマイケル・スノウ《Two Sides of Every Story》(1974)、そして最後に、作家が胴の前で掲げた小さな「映画館」の箱の中へと通行人に手を入れさえ、裸の乳房に触らせるというVALIE EXPORT《TOUCH CINEMA
》(1992)、影絵を用いた諸作品や、スクリーンを両面に女性の正面と背面を投影したマイケル・スノウ《Two Sides of Every Story》(1974)、そして最後に、作家が胴の前で掲げた小さな「映画館」の箱の中へと通行人に手を入れさえ、裸の乳房に触らせるというVALIE EXPORT《TOUCH CINEMA 》(1968-1971)が紹介されます。《TOUCH CINEMA》は、触っている鑑賞者を作家が見つめ返す点で、男性的な視線の支配を転覆させ、また触覚性と視覚性をも反転させている点で、第6章で紹介したようなフェミニスティックな「視線の去勢」に連なる作品でありながら、スクリーンとイメージが合致する「ゼロ度の」(ホワイト)シネマでもあると論じられます。
》(1968-1971)が紹介されます。《TOUCH CINEMA》は、触っている鑑賞者を作家が見つめ返す点で、男性的な視線の支配を転覆させ、また触覚性と視覚性をも反転させている点で、第6章で紹介したようなフェミニスティックな「視線の去勢」に連なる作品でありながら、スクリーンとイメージが合致する「ゼロ度の」(ホワイト)シネマでもあると論じられます。
10 音
2014 ‘Bicycle Tyre Track’ at Tate Britain from vicky smith on Vimeo物語的な一貫性への抵抗としては、まず画と音とのシンクロの切断が試みられます。ブルース・ナウマン《Lip Synch 》(1969)はその好例です。あるいは、自身の頭蓋骨を使って、カセットテープの音を展示室に反響させたローリー・アンダーソン《Small Handphone Table》など、音や声の所属先をずらす・なくすようなアプローチが見られます。
》(1969)はその好例です。あるいは、自身の頭蓋骨を使って、カセットテープの音を展示室に反響させたローリー・アンダーソン《Small Handphone Table》など、音や声の所属先をずらす・なくすようなアプローチが見られます。
あるいは録音や増幅を駆使した作品に、ビル・フォンタナやビル・ヴィオラの作品が紹介されます。いっぽう沈黙をあえて用いたインスタレーションとして、マッコールや再びヴィオラ、マックイーン、ダニーノら、特に防音材を用いたナウマン《Acoustic Wall》(1969)が紹介されます。
より関心ぶかいトピックは「声」です。ナウマン《Lipsynch》もそうですが、声と画のシンクロの破壊は、映画やテレビに慣習的な、イメージをエスコートするような権威的・男性的・証言的・知的な声を脱臼させる効果があります。ロスラーやローズ、ハトゥムらが用いる声は、慣習的な語りを避けて、歌や泣き声、笑い声を用いる点で、リュス・イリガライのいう、女性が「世間の抑圧から逃れる最初の形式」だとエルウェスは指摘します。また人間の声の民族的多様さを扱う作品として、トリン・ミンハやスーザン・ヒラー、ウィリアム・ファロングなどが紹介されます。
さらに「腹話術」といった節では、声を別の口に寄生させる作品として、母と息子兄弟の喧嘩している映像の、それぞれの声を入れ替えたジリアン・ウェアリング《2 into 1》(1997)が紹介されます。また「バイリンガル」の節で、フランス語と英語をスムーズに使い分けてアイデンティティの分裂を語ったロバート・モリン《Yes, Sir! Madame… 》(1994)が紹介されます。
》(1994)が紹介されます。
さらに声以外にも、土地の電磁場を捉えたり、映画史からアプロプリエーションしたり、ファウンドのカセットを用いたり、特にダグラス・ゴードンの、『聖処女』と『エクソシスト』という2つの対照的な映画をスクリーンの両面に同時上映することで、BGMの不協和な衝突を作り出した《Between Darkness and Light 》(1997)が紹介されます*11。またアナログフィルムにおいてはサウンドもイメージと同様物理的に記録されることに注目した、自転車で轢いたフィルムを上映するヴィッキー・スミス《Bicycle Tyre Track》(2012-2014)も紹介されます。
》(1997)が紹介されます*11。またアナログフィルムにおいてはサウンドもイメージと同様物理的に記録されることに注目した、自転車で轢いたフィルムを上映するヴィッキー・スミス《Bicycle Tyre Track》(2012-2014)も紹介されます。
ところで、音は映像インスタレーションにおいて鑑賞者の注意を引き止める効果があります。エルウェスは、何の意味もないがただ音がないと寂しかろうという理由でつけられている音響を「鳴るローション(sonic lubricant)」と呼び、もったいぶった電子ドローン音、意味のないリズム、震えた声や不吉なクリック音、水の流れる音や雷の音……などを挙げ、プロモーションでそういったものは「サウンド・デザイン」と呼ばれる、と皮肉を込めて指摘しています。それは主流映画でも観られる技法です。
11 ビデオ・インスタレーション
Gillian Wearing – Family Stories / Teaservideo from SMK , YouTube
, YouTube
本章は、テレビおよびビデオが扱われます。
1960年代には家庭用テレビは、イギリスでは平均して1日11時間ほど観られるほど膾炙しており、日用品などを用いたインスタレーションの一部を成していました。第8章でも触れたような「気散じの鑑賞者」もこのような状況から評論されたものです。生放送のかりそめの「共在」の感覚は、公共放送の真面目さから、楽しげなトーク番組の登場によって強まり、ペギー・ゲイルはテレビ自体に「擬人主義(anthropomorphism)」*12を見出しています。
フランスの彫刻家セザールやフルクサスのヴォルフ・フォステルなどテレビを嫌悪した芸術家もありました。主流映画を構造映画作家が批判したように、大衆娯楽の代表たるテレビは芸術家から敵対心をもたれ、実際マイノリティにたいするステレオタイプなイメージの再生産を批判されました。同時に、生活のなかへのテレビ的侵入は、初期のビデオ・インスタレーション作家にとってのモチーフでもあり、ダラ・バーンバウム《Technology/Transformation: Wonder Woman 》(1978-1979)をはじめ、テレビからのアプロプリエーションを用いた「スクラッチビデオ」運動がVJ文化から起こり、MV産業へと改めて流用されました。テレビは制度的・国家的保守性を批判されながらも、バーンバウムがその政治的な「再発明」をもくろむように、そのイメージは救済の対象でもありました。
》(1978-1979)をはじめ、テレビからのアプロプリエーションを用いた「スクラッチビデオ」運動がVJ文化から起こり、MV産業へと改めて流用されました。テレビは制度的・国家的保守性を批判されながらも、バーンバウムがその政治的な「再発明」をもくろむように、そのイメージは救済の対象でもありました。
ビデオが導入されると、その中継・フィードバックは、一種の「鏡」のような効果をもつようになりました。ヴィト・アコンチやピアリック・ソランらは鏡では映らない身体部位を映し、ハワーデナ・ピンデル《Free White and 21 》(1980)は、黒人である自らの肌につけられた傷をモチーフにしました。また鑑賞者自身を撮影・投影したものでは、ナウマンやホール、ピーター・キャンパス、とくにロジャー・バーナード《Corridor》(1974)が取り上げられます。こうした中景によって、鑑賞者の自己の映像にたいするナルシシックな態度は和らげられ、そこでは鑑賞者は自身を「他者」として経験する、とエルウェスは注釈します。
》(1980)は、黒人である自らの肌につけられた傷をモチーフにしました。また鑑賞者自身を撮影・投影したものでは、ナウマンやホール、ピーター・キャンパス、とくにロジャー・バーナード《Corridor》(1974)が取り上げられます。こうした中景によって、鑑賞者の自己の映像にたいするナルシシックな態度は和らげられ、そこでは鑑賞者は自身を「他者」として経験する、とエルウェスは注釈します。
そうした例では、ダン・グレアム《Performer/Mirror/Audience 》(1975)は特筆すべき例です。鏡の前、観衆に囲まれた作家が、自分の鏡像に向かって、その特徴を読み上げていきます。ふいに作家は、観衆のほうからひとりを選び出し、その特徴を鏡越しに挙げていきます。ビデオ中継を利用したものではありませんが、グレアムの他の作品と並べれば、自他の認識にもとづく一連の関心が、同時代的なテレコミュニケーションの状況にもとづくと推察できる作品です。
》(1975)は特筆すべき例です。鏡の前、観衆に囲まれた作家が、自分の鏡像に向かって、その特徴を読み上げていきます。ふいに作家は、観衆のほうからひとりを選び出し、その特徴を鏡越しに挙げていきます。ビデオ中継を利用したものではありませんが、グレアムの他の作品と並べれば、自他の認識にもとづく一連の関心が、同時代的なテレコミュニケーションの状況にもとづくと推察できる作品です。
さらに録音やその編集が可能になると、観ている時間と、インスタレーションなどの作品の中で俎上に上げられる時間とのギャップが問題になります。事前に記録した自身の映像と、ライブの作家とが口論するケヴィン・アサートンのパフォーマンス《In Two Minds 》(1978)をエルウェスは取り上げてから、2006年に行われたその再演ヴァージョンも紹介します。そこではアサートンは30年前の自分の映像と口論しており、作家の老化と、また映像メディアの進化などが重ねられて主題にあがります。
》(1978)をエルウェスは取り上げてから、2006年に行われたその再演ヴァージョンも紹介します。そこではアサートンは30年前の自分の映像と口論しており、作家の老化と、また映像メディアの進化などが重ねられて主題にあがります。
また、ギャラリーにビデオ技術が持ち込まれることで、芸術家のスタジオとギャラリー空間とのあいだの違いのなし崩しが起こったことをエルウェスは指摘します。ギャラリーが制作上となり、作品が鑑賞者・テクノロジー・そして芸術家との三者の出会いにもとづくというのは、第4章で指摘された、芸術家の(うぬぼれた)現前とつながるトピックです。たとえばギャラリーにリビングセットを持ち込んで、そこで飲み会を番組のように撮影したアレクシス・ハジンス&ラクシュミ・ルトラ《Reverse Cut 》(2010)は、芸術家が自分で番組・チャンネルをもつことや、エルウェスの本書では言及されていませんが、刊行時点ですでに登場し始めていたYouTuberにも結びつく作品でしょう。
》(2010)は、芸術家が自分で番組・チャンネルをもつことや、エルウェスの本書では言及されていませんが、刊行時点ですでに登場し始めていたYouTuberにも結びつく作品でしょう。
あるいはこの時代には、地上波テレビの放送枠を実際に用いた作品もいくつかありました。2チャンネルで放送され、家庭ごとに2台のテレビを持ち出すことでインスタレーションを作ることのできたスタン・ヴァンダビーク《Violence Sonata》(1970)や、炎を映すことでテレビを暖炉に変えたジャン・ディベッツ《TV as Fireplace 》(1969)が挙げられます。
》(1969)が挙げられます。
また1980年代には、シミュラークルと大量生産の時代において、テレビを用いた芸術表現は衰退期に入ります。パイク《Tricolor Video》(1982)《Family of Robot; Mother and Father》(1986)やヒル《Inasmuch as It Is Always Already Taking Rite II 》(1989)、ホール《1001 TV sets [End Piece]》(1972-2012)では、ときに300や1000を超えるテレビが並べられ・積載されました。
》(1989)、ホール《1001 TV sets [End Piece]》(1972-2012)では、ときに300や1000を超えるテレビが並べられ・積載されました。
テレビ文化がデジタル放送に移行し、さらにオンライン放送へと道を譲っている時期の作品として、ウェアリング《Family History 》(2006)が紹介されます。かつてのドキュメンタリー番組で紹介された労働階級の家族の娘を題材にした作品で、かつて居間のブラウン管テレビでその番組を幼い頃の作家自身が観ていたようすを模した部屋と、現在40代になった当時の娘がインタビューに答えて当時のドキュメンタリー放送の反響について述懐しているようすが並置された作品です。
》(2006)が紹介されます。かつてのドキュメンタリー番組で紹介された労働階級の家族の娘を題材にした作品で、かつて居間のブラウン管テレビでその番組を幼い頃の作家自身が観ていたようすを模した部屋と、現在40代になった当時の娘がインタビューに答えて当時のドキュメンタリー放送の反響について述懐しているようすが並置された作品です。
エルウェスはさらに、1990年代以降に登場した作家におけるテレビの取り扱いを概観しつつ、今日のテレビにもある抑圧に対する批評性を宙吊りにしていては芸術家としては手落ちである、と、「批評的なものの再配分(redistribution of the critical)」(アカヴァル)という語を引き合いに出しながら釘を指します。
12 おわりに
本書はひとつに収斂するような議論はなく、実質的には第8章が理論的な到達点で、第9~11章は映像にまつわるさまざまな要素における具体的な実例を取り上げた、と捉えてよいでしょう。最終章にあたる本章は、比較的雑多なトピックが取り扱われますが、主な内容は3つあるといえます。
ひとつめは、アナログに対するデジタル技術の登場について。エルウェスは、アナログにあったような(そして映画の実際らしさ(actuality)を支えていたような)「インデックス」(C.S.パース)の性格がデジタル映像においては薄れていることを指摘し、「ポストメディウム的状況」(ロザリンド・クラウス)に言及しながら、デジタルの領域に拡散したアナログの技術やその「再メディア化(remediation)」に触れつつ、またAppleやAdobeのコーデックによってデジタルの視聴覚環境が規定されていることを指摘します。またコンピュータやビデオゲームへのハッキングにも触れ、コーリー・アーカンジェル《Super Mairo Clouds 》(2002)を紹介します。
》(2002)を紹介します。
ふたつめは、認知科学を用いた、映像の鑑賞者性の研究の可能性について。デイヴィッド・ボードウェルやユーリ・ハソンらの、アイトラッキングやfMRIなどを用いた研究をエルウェスは紹介し、没入の度合いの測定や、中心と周辺に対する「二重の視覚」概念の検討などの成果を引用します。特に後者は、第8章でも触れた「気散じ」の議論と結びつくポテンシャルがあるでしょう。いっぽう同時にエルウェスは、そうした研究が口頭の証言にもとづいていること、鑑賞者どうしの差異について検討できていないこと、映画全体の印象についての測定ができていないこと、さらに研究対象が主流映画・テレビに集中するために、その「注意経済」ばかりに貢献する技術の再生産に加担しているという懸念を指摘します。たとえばイギリスのテレビドラマ『SHERLOCK』(2010-2017)の映像を使った実験で、そのシーンの内容に関する鑑賞者の性別・ジェンダーによる反応の違いを考慮できていないのではないか、と指摘します。
みっつめは、芸術家自身の役割です。ポスト構造主義的観点における作者の位置づけや、そのステートメントへの不信、また理論家・著述家の性格をもつ作家、「参加者」たる鑑賞者のエージェンシー、自身のアーカイブとの付き合いについて雑多に触れます。取り上げておくべきは、映像インスタレーションにおいて、スクリーンを鑑賞者に見せつけることの「強制的な(coercive)」(ケイト・モンドロッチ)性格、「設えられた構造による〔鑑賞者に対する〕いじめ」(モンドロッチ)があるという指摘です。映画が鑑賞者にたいしてショックや驚愕、不安を与えるというロバート・スミッソンやラースロー・モホリ=ナジの指摘を紹介し、ギャラリーが一種の「倫理的避妊具(ethical prophylactic)」(アマンダ・ビーチ)としてあらゆることの発生を認めてしまう側面。芸術家がそこで「意味の親としての中心性」を保持して振る舞っていることをエルウェスは批判しつつ、芸術家は鑑賞者にある観点を押し付けるという点で、不可避のナルシシズムや驕りをもつと述べます。
(まとめ)
このように、エルウェスの本書は、各章に分かれたトピックが、構造映画とエキスパンデッド・シネマを中心に、インスタレーションにおける鑑賞の二重性を賦活させる、とくに主流文化の表象へのカウンター的側面をもちいた作品を紹介する構成となっています。とはいえ単純な二項対立の構図になっていない点が美点です。
批判的な契機を呼び込む「二重性」が、本書ではさまざまな局面で取り上げられており、ビショップやレーベンティッシュの議論にも重なるところがあります。いっぽうでエルウェスは具体的な左派の形式的方法論を紹介したり、「気散じ」などの論点を加えるなど、(全体が強く組織化されていないことで)前二者よりも広範なトピックを扱っているといえます。