キルシ・ペルトマキの『状況の美学:マイケル・アッシャーの仕事(Situation Aesthetics: The Work of Michael Asher)』(2010)1の各章をまとめました。
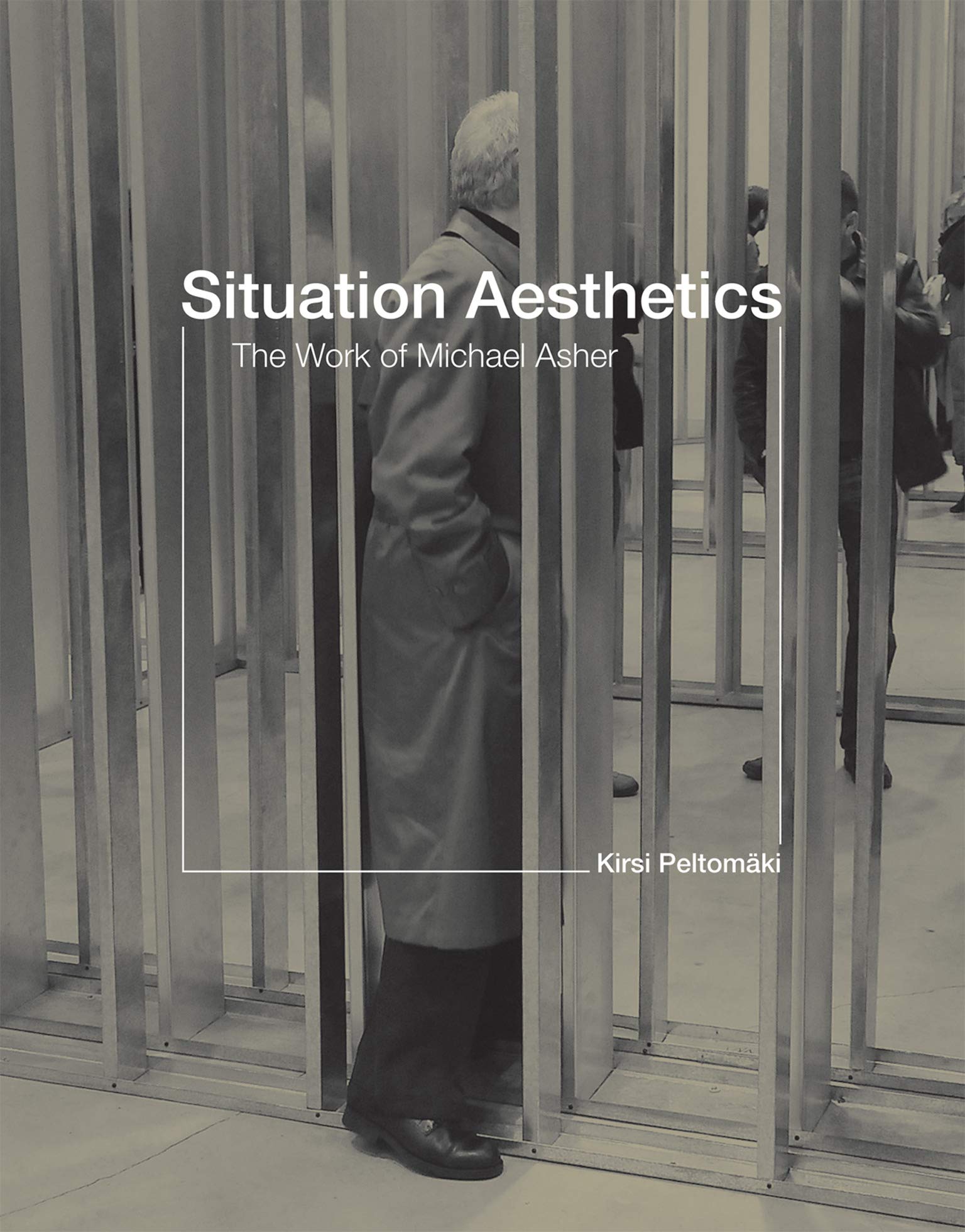
書影
この記事は、インスタレーションに関する文献の要約を公開していくシリーズです。すでにクレア・ビショップ『インスタレーション・アート:ある批評史』、ユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーション・アートの美学』、キャサリン・エルウェス『インスタレーションと映像』、ジュリー・H・ライス『周縁から中心へ:インスタレーション・アートの空間』を紹介しました。
今回はやや趣向を変えて、「インスタレーション」を冠していない書籍です。1960年代末からアメリカで活躍した作家マイケル・アッシャー(Michael Asher, 1943-2012)のモノグラフです。コンセプチュアル・アートや制度批判の文脈にある作家ですが、題の「状況(Situation)」の通り2、その作品は一貫して、美術館やギャラリーならではの「状況」を設定するものです。その手法は必ずしも物理的なものではなく、特に後期には、法的契約を結ぶことで、その場を美的に変容させる特異なアプローチをとってきました。
アッシャーの作品は、おおまかには身体経験や制度批評という括りで触れられます。すでに紹介した書籍のなかでも、ライス『周縁から中心へ』やビショップ『ある批評史』で作品が触れられたり3、他にも名前の言及があります。
身体経験という点ではロバート・アーウィンやブルース・ナウマン、制度批評という点ではマルセル・ブロータースやハンス・ハーケといった作家と並べて扱われやすいアッシャーですが、本書でペルトマキが一貫して主張するように、アッシャーにおいてはその両者が密接に連携しています。
インスタレーションという「インストール(設置)」の芸術のさまざまな可能性のなかでも、ひとつの極北といえると思います。
しかし同時に、第2章で取り上げられるアッシャー作品の特異な「参加」の側面は、参加型アートがしばしば帯びてしまう共犯的形式にたいして鋭い批判を向ける性格があります。その点でも、アッシャーの活動全体とともにそのアプローチを確認するのは、インスタレーションの社会的転回を考えるうえで非常に重要だと思います。
本書が対象とする主な範囲は、アッシャーの1960年代から1990年代までの作品です。全体はイントロダクションと4章から構成されますが、時期ではなく手法で分かれています。そのため、特に多作な1970年代の作品は、各章に散らばって紹介されます。
各章は順に、身体の知覚にフォーカスした「鑑賞経験(Viewing Experience)」、展示関係者の参加を扱う「契約された参加(Contracted Participations)」、さらに作家自身をその素材とする「作家の名において(In the Name of the Artist)」、美術館や展示の制度自体を扱う「制度的支持体=サポート(Institutional Support)」に分かれています。詳細は以降で取り上げます。
イントロダクション
アッシャーは1970年代中盤までは、ミニマリズムやポスト・ミニマルの流れを汲む、展示空間への知覚や身体感覚に重きを置いた作品群を制作していました。1974年ごろから美術館やギャラリーの空間そのものを素材にしはじめ、同年代後半には、ベンジャミン・ブクローやクレイグ・オーウェンスなどの批評家によって、ブロータースやハーケ、ダニエル・ビュレンなどと同じ「制度批評」の潮流に置かれます。
アッシャーのインスタレーションについてペルトマキは、鑑賞者の「経験」や、感情的・心理的反応が重要になると強調します4。アッシャーの作品は、美術館やギャラリーといった美術制度・機関・イデオロギーについての鑑賞者の識見――ギャラリストとはどのような人か、カタログはどのようなものか、展覧会とはどのようなものか――をある意味「ハック」することで、そうした制度のなかの個人としての鑑賞者の感情を揺さぶります。
アッシャーのそうしたインスタレーションは、流通可能な自律したオブジェクトを作らない点や、参加性がある点が、同時代のコンセプチュアル・アートやエンヴァイロンメントの動向と共通しています。いっぽうブロータースやハーケ、ビュレンと区別される特徴として、アッシャーが直に、展示室や美術館といった空間やその実在そのものを、ミニマリズム的な手つきで扱う点が挙げられるでしょう。虚構の美術館の表象をつくりあげるブロータースや、縞模様という「見るべき」ポイントを作るビュレンにたいして、「贅沢な禁欲主義」(ブクロー)「物質的な無口さ」(ペルトマキ)と形容されるアッシャーの微細な、ときにほとんど作品と認識されないような手つきこそ、アッシャーの特異なアプローチといえます。
本書のタイトル「状況」とは、そのように特異に経験されるべき状態に置かれた(situated)制度的空間を指します。鑑賞者もそうした状況に置かれて(situated)いるのです。アッシャーも自身の作品の「状況性の美学(situational aesthetics)」を以下のように要約しています。
この美学的なシステムは、制度の枠組みのなかで起こる、すでに決まりきった諸要素を並べる。その枠組みは、当の制度という文脈そのものから引き出されるものであり、公共の人々にも明確に認識されている。(アッシャー)
ちなみにそうした性格のため、アッシャーの作品は再制作・収蔵されることが極端に少なく、それゆえ回顧展も開かれていません(この記事も公的な記録へのリンクが多くありません)。実際、過去の作品の再展示を要求してきたキュレーターに、「当時の文脈が再現できなければ再展示する意義はないし、その再現自体無意味だろう」という旨の返答をしています。
重要作家に挙げられるにもかかわらず関心や説明がいまだ充分でないのは、このように現在実見できる作品が皆無であるためだとペルトマキは指摘しています。アッシャーの作品の全貌は、1979年に作品図面を自著解説をまとめた図録が出ていますが、それ以降の作品については、本書はもっともよくまとめられているものの一冊でしょう。
第1章 鑑賞経験(Viewing Experiences)
本章はアッシャーの比較的初期の作品が扱われます。特徴としては、1970年代後半以降の作品にくらべて、空間の物理的な現象を知覚・感覚する側面が強く出ています。その点では、同時期に展開したミニマリズムや、アッシャーが活躍した西海岸でその文脈を継承したライト・アンド・スペース運動との相違は確認しておくべきでしょう。
モリスやフリードの議論を紹介しつつ、ペルトマキは、アッシャー作品と異なりミニマリズムの鑑賞者は理想化・抽象化されているとみなします。その現象学的な直接性(=リテラルネス)をコンセプトとするにせよ批判するにせよ、鑑賞者ごと・状況ごとに特異な社会的条件づけを無視したそのアプローチが「感覚的でよく準備された自律的な内省と自覚の問題を残しておく」点で「ただモダニズムの形而上学を取り代えただけ」(トーマス・クロウ)だ、という批判をペルトマキは引用します。
ミニマリズム彫刻的オブジェクトよりも、環境的なインスタレーションにより接近した点では、ライト・アンド・スペースの実験性はアッシャーの関心を引くものではありました。
ギャラリーの展示室に新たな内壁を設けて三角形の空間にし、さらに入り口を取り外して外光と外気を取り込んだポモナ・カレッジ(1970)や、空間を真っ二つに塗り分けたドクメンタ5(1972)をはじめ、壁に溝を掘ったり、天井を床の色で塗ったり、内装の表面を剥がしたりする1973年のインスタレーション群は、たしかにアーウィンやジェームズ・タレルの作品を思わせるところがなくもありません。しかし、ライト・アンド・スペースの作品では、ギャラリーや美術館の空間が、光や色という知覚的効果の背景になるのにたいして、上に記したようなアッシャーの作品では、知覚できるものはどれも、展示室という、ニュートラルな背景では決してない空間が、その経験の先に結びついています。
展示室を覆い隠さず、むしろリテラルに見せるという点が、アッシャーのインスタレーションの社会的・知覚的な方針、「禁欲主義」と呼ばれるような特徴を呈します。
個展(La Jolla Museum)や「Spaces 」展(MoMA)の作品では吸音装置、「The Appearing / Disappearing Image / Object」(ニューポート・ハーバー美術館)「Anti-Illusion:Procedures/Materials」(ホイットニー美術館)では送風装置が用いられます(いずれも1969)。光学的・視覚的要素を排したそれらは、ポスト・ミニマルの文脈で受容されていました。
」展(MoMA)の作品では吸音装置、「The Appearing / Disappearing Image / Object」(ニューポート・ハーバー美術館)「Anti-Illusion:Procedures/Materials」(ホイットニー美術館)では送風装置が用いられます(いずれも1969)。光学的・視覚的要素を排したそれらは、ポスト・ミニマルの文脈で受容されていました。
室内での鑑賞者の移動に密接にかかわるこうした感覚的側面は、「親密(intimate)」「優しい抑圧」という形容から、「居心地悪い(embarrassing, uncomfortable)」という情動的反応を引き出します。
そうした特徴が、展示場所そのものの特徴を反映するようになったのは、オルタナティブスペース「Clocktower」での作品(1976)が契機といえます。扉や窓をすべて取り去ることで強調された空間の「孔」は、送風機の人工的な壁や吸音機による無音とは裏腹に、ビル最上階の展示室に、窓外の音や空気、ときには雨風を招き入れます。似たような物理的環境をもちいながら、ホワイトキューブでは〈ない〉という特徴が強調されたことで、感覚的なものと社会・制度的なものとを結びつけるアッシャー特有の関心がわかりやすく現われます。
ペルトマキは同年の、ゴードン・マッタ=クラークの、ギャラリーの窓をすべて撃ち抜いた作品《Window Blowout 》(1976)とアッシャーのインスタレーションとを比較します。とはいえ、作品自体を公共的なものに「する」ことを重視するマッタ=クラークのような活動とは異なり、アッシャーはむしろ制度の空間が鑑賞者を取り囲み、感覚されることに重点を置きます。
》(1976)とアッシャーのインスタレーションとを比較します。とはいえ、作品自体を公共的なものに「する」ことを重視するマッタ=クラークのような活動とは異なり、アッシャーはむしろ制度の空間が鑑賞者を取り囲み、感覚されることに重点を置きます。
経験の、感覚的で情動的なモードは、このような探求となおも分かちがたく結びついている。〔…〕1970年代をつうじてアッシャーの作品は、美術館や、わたしたちが共有している社会の領域のなかでふさわしいとされる行いの形式について、すでに『知っていた』ようなことを鑑賞者に問いかける。それが、反省した鑑賞経験を導くのだ。(ペルトマキ)
1979年の「73rd American Exhibition 」展(シカゴ美術館)の作品は比較的有名です。建物のファサード高所に据え付けられていたジョージ・ワシントン像を館内の「18世紀美術」展示室に移動させた作品は、わかりやすく美術館制度や権力的表象をモチーフにしている点で、制度批判やモニュメント批判の文脈で引かれることの多い作品です5。
」展(シカゴ美術館)の作品は比較的有名です。建物のファサード高所に据え付けられていたジョージ・ワシントン像を館内の「18世紀美術」展示室に移動させた作品は、わかりやすく美術館制度や権力的表象をモチーフにしている点で、制度批判やモニュメント批判の文脈で引かれることの多い作品です5。
また1990年代には、展示室の設備器具の特許番号を壁に刷ったり (1990, ルネサンス・ソサエティ)、美術館併設の図書室の「精神分析」コーナーの書籍に挟まっていた紙片を集めて展示したり(1991, ポンピドゥー・センター)、美術館のなかにありながら「展示」されない情報を俎上に載せるようなインスタレーションを行ないます。
(1990, ルネサンス・ソサエティ)、美術館併設の図書室の「精神分析」コーナーの書籍に挟まっていた紙片を集めて展示したり(1991, ポンピドゥー・センター)、美術館のなかにありながら「展示」されない情報を俎上に載せるようなインスタレーションを行ないます。
またスチュアート・コレクションの委託を承けてカリフォルニア大学のキャンパス内に常設された作品は、芝生にさりげなく設けられた水飲み場です 。
。
Stuart Collection at UCSD: Michael Asher from University of California Television , YouTube
, YouTube
一見作品のようにさえ見えないそれは、かつてこのキャンパスが軍事訓練場だったことを示すモニュメントを指し示すような位置にあることで、その展示場所がそのような場所になった経緯・歴史をモチーフとします。ペルトマキはこの「水飲み場(drinking fountain)」について、マルセル・デュシャン《泉(Fountain)》への参照を含みつつ、噴水という古典的モニュメントの形式を、実用性という点で転倒していることを指摘します。
音を聞く、風を感じる……だけでなく、水を飲む、本を読む、器具を使う、像を見遣る――展示室の外で行われる日常的な行為が、美術や表象の営みを支えている制度やその物質的実装と不可分であり、その行為をつうじてたしかに感じ取られ、反省され、心理的・感情的な反応を引き起こすようなアプローチを、アッシャーのインスタレーションはもっています。
第2章 契約された参加(Contracted Participation)
冒頭で述べたように、1950・1960年代の「エンヴァイロンメント」やフルクサス、ハプニング以来、インスタレーションという形式の中心には「参加」の主題が鎮座していました6。「参加」は、日常との融合、鑑賞者の能動化という、反資本主義・反体制という左派的なモードを背景に成立したモードですが、しかし同時に、逆説的にむしろ参加者が「受動的」な立場にも置かれてしまうという皮肉なジレンマを抱えています。
このような〔ビショップが取り上げる、鑑賞者にかなりの度合いでコミットを求めるような〕状況的な作品は、しばしば、そのような参加要求(request)を、自発的なアクティヴィティをしましょうという勧誘(invitation)として文脈づけている。表向きそれは、鑑賞者の作品にたいする『受動的な』関わりのモードを、より能動的なものへと広げよう、という目的をもっている。この図式でみると、鑑賞者が何をするかがしっかりと(heavily)事前に決められているときには特に、芸術作品に参加することは、労働の形式をとるのだ。そこでは鑑賞者は、具体的な成果(material outcome)のために、いくつかの明示されたアクティヴィティを成すよう呼びつけられている。(ペルトマキ)
このような「労働」の側面を、アッシャーの「参加型」作品はむしろ積極的に問題とします。いわばコンセプトのために鑑賞者を「こき使う」作品にたいして、アッシャーが対置するのは、むしろ近代の労働にとって根本的な「契約」の概念です。
アッシャーの参加型作品に「参加」するのは、ギャラリーのディレクターや美術館のスタッフなど、制度・権力の中にいる人々です。アッシャーはそのような人々と「契約」することで作品に参加させます。第1章では、鑑賞者にとって日常的な感覚・行為が素材となりましたが、ここでは美術の「インサイダー」にとっての日常である労働が主題になります。
したがって、アッシャー作品におけるプロフェッショナルの参加は、ふだん美術館に来るような人を、異なる鑑賞の状況に置いて『未知の』社会・経験の領域へ飛び出させる、というようなものではない。アッシャー作品の参加者たち〔契約した人々〕は、しばしばプロジェクトの実行に先立って、しっかりと共犯へと徴用(conscript)されている。前もって契約された取り決めは、参加者をアッシャーの芸術がもつ課題のなかに縛り付けるようなものだ。J.L.オースティンが述べたように、充分な信用と、適切な制度的状況(institutional circumstances)のもとにあれば、契約は具体的な結果をもたらす。プロフェッショナルとして『熟知した』、もしくは『公認の』義務を行なうことに関わる場合は特にそうだろう。(ペルトマキ)
もちろんそこで行われる業務は通常通りのものではありません。しかしアッシャーは、「通常の業務」がなにかを示すことはしません。アッシャーの契約で作り出した状況のなかで、参加者がプロフェッショナル個人としてふるまうようになるのです。
たとえばクレア・コプリー・ギャラリーでは、展示室とオフィスとのあいだの壁を除去するインスタレーションを発表しています(1974)。丁寧にも除去跡を再仕上げして、目で見てもわからないようにしています。
また同年ノヴァ・スコティア美術デザイン大学の教室棟のロビーに設けられたギャラリーでは、日光を差し入れ(室内照明を消灯し、日よけを取り除いた)、また警備員の常駐を一時的になくしています。来客や学生、さらにはスタッフがそこを通るときの息苦しさを取り除いている、とペルトマキは指摘しています。
さらに2年後では、都市部と閑静な地域とにある2つのギャラリーの業務を交換することで、それぞれの地理的、また経済的な立ち位置を前面に出しています。さらにはそうした違いは、取り扱い作家にも現われていることを、その時期の両ギャラリーで開かれた展覧会の作家を挙げてペルトマキは指摘します。
ギャラリーを空っぽにしたイヴ・クラインや、ギャラリーを封鎖したロバート・バリーと異なり、アッシャーのこの種のインスタレーションは、ギャラリーが運営しつづけることで、作家による介入の印はむしろ後景に退きます。小道具や台本、スケジュールもなく、テーマや結論、ガイドも与えられない、ただ壁や警備員の除去という状況だけで、鑑賞者(や参加するスタッフ)は、ギャラリー制度の構造的条件に直面します。丸出しのオフィスのギャラリストと顔を合わせる心理的な負荷が、そのような構造・文脈のしるしとなります。
このようなアッシャー作品について、当のギャラリストが「混乱もありながら、個人的な啓示でもあった」と述べるいっぽうで、批評家が「プライバシーを奪い取ってインタラクションを強制している」とその抑圧的な側面を指摘していることをペルトマキは紹介し、アッシャー作品における受容が、個人個人によって大きく異なることを指摘します7。
このような点で、アッシャーのインスタレーションは、現象学的で環境(エンヴァイロンメント)的なものというより、社会的で状況的なものといえます8。アッシャーの展示期間が過ぎても、その効果、つまり日常の業務・役割のアイデンティティが二重化した9影響は残ります。
ギャラリストは鑑賞者へと、不幸にも”さらされた”のではない――なぜなら、はじめから隠されていたわけではないのだから。(ペルトマキ)
他にも、展示の開館時間のあいだ批評家やキュレーター、芸術家、学生などを常駐させて、特にトピックを与えずに議論させたインスタレーション(1975, ロサンゼルス現代美術研究所:LAICA)や、一定人数の鑑賞者を雇って、特定の作品10を集団で一定時間鑑賞させつづけたインスタレーション(1982, 「74th American Exhibition 」シカゴ美術館)などでは、美術館自体のスタッフではなく、別の立場の「美術関係者」の、制度のなかでの労働を、契約によって浮き立たせています。
」シカゴ美術館)などでは、美術館自体のスタッフではなく、別の立場の「美術関係者」の、制度のなかでの労働を、契約によって浮き立たせています。
自発的に議題を選ぶこと、個人的に作品と向き合うことが、美術館のもつ枠組みやイデオロギーと切り離せないかたちで、二重化する。それはなにか指示や制約が与えられたわけではない、自由なはずの議論や鑑賞であるのに、むしろその曖昧さのなかで、葛藤や反省が刺激されます。
制作者・製造者との契約をもちいた作品もあります。カーペットを職人に依頼して複製11したり(1981)、製紙を学ぶ学生に紙を複製させて展示カタログに用いる作品(1986)があたります。こうした作品は、実際に展示の成立に寄与する点で、その「支持体=サポート(support)」とも言えるでしょう。この点は、第4章の論点にも繋がります。
また「制作」という面では、展覧会の制作もアッシャーのモチーフになります。2000年、ロサンゼルス・カウンティ美術館の企画「LACMAlab」でアッシャーは、当企画が「子供とその家族」をターゲットにした教育的ミッションを掲げていることに着目し、常設展示の展示替えを、近くにある高校の生徒にまるごと任せます。このときももちろん契約を結んでおり、あくまで外部から招聘したプロフェッショナルとして扱い、12美術館スタッフが介入しないように取り決められていました。必ずしも通常正典的に扱われる作家を重視せず、白壁や壁面設置の慣習にもとらわれない展示は、それ自体が美術館における労働と慣習の制度を、観られる展示において、照らし返すものだったと言えるでしょう。
以下、ペルトマキによる結論を引きます。やや長文ですが、多くのインスタレーションや参加型プロジェクトと対置した、アッシャーの作品の批評性が明快に概括されています。
アッシャーの初期の参加型プロジェクトと同様、LACMAでアッシャーが設定した構造の制限は、生徒たちに、十分に自由な裁量を与えていた。それでもやはり、行為へ自由に参加するというこのことは、その作品のなかで自身のふるまいに責任をもつという義務と、結びついている。(ペルトマキ)
アッシャーの作品において、「参加」とは、すでに仲介された意味や、すでに定められたいくつかの芸術的・政治的目的を強調するために、美術館やギャラリーの来場者を巻き込んだり、芸術家が認知している意図へと優先権を置くようなものではない。むしろ、参加者がもともと持っている制度的な役割のほうを、その参加型プロジェクトのなかで役割やアクティヴィティの特異性が、アッシャーの作り出した状況にある物質的な側面へと合うようにしていくのだ。〔…〕慣れ親しんでいる『日々のアクティヴィティ』が美術館やギャラリーの来場者の前で演じられる、という契約は、ミニマリズムやコンセプチュアル・アートのインスタレーションのもつ、来場者が美術館やギャラリーにいるあいだに芸術家の描き出した構想を見せつける、という戦略からは異なっている。〔…〕美術館・ギャラリーの来場者のような集団的・匿名的な経験にかかわるのではなく、アッシャーの参加者は、自身の名前、態度、プロフェッショナルとしての評価をもって、自分がそれに巻き込まれることを承り、作家の作品に貢献するのだ。このような、明示されたプロフェッショナルのコミットメントは、アッシャーの作品において、あらゆる労働が参加者にとって個性づけられていることを意味している。クレア・コプリー〔オフィスを隔てる壁を取り除かれたギャラリスト〕は、匿名の役者でもなければ、非人称化された〈とある一般のギャラリスト〉でもない。彼女はアッシャーの作品が実行されているギャラリーのオーナーであり、その展示の成功に、個人的またプロフェッショナルとしての関与をもつ。(ペルトマキ)
また、アッシャーによる参加型アクティヴィティは、参加者に過度なインストラクション(指示)を与えることを拒んだことによって、さらに特徴づけられている。作者直々の教訓主義(authorial didacticism)に陥らないことを見越したアッシャーの慎重な配慮は、そのような参加的アクティヴィティを、多くの分析的で情動的な反応へと、その経験によって開かれるようにする。アッシャーの作り出した状況のなかで自身の行為を見越しながら、何かひとつの選択をすること、そしてそのプロセスにおける自身の関与、その関与がいかに自身に影響したかを解釈することによって、ギャラリストや美術館職員、学生たちは、そこでの自身の役割に、個人としての感覚を分け与える。アッシャーの作品における参加は、契約を結んだひとりひとりのための開かれをもたらし、日常的な集団的、社会的関係から解放する。それによって、芸術制度がもつ社会的・イデオロギー的権力との関係のなかで自身のアイデンティティがいかに形成されたか、という問いに直面するのだ。(ペルトマキ)
第3章 作家の名において(In the Name of the Artist)
さて、このような美術の制度のなかで、まだ取り上げられていない要素があります。それはほかならぬ作家自身です。
言うまでもなく、個人的な情報や生活をこれみよがしに開示するような作品ではありません。ここでもアッシャーという個人名は、制度のなかの状況において、作家という存在がもてる権力について検討するために用いられるモチーフです。
初期の、名前や「わたし」という一人称代名詞、さらには居住区の郵便番号をもちいた作品もいくつかありますが、注目すべきは、これもまた第2章のように「契約」のなかに組み入れられる作品でしょう。
1978年、アーティストが運営するオルタナティブ・スペース「Los Angeles Contemporary Exhibitions(LACE)」にアッシャーが提出したプロポーザルは、当の建物の「賃貸」をめぐるものでした。アッシャーは、4ヶ月のあいだその建物の大家となって、改めてLACEにその建物を再リースする、というプロジェクトを建てました。そこで開かれる展示の内容について、アッシャーは報告を受ける義務をもち、また作家のほうにもこの権利関係は知らされる……といったものです。建築を利用する権利もまた、展示をはじめとした芸術的活動を成り立たせる「支持体=サポート」とすれば、前章で取り上げた備品や消耗品と同様に、次の第4章にもつながるトピックといえるでしょう。
前章で取り上げたような、スタッフや関係者、学生などとの契約と異なる点は、作家という、作り手のアイデンティティをもち、また権利をもつ存在が、他者の芸術活動の基盤に挿入されているということです。とはいえ、実際多くの芸術作品やその展示は、それが成り立つために、当の作家以外に、多くのエージェンシーをもつはずです。そのような一種の権力関係を、心理的・経済的・象徴的な側面からプレイに持ち込む点が、アッシャーのプロジェクトの特徴です。このプロポーザルが、第2章で触れた、2つのギャラリーの業務を交換する作品と同時期であることに、ペルトマキは注意を払います。
ただし、このプロポーザルは「技術的な理由」から実現には至りませんでした。同時期にヴァンアッベ市立美術館に提出された、展示室の権利を2年間購入して美術館に再リースし、アッシャーの名前を冠するというプロポーザル(1978)や、後年に同館に提出された、アッシャーの名前を冠した信託基金を美術館と共同で設立するというプロポーザル(1985)も、結局却下されています。いずれの計画では、美術館と作家との金融的な契約が、一種の報酬・助成かのように機能する点が肝になっています。
このような、「運営構造に自身を挿入する」プロジェクトのうち実現に至ったものが、1979年にロサンゼルス現代美術館13(MOCA)で行われたものです。イントロダクションで触れた図録もこの展示に際して刊行されています。
このプロポーザルでは、MOCAのロビー14の権利を4年間、100ドルの一括払いで支払い、それを当の美術館に再リースするというものです。運営および広報などが行われる空間の「テナント」となることで、アッシャーはさらに、美術館が「貸主」アッシャーを、規定の様式で顕彰することをプロポーザルに含めました。つまり、作品寄贈者などと同じオーダーで、ロビーに自身の名前を冠することを求めたのです。
結果的に、このプロポーザルは、二重リースではなくライセンス権の形と、また期間の短縮を経て、実現されました 。開館はじめの20ヶ月、ロビーには「The Michael Asher Lobby」という銘板が柱に取り付けられ、詳細はデスクに記載されました。ペルトマキは、「命名」という言語行為に関してオースティンに触れながら、この命名行為が、アッシャーと美術館との適切な意図と合意によって成り立っていることを指摘します。
。開館はじめの20ヶ月、ロビーには「The Michael Asher Lobby」という銘板が柱に取り付けられ、詳細はデスクに記載されました。ペルトマキは、「命名」という言語行為に関してオースティンに触れながら、この命名行為が、アッシャーと美術館との適切な意図と合意によって成り立っていることを指摘します。
同時にペルトマキは、あくまでこの顕彰が、普通の寄贈者とまったく同様のものではないこと15を強調します。ここで顕彰されているアッシャーの貢献は、実質的には「芸術家としての」貢献であり、公式のものとは一線が画されますが、しかしそれは、財政的・政治的なスポンサーへ賛辞を贈るという慣習を避けるという結果をもたらした、とペルトマキは付言しています。
言語や命名をつうじて、芸術家自身を対象とした一連のプロジェクトにおいて、アッシャーという名前=記号は、制度がもつ利益そして情動が凝縮されたものだ、とペルトマキは指摘します。
2007年にアッシャーの名は改めてMOCAに「顕彰」されます。それは、アッシャーが所有していた、主に1970年代に活躍した美術家の作品を37点、MOCAに寄贈したことに際してであり、つまり作品としてではなく、通常の貢献にたいする顕彰です。とはいえロビーの銘板とは異なり、寄贈作品の展示に「芸術家による寄贈:マイケル・アッシャー(Artist’s Gifts: Micheal Asher) 」と題されるというものでした。ペルトマキは、この「芸術家による」という言い回しが、1983年のプロジェクトも含めたアッシャーの貢献をも(結果的に)指していることを示唆しています。
」と題されるというものでした。ペルトマキは、この「芸術家による」という言い回しが、1983年のプロジェクトも含めたアッシャーの貢献をも(結果的に)指していることを示唆しています。
さて、このようなプロジェクトはしかし、芸術家の名によってプロポーザルが合理的なものとして受け止められる以上、それは文化資本のなかで権力が交換されているだけではないか。そうペルトマキは問題提起してから、むしろアッシャーが美術館を「サポート」するという転倒を主題としたプロジェクトを次章で紹介します。
第4章 制度的サポート=支持体(Institutional Support)
本章で扱う作品は、美術館やギャラリーがおこなう「サポート=支持体(support)」に着目したものです。
まず物理的な支持体として、たとえば壁が挙げられるでしょう。ギャラリーの壁を取り払った作品を第2章で紹介しましたが、逆に壁を移設する作品(シカゴ美術館)や複製する作品(ハウス・ランゲ)もアッシャーは手掛けています。あるいは、暖房システム (ベルン美術館)や中二階(クンストラウム・ヴィーン)を移設した作品も、1990年代に手がけています。
(ベルン美術館)や中二階(クンストラウム・ヴィーン)を移設した作品も、1990年代に手がけています。
そのなかでもペルトマキが取り上げるのは、ドクメンタ7(1981)のプロジェクトです。キュレーターのルディ・フックスは、会場の壁が不十分であることを事前に招待作家に知らせており、アッシャーはそれにたいして、展示壁16を提供する、という作品を提出しました。つまり、「作品の支持体(support)」を「作家の援助(support)」によって提供した、という二重の意味で「サポート」の壁だといえます。展示ハンドアウトには、その壁に展示される数人の作家の名前とともに、重なるように「アッシャー」の名が大きく記されています。前章で、展示会場や美術館ロビーの権利を得ることで他者の作品の象徴的・経済的な「支持体」となる提案をしたアッシャーは、ここではより物理的かつ実際的に「支持体」となっています。ともあれこれは契約というより、贈与であるという点で、前章終盤で触れた「寄贈」と比較して考えられるかもしれません。
「l’art conceptuel, une perspective」展(1989, パリ市立近代美術館)では、美術雑誌の広告枠をアッシャーが自費で買い取り、当展の広告を掲載しました。もともとは、コンセプチュアル・アートを経験した、当時シニアになっていた世代向けの新聞・雑誌に掲載する予定でしたが、プロジェクトの変更を経て、美術史家向けの雑誌が対象に選ばれました。当展自体が、コンセプチュアル・アートを歴史化・回顧するという向きの展示であり、アッシャーもはじめは、1972年の作品の再展示を求められていました(拒否)。歴史化するというフォーマット・イデオロギーをもつ展示を、実際に史学者の見聞に触れさせることがアッシャーの提案でした。同雑誌は、美術館会場でも購入できるようになっていました。
こうした「歴史化」へのアプローチは、MoMAでの展示「The Museum as Muse: Artists Reflect 」での作品にも現われます。アッシャーは、MoMAが1929年の設立以来に売却したすべての絵画・彫刻のカタログを編纂するというプロポーザルを提出しました。そのカタログはMoMAがふだん刊行しているカタログと同じデザインで実際に印刷されることをアッシャーは固辞し、印刷コストを埋め合わせるために、美術館の書店で販売することもプロポーザルに含みました(現在はウェブ上にアーカイブ
」での作品にも現われます。アッシャーは、MoMAが1929年の設立以来に売却したすべての絵画・彫刻のカタログを編纂するというプロポーザルを提出しました。そのカタログはMoMAがふだん刊行しているカタログと同じデザインで実際に印刷されることをアッシャーは固辞し、印刷コストを埋め合わせるために、美術館の書店で販売することもプロポーザルに含みました(現在はウェブ上にアーカイブ )。このカタログの編纂・制作は、アッシャーではなくインターンによって制作され、展示会場ではベンチの上に置かれて展示されました。
)。このカタログの編纂・制作は、アッシャーではなくインターンによって制作され、展示会場ではベンチの上に置かれて展示されました。
編集・販売をMoMAが行ったために起きた、興味深い点をペルトマキは2つ挙げています。ひとつは販売について、書店でこのカタログは店頭ではなくレジ後ろに保管され、知っている客(展示の来場者)しか求められないようになっていました。このような隠密は、クロウやロベルタ・スミスといった批評家に、違法ポルノの流通と比較されています。もうひとつは、カタログ冒頭に、アッシャーのステートメントと並んで、絵画・彫刻部門のキュレーターによるテクストも並んでいる点です。そこでは、作品の売却は新たな作品の収蔵のためであることを強調するとともに、収められたリストに「ミスや限界がある」「通常の目録と同じ正確性があるかわからない」ことを宣言するものでした。
このテクストは、アッシャーとMoMAとの動機や意図の不一致を証しています。前章最後に触れた、文化資本のなかでの権力の共犯的な交換が、うまくいかないケースが記されています。1971年に起きたグッゲンハイムによるビュレンやハーケ作品への検閲と比較して、むしろこのカタログは、目に見える形で、アッシャーの作品を公認しながら、自身の歴史とともに否認するというMoMAの分裂を示していることをペルトマキは指摘しています。
「Artists Reflect(作家は反省する)」という展示において「美術館が反省する」ような、関係の転倒が起きた、といえるでしょう。
アッシャーは、美術制度・機関とのあいだに、権力関係と切り離せない契約を結ぶことで、その関係を形づくり、またその作品によって形づくられるような状況へと、その場(サイト)を拡張します。
アッシャーの作品において、社会的な関係は、まさにフーコーのいう意味で経験的なものとなる。それは、知識・ルール・主体性の生産を再び開くのだ。鑑賞者、参加者、制度=機関の代表にとって、アッシャーのプロジェクトは知識を呼びおこし、ルールとともに、あるいはルールに対抗してプレイする。そして、変化のポテンシャルをけして失わないような領域として、主体性を構成するのだ。(ペルトマキ)