アンネ・リング・ぺーターセンの『インスタレーション・アート:イメージと舞台のあいだ(Installation Art: Between Image and Stage)』(2009)1の各章をまとめました。
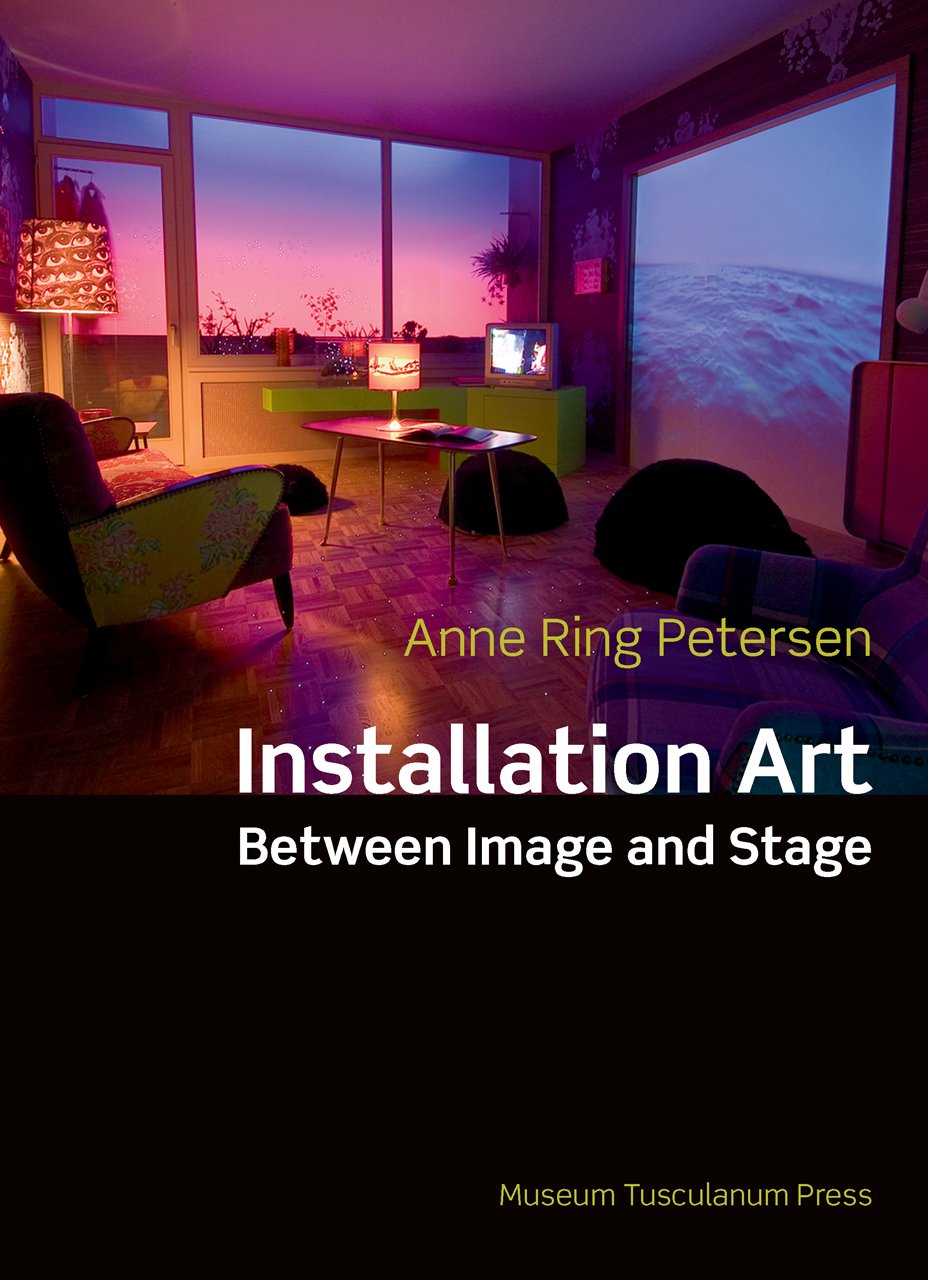
書影
本書の特徴は、以下の2点でしょう。
- パフォーマンス史・「パフォーマティヴ」概念を、インスタレーションの歴史や形式に対置している
- インスタレーション形式がもつ複数の側面の整理
順に説明します。
(1.)まず、パフォーマンス史・「パフォーマティヴ」概念を、インスタレーションの歴史や形式に対置している点。
タイトル「イメージ(image)と舞台(stage)のあいだ」の通り、本書は視覚芸術史の延長におけるインスタレーションが、その黎明期である1960年代・1970年代に隣接分野である演劇・パフォーマンス・アートから、そして1990年代に定着した「パフォーマティヴィティ」概念から影響を受けていることを、話の展開の軸に置きます。
たとえばライス『周縁から中心へ』は環境への鑑賞者の〈参加〉をインスタレーションの「本質」としました。たいして本書は、〈舞台〉というテーマを採ったことで、参加と、距離をとった鑑賞との同居・バランスを注視できているように思います。同様に、前者と結びつけられて強調されがちだった〈現象学〉〈鑑賞者の包含〉の側面も、〈フィクション〉〈作品の自律〉という対照的なトピックと合わせて語られます。
(2.)このような、複数の側面が同居することへの重視が、もうひとつの特徴に活かされます。
本書は、「空間」「時間」「鑑賞者の行為」「演劇性・パフォーマティヴィティ」といった、インスタレーションを論じるさいに重要になるトピックについて、それが指す複数の意味・側面を整理しています。
たとえば空間については、空間の物理的なありかた、鑑賞者の認識、外部との分割、意味のまとまり、という4つの異なる特徴を分けて扱っています(詳細は第5章)。そのため、各特徴を混同・偏重することない、より精緻な分析ができる概念を提供しています。
そうした総覧的な性格のため、本書は非常に巨大な本になっています。判型もさることながら、ページ数が注釈も含めると500ページに達しています。同時に、ビショップの「脱中心化」や、レーベンティッシュの「プロセス」のような、ひとつの鍵概念に沿った構成では必ずしもありません。
そのため以下の要約では、細かい・具体的な文献参照や作品紹介は最小限にとどめ、各章順に概念整理を紹介します。特に「フィクション的空間」「ヴァーチャルなフレーム」(第5章)「パフォーマティヴなリアリズム」(第7章)「ネットワーク化したサイト・スペシフィシティ」(第10章)は特に「かゆいところに手が届く」概念なので、重視しています。
イントロダクション
序章では本書の方針が示されます。
まずペーターセンはインスタレーションの一般的な性格を以下のように紹介します。
インスタレーションは――彫刻に似て――三次元の形状をもつ。とはいえ、彫刻の場合のようにひとつの孤立したオブジェクトとして形をもつというより、インスタレーションは、空間あるいは空間的な舞台美術が、想像をとおして意味や感覚的経験を伝えるという形が特徴だ。そのため、インスタレーションは鑑賞者がその中に入れるような大規模な芸術作品であり、それは、スペクタクル的で美的に舞台に挙げられた出来事、そして感覚をもよおす文化的経験を求める、現代の要求を満たしているのだ。(ペーターセン)
フラットな説明です。これはおおむね本書全体の構成に対応します。続けて、冒頭に紹介したとおり、本書の方針が紹介されます。
本書はおもに、インスタレーション・アートの舞台的、またパフォーマティヴな(scenic and performative)側面に注目する。またさらに、パフォーマンス・アートや演劇における、視覚的ないしインスタレーション的な要素をも見定める。(ペーターセン)
本要約では基本的に前者を紹介します。実際同書の構成・ページ数をみても、後者はあくまでサブのようで、上記に示した「概念の複数の側面の整理」もインスタレーションにとって重要なものばかりです。
ペーターセンは、従来の遠近法絵画に代表される「中心的なパースペクティヴ(central perspective)」の象徴形式はインスタレーションに適用できないと考えます。中心的なパースペクティヴとは、作品の空間の外の抽象的な位置に主体を据えるモデルです。たいしてインスタレーションの空間モデルは、見る者の周りに空間が広がっていく、現象学的な、「環境的な(ambient)」ものです。
この特徴は、本書の以降の章や、ビショップ、ライスなどが強調する鑑賞者性の問題にも結びつきます。鑑賞者は空間にたいして自分の視点をかたちづくる。それは、ただ模倣で空間やものを表象して見せるイリュージョニズムではなく、作品の「舞台」に足を踏み入れた鑑賞者が利用させられる、「舞台に上げられたイメージ、フィクション、状況(staged images, fictions and situations)」という形のリアリズムを呈します。
本書の目的は、歴史的記述でも、分類でも、哲学・美学でもなく、インスタレーションという「ジャンルのもつ主要な規則(principle)」を、帰納的・認識論的に導くことです。
以降の章で紐解いていくのは、インスタレーションという芸術形式の特徴、「知的で感覚的なリアリズム」と「演劇性」が組み合わさっている点です。その点で、彫刻や、あるいは単なる「イメージ」とは異なる。こうした点がいかなる「文化的ダイナミズム」に由来するかを分析するために、本書はパフォーマンス研究との比較、メディア研究・文化理論の導入など、積極的に多様なアプローチをとっています。
またペーターセンは、2000年代以降の近現代美術やその議論における「政治的転回」に触れます。ネオリベラリズムや環境危機、差別、移民等のトピックを具体的に挙げつつ、そうした政治化によって、いっぽう「美的な言語・経験・カテゴリー」についての言説は枯渇してしまった、とペーターセンは批判します2。その裏でインスタレーションは、どのような芸術なのか反省されずにいつしか「自然化」されてしまった。
本書は、鑑賞者の包含やインタラクト自体を政治的に主題化するのではなく3、その形式的なパターンの整理分析に注力しますが、それにはこのような問題意識があるでしょう。
第1章 定義に向けて(Towards a definition)
The weather project, 2003 from Studio Olafur Eliasson , YouTube
, YouTube
本書でペーターセンはインスタレーションを「passage work」と形容します。「passage」が意味するところは、「通路」の構造と、「通過」の運動・状況の両方です。ペーターセンはこれを「領域と状態の敷居」と言い換え、1970年代のポストミニマリズムや、ロザリンド・クラウスの著書『近代彫刻における通路=通過(Passages in Modern Sculpture)』(1977)をこの語の由来として説明します。身体、認識論、参加という多くのトピックにつながる形容ですが、批評的な鍵語というより、おおまかなスローガンとして捉えたほうが良いでしょう。
ペーターセンは「passage」という語が、「裂け目」「周縁」などのロマンティックな語と関係することを注意していますが、それも前述のとおり形式の安易なイデオロギー化を避けるためにも読めます。
イントロダクションに示したとおり、本書は「ジャンル」論です。ペーターセンがここでいう「ジャンル」は、本質主義的でない、混交的で変化する伝統という意味で使われます。
絵画・彫刻・写真といった、共通した形式的特徴をもち、その描出が相互に関係した方法にもとづくまとまりに作品を分類するような語とは対照的に、インスタレーションという語は、芸術のこの種の内在的な特別な形式的・技術的な特徴を囲い込んでいるわけではない。(ペーターセン)
インスタレーションは、物質とそのコードに定義される「メディウム」ではなく、実践者が自由に用いる慣習・ルールに定義される「ジャンル」だ、とペーターセンはまとめます。むしろインスタレーションにおいて、あらゆる種類のメディウムが組み合わさります。
そしてそうした慣習には、作品の実践以外にも、たとえばある作品の美術館収蔵やカタログ記載などで「インスタレーション」と定めるような、言説的なものも含まれます。続く第2章・第3章は、インスタレーションのジャンル定義に寄与する「言説」に集中することで、このジャンルを成り立たせる「家族的類似」4を分析します。
上記のような理由から、ペーターセンはあくまでインスタレーションに共通する特徴が少ないことを主張します。本書が諸概念を「切り分けて」いく構成なのも、共通点より差異づけに方法論を置くためでしょう。
とはいえ実際的な大まかな傾向として、ペーターセンはオラファー・エリアソン《The Weather Project》(2003) を好例に挙げて、①空間・文脈を活性化(アクティベーション)すること、②時間のなかで状況・プロセスをもつこと、③鑑賞者が主体的・身体的経験をもつこと、を挙げます。以下段落に分けて簡単に紹介します。
を好例に挙げて、①空間・文脈を活性化(アクティベーション)すること、②時間のなかで状況・プロセスをもつこと、③鑑賞者が主体的・身体的経験をもつこと、を挙げます。以下段落に分けて簡単に紹介します。
①インスタレーションはその語源どおり「どこかに何かを置くこと(placing something somewhere)」であり、そうして空間的構造を組織します。この点は芸術概念の拡張、つまり「自律の放棄」としばしば結びつけられてきましたが、ペーターセンはレーベンティッシュ同様5、作品は従来どおり世界・日常からは切り離されており、自律性概念のほうを再考すべきと考えます。このような「空間」の問題は、第5章で詳しく見ていくことになります。加えて、絵画や彫刻と異なり展覧会の閉幕と同時に解体される点で、インスタレーションは文脈にも依存しています。これは、1960年代以降「鑑賞者のアクティベーション」とみなされてきたポイントです。
②マイケル・フリードはモダニズムの絵画や彫刻を「瞬間性(instantaneousness)」で特徴づけ、たいしてミニマリズムの時間的経験は「持続(duration)」があるといえます。インスタレーションにもこの特徴は引き継がれており、ペーターセンはそれを「芸術作品の経験がもつ状況的性格と結びついた、空間的なドラマツルギーの時間的性格(temporal nature of its spatial dramaturgy that, in combination with the situative nature of the experience of the artwork)」とまとめています6。
③鑑賞者はインスタレーションの中で動き回ります。額縁や台座によって鑑賞者の空間を作品の空間から切り離すのではなく、むしろそれらが重なり合っているために、鑑賞者はみずから現象学的経験や主体性に気づく。
以上の3つの特徴は従来のインスタレーション論でしばしば扱われてきた点です。本書でいえばそれぞれ、第5章の「空間」に①、第6章の「時間」に②、第7章の「演劇性」に①③が主に対応すると思います。
あるいはカテゴリで分ければ、(A)「ものの設置の形(installation)」(B)「時間(time)」(C)「文脈(context)」の3要素の結びつきとも考えられます。
これらもまた、(A)は第5章、(B)は第6章、(C)は特に具体的には第9章・第12章で扱う映像メディアとの関係や、第10章で扱う「場=サイト(site)」に対応します。
第2章 インスタレーションの明確化(Articulating Installation)
前章で述べたように、本書は、作品実践だけでなく、インスタレーションをめぐる「言説(discourse)」つまりテクストも、その定義に寄与するものとして取材します。
ペーターセンは、ノーマン・フェアクローやミシェル・フーコーを参照して、「言説の領界(order of discourse)」という語を導入します。たとえば芸術の「言説の領界」は、彫刻についての言説、受容美学についての言説、制度批判について、アヴァンギャルドについて、モダニズムについて、ポストモダニズムについて……など、さまざまな「タイプ」の言説が含まれています。このような、ある社会の領域・制度のなかで用いられている言説の総計を、ここで「言説の領界」と指しています。
そうした並立する言説どうしは、一致合流するというより、含まれる概念の衝突や不和をもつことで生産的になるものです。「作品」「形式」といった概念が、それぞれの言説で別のニュアンス・役割に結晶化するように、「インスタレーション」もまた、それぞれの言説ごとに異なる特徴づけのされる概念でしょう。
詳述は省きますが、たとえばインスタレーションは、1960年代・1970年代の「彫刻」や「エンヴァイロンメント」の言説と関わります。
クラウスの「展開された場における彫刻」(1978)や、『美学百科事典』『The Art Index』での「エンヴァイロンメント」概念との淘汰関係です。あるいは同時期には「巻き込み(involvement)」「アクティベーション(activation)」という受容美学的な言説が登場します。鑑賞者という主体を焦点においた「状況的な経験の形成(situative experience formation)」(ゾティリオス・バーツェツィス)をインスタレーションはおこなう。あるいは受容美学という点では、「対象(object)から空間へ」という言われ方も多くあります。さらにフリードの「芸術と客体性」(1967) に代表される「モダニズム」、さらに「ポストモダニズム」といったイデオロギー的言説、また同じテクストから派生し、ライスやマイケル・アーチャーなどが扱う「演劇性」という言説が挙がります。
に代表される「モダニズム」、さらに「ポストモダニズム」といったイデオロギー的言説、また同じテクストから派生し、ライスやマイケル・アーチャーなどが扱う「演劇性」という言説が挙がります。
とくに「空間」の言説については多様です。作品そのものである「空間」、鑑賞者が作品に関わるところである「空間」など、前者についてはアラン・カプローのテクスト「全体芸術の制作についてのノート」(1958)、ジェニファー・リヒトが1969年にMoMaで企画した「Spaces 」展やジェルマーノ・チェラントが1976年のベネチア・ビエンナーレで企画した「Ambiente/Arte」で発表したエッセイ「Artspaces」などを、後者についてはレズリー・ジョンストーンの著書『インスタレーション:文脈の発明』(1985)やマイケル・アーチャー『インスタレーションに向けて』(1994)、さらにブライアン・オドハティ『ホワイトキューブの中で』(1999)などを挙げてペーターセンは説明します。後者はとくに、第12章で触れる「スペクタクル」や「後期資本主義」の問題として取り沙汰されるものです。
」展やジェルマーノ・チェラントが1976年のベネチア・ビエンナーレで企画した「Ambiente/Arte」で発表したエッセイ「Artspaces」などを、後者についてはレズリー・ジョンストーンの著書『インスタレーション:文脈の発明』(1985)やマイケル・アーチャー『インスタレーションに向けて』(1994)、さらにブライアン・オドハティ『ホワイトキューブの中で』(1999)などを挙げてペーターセンは説明します。後者はとくに、第12章で触れる「スペクタクル」や「後期資本主義」の問題として取り沙汰されるものです。
ペーターセンはこうした、諸々の言説を、大きく3つのアプローチに分けます。
- 現象学的(phenomenological)アプローチ
- 文脈主義的(contextualist)アプローチ
- パフォーマティヴ+受容美学的(performative and reception aesthetic)アプローチ
これらは必ずしも網羅的でも排他的でもない特徴づけです。あくまで内容に即したものですが、おおよそこの順に登場・発展したといえます。「現象学的」な言説は、1960年代・1970年代ごろの、彫刻やメルロ=ポンティの現象学の言説に由来します。「文脈主義的」な言説は、特に1980年代ごろに、構造主義やポスト構造主義、コンセプチュアル・アートの隆盛に影響される形であらわれます。政治性、制度批判の導入といえるでしょう。
インスタレーションは現在の形式では、受容美学の文脈と意識に焦点を置き、1960年代にエンヴァイロンメント・アートやミニマリズム、ポストミニマリズム、ランドアート、コンセプチュアル・アート、そしてパフォーマンスなどによって敷かれた理論的な基礎の外で考えることはできない。そのため、本書はインスタレーションを、1960年代から登場した理論的議論と、また当初の社会・文化・芸術的変化とのインタラクションにおいて登場したジャンルとみなす。(ペーターセン)
とはいえ、文脈主義あるいは「コンセプチュアル」な性格を重視するピーター・オズボーンが現象学的な側面を軽視するように、両アプローチはしばしば衝突しながら、統合されませんでした。
3つ目の「パフォーマティヴ+受容美学的」はこの衝突を解消する傾向があります。鑑賞者を巻き込む現象学的な関心と、周囲の世界との「パレルゴン」的関わりを重視する文脈主義的な関わりの両方、そしてその協働を関心に置くもので、たとえばユリアーネ・レーベンティッシュ『インスタレーションの美学』、ゾティリオス・バーツェツィスの博士論文「インスタレーションの時代:状況的経験の形成と近代美術」、アンゲリカ・ノラート「パフォーマティヴ・インスタレーション」、グラハム・コルター=スミス『インスタレーションの脱構築』、フォーク・ハインリッヒ『インタラクティヴ・デジタル・インスタレーション・アート』などが挙げられます。
第3章 インスタレーションへの諸観点(Viewpoints on installation)
本章は、さらに具体的に言説を紹介するパートです。
まず「現前の経験」を重視したロバート・モリスのテクスト「空間の現在時制」(1978)。オブジェクト重視だった「彫刻についてのノート」(1966)にたいして、建築を参照しながら、空間へとモリスの焦点は移っています。このような「現前」への美学的重視は、フリードの議論はもちろん、マーガレット・モースが『ヴィデオ・インスタレーション・アート』(1990)で「表象」に代えて「提示(presentation)」を重視し、インスタレーションを「経験を経験する場」とみなす点にも通じています。対照的にブライオニー・ファーはむしろインスタレーションの状況はなお表象の領域のなかにあり、媒介された経験だと考えました。
観客の参加にも政治的に結びつく「現前」への現象学的重視は、むしろ表象の要素を無視する偏向を生んでしまっていたと指摘できるでしょう。
文脈主義的なものでは、カプローの著書『アッサンブラージュ、エンヴァイロンメント、ハプニング』(1966)はオルタナティヴ・スペースで活動するなかでの反美術館的姿勢を打ち出しています。カプローが重視した芸術と生活との接続は、マーク・ローゼンタール『インスタレーション・アートを理解する』(2003)でも重視されます。より具体的に政治的なものでは、前に挙げたオドハティの議論や、ベンジャミン・ブクローの市場・ギャラリー・資本主義批判があります。あるいはより存在論的なもので、アンドリュー・ベンジャミン『オブジェクト絵画』(1994)も挙がります。
またニューヨークにおけるインスタレーションと美術館との関係を追ったジュリー・H・ライス『周縁から中心へ』(1999)、テーマごとに複数の歴史を描き出したビショップ『インスタレーション・アート:ある批評史』、彫刻の「上演(staging)」というテーゼから迫ったアレックス・ポッツの論文「インスタレーションと彫刻」(2001)が紹介されます。
「パフォーマティヴ+受容美学的」アプローチとしては、文字通りのノラート編『パフォーマティヴ・インスタレーション』(2003)が挙がります。
以上を総括して、インスタレーションは「橋渡し役」つまり「通路=通過」だ、とペーターセンは改めて形容します。建築と彫刻、視覚芸術と映像メディア、表象と提示、日常と芸術、外部と内部……というように、多くの次元でインスタレーションは「弁証法的カテゴリー」として考えられます。
それがどのような「通路」かといえば、現象学的には、そこを通る鑑賞者の反応・経験を媒介する「ふるまいのための構造」(ナスゴール)、ないし行為を媒介する「空間性」(ボルノウ)ともいえるし、また美学的にも、鑑賞者と対象とのあいだを実験的・主観的につなぐよう特殊に作られた構造といえます。
本書はパフォーマンスとインスタレーションのあいだに「通路」を開くことでそうした側面を分析しようとします。クラウスの議論や、あるいは「演劇性」という語の、イデオロギー的な性格も含めた広い利用に目配せしながら、ファーやノラート同様、インスタレーションの言説における、パフォーマンスや演劇の言説からの影響をペーターセンは改めて強調します。
第4章 パフォーマンスの明確化(Articulating Performance)
本章は短くまとめます。インスタレーションの言説に影響を与えるところの、パフォーマンスの言説の紹介が本章の題材です。
1970年代にパフォーマンスが表現の形式として確立してから、1980年代には、「パフォーマンス」という語が、作品カテゴリだけでなく、書籍や展示でも見られるようになり、広い文化研究のサブカテゴリーとなります。
いっぽう「パフォーマティヴィティ」は、言語行為論を確立したジョン・L・オースティンがレクチャー(1955)および著書『言語と行為』(1962)で概念づけた「パフォーマティヴ」という、言語が指示だけでない行為を行うことを指す形容詞に由来し、ジャック・デリダの脱構築哲学やジュディス・バトラーのジェンダー研究の議論を経て、言語に限らない身体的・社会的ふるまいに広く用いられるようになった概念です。
この両方は、1990年代には芸術・人文の領域に広がり、この学際的な現象は「パフォーマンス的=パフォーマティヴ転回(performative turn)」とも呼ばれます7。上演(staging)、演技(act)、仮装=見せかけ(masquerade)、スペクタクル(spectacle)とった概念・語彙が文化の言説で広く流通しました。ただのいちジャンルではなくなったそれは、いわば「プロセス」志向の「認知の形式」です。
インスタレーションにおける、鑑賞者の参加への強調は、この文脈において、視覚芸術においてパフォーマティヴ的転回がもったようなインパクトの結果なのだ。(ペーターセン)
インスタレーション同様、演劇・パフォーマンス分野でも、1960年代から1980年代にかけては大きな変化があります。従来のドラマテクスト重視の伝統から離れた「混合した方法を用いる」(コステラネッツ)新たな演劇が現われます。ハプニングやイヴェントといった、美術の言説でも触れられる類のパフォーマンスだけでなく、「ニュー・シアター」「キネティック・シアター」「アクティヴィティー」「アクション・シアター」などが、当時の間領域的で実験的なものとして現われました。
そうしたパフォーマンスでは、インスタレーション同様やはり「媒介なき現前」が美学的に重視され、従来の演劇形式の「核」とされた物語的な表象とは対照します。そうした点で、インスタレーションにせよパフォーマンスにせよ、この時期の動向は「モダニズム」の本質主義的な存在論にたいするカウンターという意味で「ポストモダニズム」といえるでしょう。ただし、「媒介なき現前」の神話は後年、ポスト構造主義や脱構築主義のもとで批判・再解釈されていきます。またポストモダンという言説として、ジャン=フランソワ・リオタール『ポストモダンの条件』やニック・ケイ『ポストモダニズムとパフォーマンス』がパフォーマンスとの関係では挙げられます。インスタレーションも、その言説において「ポストモダン」な実践とみなされやすい点ではパフォーマンスとよく似ています。
第5章 形づくられた空間としてのインスタレーション(Installation as shaped space)

Vito Acconci, Instant House, 1980 flags, woods, spring, ropes, and pulleys, Collection Museum of Contemporary Art San Diego, Museum purchase 1984.6
本章ではインスタレーションがいかなる「空間(的構造)」をもつのかが検討されます。
冒頭で述べたように、本書は「鑑賞者の参加」を必ずしも偏重しません。絵画や彫刻においても、作品と鑑賞者とのあいだに対話や身体的関わりは当然あるし、また同時代のハプニングやパフォーマンス、ヴィデオ、コンセプチュアル・アートでも同様です。ペーターセンはインスタレーションに関する「参加」の過度な強調は、他の特徴を見逃す原因になると批判します。
私が論じたいのは、インスタレーションを他の芸術から区別する主たる特徴は、鑑賞者の強い関わりではなく、空間的な構造だということだ。(ペーターセン)
つまり、インスタレーションが彫刻と異なるのは、それがオブジェクトをデザインすることについてではなく、建築のように、空間をデザインすること、あるいは演劇のように、空間を鑑賞者のために舞台化=上演することによってなのだ。同時にそれは鑑賞者を、伝統的なプロセニアム演劇よりも能動的・身体的に、作品とのパフォーマティブなやりとりへと巻き込む。(ペーターセン)
インスタレーションは、どのように「形づくられた空間(shaped space)」なのか。その分析にあたって、「参加」に偏向したり、あるいは現象学的側面に終始することでミニマリズム彫刻とカバコフ作品とを区別できなくなったりしないよう、ペーターセンは4つの並列した側面を指摘します。
- 美的に組織された空間(aesthetically organised space)
- 空間性(spatiality)
- 演劇性(theatricality)
- フィクション的空間(fictional space)
以下それぞれを説明します。
(1.)「美的に組織された空間」は、個々のオブジェクトの配置や選択によって境界づけられた空間、といえるでしょう。かならずしも壁などで囲まれている必要はなく、ともかく物によってインスタレーションを茫漠としないひとまとまりのものとさせている構造です。
たとえばペーターセンが例に挙げるヴィト・アコンチ《Instant House》(1980) は、宙吊りのブランコに鑑賞者が座ると、重みが滑車越しに伝わり、床に広がっている、アメリカ国旗が描かれた4枚の板が立ち上がります。板は立ち上がると鑑賞者を囲む小屋のようになります。床に伏せられていた面がいまや小屋の壁になり、そこにはソビエト連邦の旗が描かれています。この作品は、インタラクティブにキネティックであるため、彫像のように明確に物理的界面は示せませんが、きまった「空間的構造」は成り立っているでしょう。
は、宙吊りのブランコに鑑賞者が座ると、重みが滑車越しに伝わり、床に広がっている、アメリカ国旗が描かれた4枚の板が立ち上がります。板は立ち上がると鑑賞者を囲む小屋のようになります。床に伏せられていた面がいまや小屋の壁になり、そこにはソビエト連邦の旗が描かれています。この作品は、インタラクティブにキネティックであるため、彫像のように明確に物理的界面は示せませんが、きまった「空間的構造」は成り立っているでしょう。
(2.)「空間性」は、第3章でも触れましたが、オットー・フリードリヒ・ボルノウによる現象学的な概念です。人間が空間を理解するとき、日常的で主体的な経験にもとづいています8。
行為するために空間を理解するというモデルは、ほかにもアフォーダンスで知られるJ.J.ギブソンの生態学的視覚論や、もしくはポール・ロダウェイの触覚論にも結びつきます。ギブソンは空間における行動のための能動的な探索ツールとして視覚を位置づけ、ロダウェイも同様に触覚の「届く」だけでなく「想像的な」側面があることを指摘しました。
ペーターセンはこうした「利用のポテンシャル」がインスタレーションの空間にも読み取られ、また活用されていることを指摘します。たとえば先の《Instant House》でいえば、ブランコに座れるという認知、それが降りて空間が狭くなるということへの理解や予見……といったものでしょう。
(3.)「演劇性」は、そこでの経験が、現実にたいしてもつ関係を指します。たとえば現実、日常生活は②の意味で利用のポテンシャルを向けられていますが、インスタレーションは「芸術」である以上、それだけではないはずです。つまり、純粋なものの、時に直接用いるように行為できる「現前」だけでなく、組織された「表象」の側面もあるはずです。その極端なものに、既存の空間を模倣する・引用する「レディメイドの空間化」(ブクロー)があるでしょう。
つまり現象学的な「空間性」とパフォーマティヴな「演劇性」とは、提示と表象にあたる、インスタレーション空間の対照的な側面です。インスタレーションはたしかに彫刻や絵画に比べて前者を引き出しながらも、後者についても特有の表現を形成します。それであってそれでない、バイルの作品でいえば病院のようで病院でないという「感覚的な疎外」があり、そこで病院は、現象学的に病院空間であると同時に、価値や規範、社会構造などを表象する表現でもあります。
少々長いですが、ペーターセンの記述を引用します。
インスタレーション・アートの提示的な側面を強調するというのはつまり、わたしたちの日常にもとづいた、そのなかを歩き回るような屋内環境と同じような現象学的なものを重視するということだ。日常生活を組織づける原則に構造的に似ていることで、インスタレーションは、わたしたちが生きている歴史的な時間やその問題、欲求、それにかかわる認知的な道具としてあるようなポテンシャルをもつ。インスタレーションはしばしば、非常に具体的に空間的な感覚において、現実に結びついており、そこでは鑑賞者のパーソナルな空間が、美的に組織づけられた空間へと統合しているのだが、この空間は、日常的なオブジェクトや素材、構造を内側に含んでいることもありうる。わたしが特に論じたいのは、このような日常的なものの使用・構造的類似によって、インスタレーションは、意味論的なレベルでも、その周りにある社会や世界にたいして開かれているということだ。日常的な空間とインスタレーションとを取り違えるような人はほとんどいない。それこそ、上述したような異化効果の証明であるのみならず、インスタレーションというものの演劇性である。この演劇的側面はまず、その空間が、鑑賞者が入り込める場面として演出(arrange)されていることにもとづく。つまり、空間を舞台化するのだ(it stages the space)。また、芸術家が、その作品はある状況の中のオブジェクトである、という意識をもって構築するとき、ほとんど定義からして、作品は鑑賞者の存在を含んでいる。マイケル・フリードが『舞台のような現前』と呼んだものを、インスタレーションは持つ。演劇やパフォーマンスに似て、インスタレーションは鑑賞者のために舞台となっている。〔…〕このように、インスタレーション・アートは必ず、馴染み深い日常のものと、異化された人工的なものとのあいだに作り上げられた、緊張ありきの芸術形式となる。(ペーターセン)
(4.)「フィクション的空間」もまた、意味論的な側面を指します。しかし舞台化した空間である「演劇性」とは異なり、「フィクション的空間」は、インスタレーションの諸要素のあいだに読み取られる物語のようなものを指します。
これもまた、ペーターセンの記述を引きます。
言い換えれば、フィクション的空間とは、受容されたフィクション、解読された表象、意味の構造の総計であり、鑑賞者がそれらをどう解釈するか、芸術家が規定したものだ。〔とはいえ〕フィクション的空間は、意味が安定した、事前に定められた核心そのものではない。それは個人ごと、タイミングごとに異なる。フィクション的な空間は作品と鑑賞者との出会いのなかで作られる。その出会いこそが、インスタレーションの演劇的な特質によってその〔フィクションの〕特殊な特質を受容されるのだ。(ペーターセン)
現象学的つまり身体的・認知的な空間性〔②〕が、参加しうる演劇性=舞台〔③〕と共存し、そうした参加は、さらにより抽象的なフィクション的空間〔④〕を呼び込む、というプロセス9です。これがひとつの美的なまとまり〔①〕として組織されている。この空間の組み合わさりをこそ、ペーターセンがインスタレーションの特徴とみなします。
インスタレーションという表現形式の特徴・重要な性質とは明らかに、このフィクション的で意味論的な平面〔④〕と、さきほど空間性という概念を通じて捉えようとした、物理的な平面〔②〕との組み合わせだ。インスタレーション・アートは、美的な手段を通じて、身体的なものと言説的なものを混ぜ合わせる。(ペーターセン)
ペーターセンは、この「フィクション的空間」こそ、ミニマリズム彫刻とインスタレーションを区別する点だと指摘します。ミニマリズム彫刻は、美的組織や空間性、そして、まさにフリードが批判したように演劇性を備えていますが、フィクション的空間はほとんどありません。カフェやスタジアム、ショッピングモールにも同様に言えるでしょう。対してインスタレーションは、物語的・意味的なポテンシャルを利用しています。
このようにインスタレーションには、提示と表象が空間的な意味で同居し、それを演劇的な参加が媒介する性質をもつといえるでしょう。この段階的プロセスをペーターセンは解釈の「遅延(delay)」10と指摘します。インスタレーションはしばしば複数のメディウムを含むため、それをフィクション的空間へとまとめあげるには、それら異なる表象システムがインタラクトするプロセスが必要です。
つまり、インスタレーションは複数の意味での空間が、プロセス的に連携するよう「形づくられた(shaped)」ものと言えるでしょう11。
ここまでの例で示したように、インスタレーションは、鑑賞者=パフォーマーの現実空間が作品の空間に混ざり合うような、美的に設えられた物理的な空間――あるいは、わたしがインスタレーションの形づくられた空間と呼んだ、4つの側面をもつ空間として示したものとして、組織されている。その4つの側面とは、〔上述の通り〕美的に組織された空間、空間性、演劇性、フィクション的空間である。これらが一つにまとまることで、新たな空間が現われるように見える。芸術作品と現実とのあいだの線引きが曖昧になるような類のハイブリッドな空間であり、そこでは鑑賞者=主体と作品=客体もまた混ざり合う。とはいえ、作品の空間と鑑賞者の現実空間との組み合わせは、イリュージョンにすぎない。たとえ感覚的に説得力があっても、それはイリュージョンである。(ペーターセン)
イェンス・トフトを参照しながら、このイリュージョンのイメージを作る輪郭を、「ヴァーチャルなフレーム(virtual frame)」とペーターセンは呼びます。作品の輪郭が必ずしも絵画の額縁のように明白でない、近現代芸術において、作品の存在論的なありかたを再考する概念です。インスタレーションという作品は、ある閉じた作品として存在している。
あらゆるインスタレーションにおいてフレーム――ヴァーチャルなフレームは存在するが、それは物理的な観点から位置づけられるものではない。にもかかわらずそれは、受容において構造的な要素として『存在する』。(ペーターセン)
第6章 時間的な状況としてのインスタレーション(Installation as temporal situation)

Ilya Kabakov, The Boat of My Life, 1993, Ilya & Emilia Kabakov
本章はインスタレーションの「時間」について検討します。前章で「空間」が複数のプロセス的なものに分析されたのに対し、本章での「時間」も似た構造をもちます。
たとえば「空間」については、表象されるフィクション的な空間と、提示される現象学的空間やそれに関わる演劇性がありましたが、時間についても、何かの形で表象される時間と、それを鑑賞者が受容している時間、という別種の時間があります。それぞれを、ゴットフリート・ベーム『イメージと時間』(1987)を参照して、「描かれたものの時間(the time of the depicted)」「受容の時間(the time of reception)」とペーターセンは整理します12。むろん後者なしに前者は鑑賞されないのであり、これはペーターセンが「遅延」と呼んだ、空間の受容のプロセスと同様です。
インスタレーションの空間的な組織化は、表象された時間がどのように受容され、解釈されるかにとって重要である。(ペーターセン)
たとえば小説において、直線的な受容の時間にたいして、表象される時間は、シーンの入れ替えや速度などが様々であるように、インスタレーションにおいても、これらの関係は重要になります。ペーターセンはカバコフの《The Man Who Never Threw Anything Away》(1985-1988) や《The Boat of my Life》(1993)
や《The Boat of my Life》(1993) を例に挙げて、その部屋やボート型のインスタレーションに見受けられる物語的内容の受容が、順序も決まっておらず、また「飛ばし読み」するかのようであることを指摘します。つまり「表象される時間」だけでなく、「受容の時間」もまた、必ずしも実際に物理的に流れる時間のように一直線ではありません。ダグ・エイケン《i am in you》(2000)
を例に挙げて、その部屋やボート型のインスタレーションに見受けられる物語的内容の受容が、順序も決まっておらず、また「飛ばし読み」するかのようであることを指摘します。つまり「表象される時間」だけでなく、「受容の時間」もまた、必ずしも実際に物理的に流れる時間のように一直線ではありません。ダグ・エイケン《i am in you》(2000) のようにヴィデオを用いたインスタレーションでは、時間の構造は容易にさらに複雑になります。
のようにヴィデオを用いたインスタレーションでは、時間の構造は容易にさらに複雑になります。
前章で「空間」を明確に分割したようには、インスタレーションの「時間」的デザインは共通分母をもたない、とペーターセンは指摘し、3つの「典型的特徴」を考察します。
- 一時的インスタレーション(temporary installation)
- 時間モデルとしてのインスタレーション(installation as a time model)
- 物語的インスタレーション(narrative installation)
以下それぞれを説明します。
(1.)「一時的インスタレーション」は、非永続的(non-permanent)と呼んでもいいでしょう。
これは1960年代・1970年代の、反市場・反美術館的な制度批判性をもつ実践に由来します。会期中に溶けてなくなる氷を展示したラファエル・フェラー《Ice》(1969)をはじめ、プロセス・アートやインスタレーションは、収蔵や流通に向かない非永続性をもっていました13。その点で作品がオブジェクトというよりパフォーマンスに近づいたことをペーターセンは指摘します。
永続的で移動可能な物質であることを避けるラディカリズムは、ゴードン・マッタ=クラークのインスタレーションにも表れています。家を切断した《Splitting》(1974)は、ミニマリズム的な関心があると同時に、プロセス自体が作品と化している例です。家の切断だけでなく、その断片がギャラリーに置かれたり、写真ドキュメンテーションになるほかない、という不可逆な変容のプロセスが、マッタ=クラーク作品における時間の問題として表れています。
1970年代を過ぎると、一時性の政治的・反制度的含意は薄くなり、それ自体で哲学的なコンセプトとしても用いられます。たとえばフェラー同様氷を素材にとったクリステン・ジュステセン《Meltingtime》 は、インスタレーションやパフォーマンスをとることで、氷の非永続性をモチーフにした思索的作品です。
は、インスタレーションやパフォーマンスをとることで、氷の非永続性をモチーフにした思索的作品です。
(2.)「時間モデルとしてのインスタレーション」は、ペーターセンは明確に定義づけておらず、ややわかりづらいです。
ハンネ・ダーヴォーベンのカレンダーを用いた作品や、吊られた電球が時間をモチーフにした様々なインタラクションや運動、点滅をするソービョーン・ラウステンの作品が挙がっています。その点では、時間自体を主題に置き、その構成が時間の流れや実質、文化自体を表象するようになっている作品と考えるとよいでしょう。ただその点では①に挙がる作品もその性格を拭いきれないので、あくまでカテゴリというより特徴・タイプとして捉えるべきでしょう。
ペーターセンの挙げる例ではありませんが、たとえば野村仁《遅延論》(1968-1969)やクリスチャン・マークレー《The Clock》(2010) などが、このタイプにあたると思います。
などが、このタイプにあたると思います。
(3.)「物語的インスタレーション」もまた明確な定義づけはありませんが、文字通りの(文学的な)リアリスティックな物語に限らない、配置された要素から鑑賞者が内容を構築するデザインをもちいたインスタレーションを広く指す、と言えます。
先に挙げたカバコフ作品のように、必ずしも起承転結のような流れのない、一人の人間の人生を断片的に示したものも「物語的」と言える14し、あるいはペーターセンが挙げる、フィン・ラインボート《Between Before and After》は、「ON AIR」と「THE END」と書かれたガラス板や木の板が映画のコマのように並んだインスタレーションで、物語的な内容はなく、空虚な流れとその認知だけあるものです。
ペーターセンがポール・リクール『時間と物語』から紹介する、物語こそが、人間が経験する時間を把握する構造・行為だ、という観点が、インスタレーションに活用されたものといえます。これは第5章の「空間」でいえば、「演劇性」にあたるでしょう。15
美術史家マリアンヌ・トルプが論じたように、フィン・ラインボートは、このような『鑑賞者の反省』――見えるものがその全体にまたがる論理に導かれた物語のパターンにぴったりはまっていく文脈を構成して、そこに意味ある秩序(meaningful order)16を作り出そうとするこの欲望をわざと刺激しているのだ。つまりラインボートにとって、話の意味や内容は中心的ではない。むしろ認知のプロセスそのものが重要なのだ。それはすなわち、ばらばらの手がかりをもとに物語を作り出して、そうして『時間のなかで拡がったり抑え込んだりする』ようなものだ。〔…〕ラインボート《Between Before and After》のインスタレーション全体において、表象された時間は、独立して存在するなにかではない。それは鑑賞者の受容が生み出すものであり、その受容の時間に依存したものだ。それはつねに、知覚的で主体的な時間であり、その流れは、その空間内部での鑑賞者の位置の継続的な変化によって決まる。(ペーターセン)
このように、演劇性と物語性は、インスタレーションのパフォーマティヴな側面の、それぞれ空間的・時間的な形式ととらえてよいでしょう。
マリー=ロール・ライアンを参照して、ペーターセンはインスタレーションにおける物語性を、言語・語り手を前提としたディエゲーシスよりも、舞台芸術や映画のミメーシスに関わると考えます。また加えて、映画と異なり鑑賞者の能動的参加をもつ点では、ヴィデオゲームのようなインタラクティヴなデジタルメディアとの関連を指摘します。これは第12章でもまた触れられます。
とはいえ、前章で、異なるメディア同士の空間的並置がインスタレーションの特徴とした以上は、ミメーシス的な表象システムに、ディエゲーシス的な表象システムが伴うこともあるはずです。たとえば映像インスタレーションや、リサーチにもとづくインスタレーションなどは、その傾向が強いでしょう。ペーターセン自身「映画のナレーション」はディエゲーシス的だと注記するあたり、そうした並置をインスタレーションにも見いだせるはずです。
第7章 インスタレーション――イメージと舞台のあいだ(Installation Between Image and Stage)

Robert Morris, Site, 1964. Performance view, Stage 73, Surplus Dance Theater, New York, February 1964. Carolee Schneemann and Robert Morris. Photo: Hans Namuth from Artforum
本章は本書でもっとも長く、章題を見ても、テーマ的な重要性の高い章です。とはいえ構成が冗長でばらけているため、この要約では切り詰めてまとめます。
第4章で見たように、パフォーマンスの言説はインスタレーションの言説と同時期に発展しました。同様に、1940年代・1950年代からすでに実践面でも多くの作家が関わっています。、カプローやオルデンバーグ、ダインらはエンヴァイロンメントとハプニングを並行して行ない、またモリス、キャロリー・シュニーマン、草間彌生、レベッカ・ホーン、ブルース・ナウマン、ヴィト・アコンチ、ヨーゼフ・ボイスらも、パフォーマンスやボディ・アートに取り組んでいました。さらにヨーロッパではフルクサスやベン・ヴォーチエ、イヴ・クライン、シチュアシオニストが、またニューヨークではブラック・マウンテン・カレッジを中心に、ジョン・ケージやラウシェンバーグ、マース・カニンガムらのメディア実験的な活動が見られます。
一例としてペーターセンはケージによる《Untitled Event》(1952) やカプロー《18 Happenings in 6 Parts》(1959)
やカプロー《18 Happenings in 6 Parts》(1959) を紹介します。さらに、後にフリードに「擬人主義的」と批判されるような性格を早くからもっていた、モリスの初期の作品《Column》(1961)、さらにはシュニーマンやイヴォンヌ・レイナーとのモリスの協働に触れ、ミニマリズム彫刻とパフォーマンス、また著述活動で幅広く活動したモリスこそが、この時代の動向の中心的人物だったと指摘しています。
を紹介します。さらに、後にフリードに「擬人主義的」と批判されるような性格を早くからもっていた、モリスの初期の作品《Column》(1961)、さらにはシュニーマンやイヴォンヌ・レイナーとのモリスの協働に触れ、ミニマリズム彫刻とパフォーマンス、また著述活動で幅広く活動したモリスこそが、この時代の動向の中心的人物だったと指摘しています。
視覚芸術や音楽、ダンス、演劇、先進メディアなどのクロスオーバー・合流が、パフォーマティヴでプロセス志向の芸術を生み、その確立のプラットフォームのひとつがインスタレーションだった、と言えます17。
ただし、「パフォーマティヴ(ィティ)」と「演劇性」とは、必ずしも同義語ではありません。いずれも制作や受容におけるプロセスが重視されていますが、第4章で見たとおり、前者のほうが広く用いられる一種の人類学的に概念です。たいして後者は狭く、芸術作品の性格を指す語です。
さて、芸術において「パフォーマティヴ」概念は、時間・状況・プロセス・身体などの導入された実践を広く促しました。従来の視覚芸術は、作品に鑑賞者が出会う状況、作品の中にあるプロセスが強調されるという点でより演劇に近づいたといえます。こうした点は、それまでの、デカルトの心身二元論やカント的なモダニズムにもとづく芸術理論とは対照的といえます。もはや対象は主体には完全にコントロールされず、むしろ主体に対して「何かをなす」ものです。
たいして「演劇性」概念は、第5章でも見たように、より受容の側面に限定して本書では用いられます。
さて、第5章・第6章で見たように、インスタレーションでは鑑賞者による美的な受容が、複数の空間・時間を織り合わせるプロセスを発動させています。そのプロセスでは、現象学的な「空間性」や、現実の時間が、表象・物語と結びつく、といえるでしょう。
現実とかかわる、現実的だという点でこれは「リアリズム」です。もちろん、ここまで見たように、それは従来の写実・ミメーシス的な、何かを模倣して見せるようなリアリズムではありません。インスタレーションにおけるリアリズムとは、鑑賞者の行為を通じて、現実と表象の関わりが生成される、「パフォーマティヴなリアリズム(performative realism)」です。
そのような行為には、インスタレーションのなかを歩き回る・知覚するだけでなく、それを反省したり、あるいは参加やインタラクションするものもあります。必ずしも意識的・自発的に行われず、動いていたら・見ていたらいつしか行っていたような非自発的(involuntary)行為も含まれるでしょう18。また実際にインタラクションを起こさなくても、想像のなかだけでする行為も、そうしたリアリズムに寄与します。その点では、ただ「観ながら立っている(standing while viewing)」ことも、インスタレーションの中では、意味の生成に貢献する行為なのです。
第5章の議論を繰り返せば、「演劇性」とは、そうしたプロセスにおいて、日常・空間性(利用・運動)とフィクション的空間(表象・意味)とを重ね合わせる、「舞台化=上演(staging)」するように形づくられた性格自体を指すでしょう。パフォーマティヴなリアリズムは演劇性を利用しているのです。
間メディア・身体への志向、そして日常との結びつきのために、鑑賞者の身体経験が強調され、そこではジェンダーやアイデンティティ・ポリティクスが前面に出てきます(アメリア・ジョーンズの分析)。
インスタレーションの歴史の重要な点のひとつに、絵画・彫刻・写真など歴史的に男性に支配されてきた伝統領域とは対照的に、女性作家と男性作家がジャンルの展開において等しいシェアを占めていたことが挙げられる。とはいえこの展開の歴史は、絵画・彫刻・写真よりもいっそう、インスタレーションをより『ジェンダー』や『アイデンティティ・ポリティクス』にもとづいたジャンルとした。個々の作家における表現形式の利用や、特定の展示のテーマ的枠組み、所与のインスタレーションの鑑賞者の受容においてこそ、ジェンダーのコードやアイデンティティ・ポリティクスの政治への参照が発生する。(ペーターセン)
とはいえ冒頭に述べたとおり、ペーターセンは必ずしもジャンルや言説の一辺倒な「政治化」「社会化」を支持しません。以上の特徴はペーターセンにとっては、あくまで現象学・受容美学的に身体が経験に協働するという観点から歴史的に派生したものでしょう。
そして必ずしも、アメリア・ジョーンズの系譜が示すようには、〔インスタレーションの経験は〕ジェンダーやアイデンティティの問題に強くコミットするわけではない。(ペーターセン)
あくまで「演劇性」という形式的特徴こそが本書での焦点です。
鑑賞者の身体感覚から発して、フィクション的空間の創造に貢献する「演劇性」は、つまりその両者(作品と鑑賞者、象徴と行為)を浸透可能にする、一種の「弁証法的」なものといえるでしょう。
このプロセス的性格を踏まえて、ジョゼット・フェラルは「演劇化(theatricalisation)」と動詞で捉えています。日常的な空間が、行為をとおして新たに意味づけられるそれは、フェラルにとっては、芸術に限らず人間のふるまいにとって根本的なものです。
このプロセスは世界についての観点を変え、日常の空間におけるそれは異なったしかたで空間が意味づけられる。フェラルによれば、観点の切り替えは、意図の純粋な行為によって引き出されるのではない。そのため、フェラルにおける演劇性の概念は、自発的なものではない。それは、鑑賞者がその何かにとりかかるまえにすでに約束されたものにもとづいており、そこには、表象――パフォーマンス、出来事、作品――を作り出そうという意図をもったアクターがあるのだ。鑑賞者の視線はこれにとりかかり、そうして、日常空間とは意味論的な意味で異なる、他者性の空間、フィクション的な空間を作り出す。演劇性とはこの意味で、視線がおこなう何かであり、鑑賞者によるパフォーマティヴな行為なのだ。(ペーターセン)
改めて概括すれば、このようにインスタレーションにおいては、二つの空間を、鑑賞者のパフォーマティヴィティが結びつけます。それは空間の側からすれば「舞台化する」ともいえます。そのプロセスを経て、インスタレーション作品の「ヴァーチャルなフレーム」が成立するのです。
第8章 パフォーマンス演劇――舞台とイメージのあいだ(Performance theatre between stage and image)
本章はタイトルのとおり、パフォーマンスの側から、前章で見たような、メディア・実践をまたいだ動向を捉えていきます。とはいえ重要な概念づけは少なく、具体的な名前に終始する内容なので、ごく簡潔にまとめます。
20世紀前半から1970年代にかけて、視覚芸術がメディアやパフォーマンスの発展から影響を受けて変化したように、演劇・パフォーマンスもまた同時代に大きな変化を迎えます。たとえばアルトー、アッピア、クレイグらのアヴァンギャルドな実践、アメリカの大衆演劇・エンターテインメント、またイザドラ・ダンカンやマーサ・グラハム、ドリス・ハンフリーなどモダンダンスの展開が挙げられます。マーヴィン・カールソンはこれを大局的に、テクストからパフォーマーへ、制作からプロセスへの変化と捉えています。
ペーターセンは、ギヨーム・アポリネールの前衛的な演劇《ティレジアスの乳房》(1917)や、モリス経由でミニマリズムの影響を受けていたイヴォンヌ・レイナーの『The Mind is a Muscle』(1966)を紹介します。本章後半では、視覚・イメージを重視したロバート・ウィルソン や、デンマークのパフォーマンス・コレクティヴ「Hotel Pro Forma」
や、デンマークのパフォーマンス・コレクティヴ「Hotel Pro Forma」 が詳しく紹介されます。
が詳しく紹介されます。
第9章 ヴィデオ・インスタレーション――ナヴィゲーション・没入・インタラクション(Navigation, immersion and interaction in video installation)
この章ではタイトルのとおり、ヴィデオ・インスタレーションを取り上げます。
1970年代のヴィデオ・アートだけでなく、1950年代にアメリカ、1960年代にヨーロッパで普及したテレヴィジョン、他にも広く電子テクノロジー、さらにナム・ジュン・パイクらフルクサスの活動などをペーターセンは概観します。
ペーターセンは、ナウマン《Live-Taped Video Corridor》(1969-1970) 19やラファエル・ロザノ=ヘマー《Body Movies. Relational Architecture 6》(2001)
19やラファエル・ロザノ=ヘマー《Body Movies. Relational Architecture 6》(2001) 、モナ・ハトゥム《Corps étranger》(1994)
、モナ・ハトゥム《Corps étranger》(1994) 、また本書表紙にもなっているピピロッティ・リスト《Dawn Hours in the Neighbour’s House》(2004-2005)
、また本書表紙にもなっているピピロッティ・リスト《Dawn Hours in the Neighbour’s House》(2004-2005) などを例に、ヴィデオ・インスタレーションにおいて鑑賞者の身体が時空間に結び付けられることを紹介します。
などを例に、ヴィデオ・インスタレーションにおいて鑑賞者の身体が時空間に結び付けられることを紹介します。
中継や録画、さらにはパノラマ、クロースアップ、モンタージュ、プレイバックやマルチスクリーンといった映像技術による時空間の編集とその演劇的経験は、複雑でこそあれ、第5章・第6章で見たモデルの延長で分析できるでしょう。その点では、相変わらずモダニズム的自律概念への挑戦・解体、ないし「身体的転回(physical turn)」があることは明白です。視覚に中心を置かず多感覚的・パフォーマティヴに反省される身体をペーターセンは「ポストヒューマン」と形容します。
エルウェスも強調するように、そこで鑑賞者は、三次元空間とさえも混ざりあった映像イメージへ強く巻き込まれると同時に、モニターやプレイヤーなどの映像装置自体がインスタレーションのなかで見えていることで、距離がとられもします。まとめると、以下のように言えるでしょう。
シングルチャンネルヴィデオに比べて、ヴィデオインスタレーションは、空間的な拡張、時間的な複雑性と絵画的な同時性、分散、そしてさらには断片化によって特徴づけられる。(ペーターセン)
現代の、あらゆるデータがメディアごとに変容可能性をもつという状況におけるイメージのありかたを指す「デジタル・イメージ」(マーク・ハンセン)という呼び方を引きながら、ペーターセンは、イメージが物理的なフレームありきのオブジェクト志向のものから、身体に媒介された感覚的・認知的プロセスを含みこんで生産されるものになっている、と整理します。
そのようなヴィデオ・インスタレーションの受容を、ペーターセンは①視覚中心性20、②ナヴィゲーション、③没入、④インタラクションに区別します。
ナヴィゲーションとは、鑑賞者がそこで動き回ることです。没入とインタラクションは、かたや受動、かたや能動という、受容のありかたのもつ二つの極といえます。ペーターセンは、1960年代以降後者が政治的に重視されていると紹介しながら、あくまでこの二者は価値づけのカテゴリーではなく、記述的なものだと釘を差します。ここにも、「参加=アクティベーション=政治的」という安易な構図を再三避けていることがわかるでしょう。
またペーターセンは上の4つに加えて、退屈や注意散漫状態つまり⑤「心ここにあらず(absent-mindedness)」を加えます。
こうした特徴は、ヴィデオ・インスタレーションに特有というより、多くのイメージとデジタル技術を用いるからこそ強調されている程度の話で、インスタレーション一般の分析に使えるものでしょう。
それを踏まえると、ヴィデオ・インスタレーションにかんして「没入/インタラクション」の対照性を表立たせたのは、ペーターセンの批評的なねらいが窺えます。
没入とインタラクションとの対照性は、ビショップにおいてはイデオロギー的な対照になります。鑑賞者による身体的気づきや自己反省こそアクティベーションである、とビショップ『ある批評史』は重視します。それは第4章や結論に見られる、「参加」概念に政治性を読み込んだイデオロギーでしょう。しかしヴィデオ・インスタレーションは「脱差異化」を招くという点で、ビショップはその受動性を「嫌悪」しているとペーターセンは述べます。
しかしペーターセンによれば、それはアクティベーションにたいする狭量な視点であり、より一般的にパフォーマティヴィティ・演劇性は、反省・気づきの有無にかかわらずアクティベーションであると主張します。ヴィデオ・インスタレーションの受容は、ペーターセンが上に列記したように広いタイプをもるのです。
第10章 場=サイトと文脈(Site and Context)
本章が、実質的には本書で最後の、重要な形式分析的をもつ章にあたります。
本章のテーマは「場=サイト(site)」ないし「サイト・スペシフィシティ(site-specifity)」です。第5章では「空間」を、インスタレーションに内在し、鑑賞者の演劇性によって媒介・駆動するプロセス構造として扱っていましたが、ここでは作品に外在し、同様に演劇性によって、第7章で扱ったような「パフォーマティヴなリアリズム」として結びつく現実の側の特異性として、「場=サイト」が議題に上がる、と整理できるでしょう。つまりインスタレーション作品は、それ自体が意味をもつような「場」を既存の「ロケーション」のなかで作り、ダイナミックに・弁証法的に結びつくのです。これは、第3章で触れたベンジャミンも扱っていた問題です。
場と文脈が、作品の構成に影響する。これはサイト・スペシフィックなプロジェクトの基礎にある考え方です。ペーターセンはこのような世界と作品の関係について、「レディメイド21」もまた同じ原則で導かれていることを指摘します。
1960年代以降、サイト・スペシフィックで文脈主義的な作品が増加し、インスタレーションにも影響したことをペーターセンは改めて確認します。
ここでのサイト・スペシフィティの系統学的分類は、ペーターセン独自のものではなく、ミウォン・クウォン『One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity』(2002)で提案されたものです。
- 現象学的・経験的
- 社会的・制度的
- 言説的
これらは、進化的な関係にはありませんが、おおよそ時系列的に並んでいます。それぞれを説明します。
(1.)「現象学的・経験的」なサイト・スペシフィティのパラダイムは、1960年代・1970年代の、モダニズム彫刻への反動に由来します。
いわば移動可能・ノマド的となった「サイトレス(site-less)」なモダニズム彫刻にたいし、それが置かれたロケーションが現象学的・経験的に理解されるよう特徴づけるアプローチです。その点では、ミニマリズム彫刻にも関わる「現象学的転回」の動向どいえるでしょう。
ペーターセンは、リチャード・セラの作品や、当時スミッソンが多く書いた「サイト」についてのエッセイに触れ、とくに後者の「ノンサイト」概念が、サイト・スペシフィックな作品の写真が展示されるという点で、芸術の言語的なシステム・制度を主題とすることを強調します。この点が次のパラダイムに続きます。
(2.)「社会的・制度的」なパラダイムは、コンセプチュアル・アートや制度批評の延長にあります。
つまり、いかなるロケーションもサイトも、政治的・文化的に「無垢」ではない。本章冒頭や第3章ではオドハティのホワイトキューブ論が引かれますが、美術館・ギャラリーというロケーションがもつ政治的性格への注目・抵抗が、1960年代・1970年代に広く共有されていたことは、インスタレーション史において重要なトピックです。
ペーターセンは、この種のサイト・スペシフィシティを用いた作家に、マイケル・アッシャー22、ダニエル・ビュレン、ハンス・ハーケ、ロバート・スミッソン、ミエレル・レーダーマン・ユケレスを挙げます。
そのため、(1.)現象学的なサイト・スペシフィシティにおける身体もまた、受容にたいする批評的要素として賦活され、鑑賞者の階級・人種・ジェンダー・セクシュアリティなどを反照します。
このように、ロケーションにせよ身体にせよ、そこで扱われるスペシフィシティとして、非物質的な、言説に構造づけられたものが強調されます。この点が次のパラダイムに続きます。
(3.)「言説的」なパラダイムとして、1990年代以降のサイト・スペシフィシティを特徴づけられるでしょう。
ここでの「場」はもはや現象学的・身体的な場でも、政治性を負った特定のロケーションでもなく、「言説的に決まった場(discursively determined site)」です。芸術制度の外や日常生活さえも、あまねく言説に左右される「場」――いわばコンセプトそのものです。
このようなサイト・スペシフィシティのある種の全般化は、作品・作家のありかたとも関わります。サイト・スペシフィックな特定の場からは引き離され、同じコンセプトにもとづいてさまざまな場、展示の招聘においてヴァリエーションが作られることになります。その点で、結局作家は、分散・分岐した複数のプロジェクトをまとめあげる「語り手」の権威を再獲得するといえます。このプロジェクトの分岐構造こそが「場」を左右するのです。
場=サイトは、非常に広い文化的・社会的・言説的な場を横切って散らばっており、作家によるノマド的な移動――地図というより〈旅程表〉のような――を通じて、相互に文脈づくよう組織だてられたものとなる。それは、広告看板や、芸術ジャンル、公民権を奪われたコミュニティ、制度的枠組み、とある雑誌のページ、社会的な因果関係、政治的議論など、さまざまなものでありうる。それは〔たとえば〕街角のように文字どおり(literal)の意味の〈場所〉でも、理論的概念のようにヴァーチャルな〈場〉でもありうる。(クウォン)
ペーターセンはこれを「ネットワーク化したサイト・スペシフィシティ(networked site-speficity)」と言い換えます。
これら〔ネットワーク化したサイト・スペシフィティという〕新たなプロジェクトの多くを特徴づけているのは、作家によって主導される行為とプロセス、物理的なロケーション、オブジェクト、テクスト、写真、動画記録等々すべてが、異質性をもったひとつのプロジェクトに結びついていることだ。そのプロジェクトは、多くの異なるサイト――ウェブサイトという、オンラインのコンピューターと携帯電話さえあればどこからでもアクセスできる点で〈サイト・アンスペシフィック〉なサイトも含む――と関係し、またインパクトをもつ。ネットワーク化したサイト・スペシフィシティは、異なるロケーション、そしてその間で動く主体たちのあいだにある、言説的で制度的な関係を――特にアーティストが、プロジェクトの主要な語り手に座することで――作り出す。かくして、このタイプのプロジェクト、あるいは知識の生産といった、このしかたによって帰結するものは、意味と行為の連鎖あるいはネットワークとして現われる。このプロジェクトは根本的にプロセスにもとづいており、いかなる特定の焦点もない。その『場=サイト(the site)』とは、空間のなかの安定した一点として在るのではないし、作品の単一・永遠の参照先でもない。『場=サイト』は、発生する運動に比される。『場=サイト』は機能的なものだ。『場=サイト』は、関係を作り出す『機械』である。この関係に、プロジェクトの各段階の概念的な一貫性がもとづくような相互関係が含まれるのだ。(ペーターセン)
このような「ネットワーク化」という形容が、インターネットの登場を参照していることは言うまでもありません23。
ネットワーク化したサイト・スペシフィシティの例として、ペーターセンはスーパーフレックスの、バイオガスをモチーフにした一連のインスタレーションのシリーズ《Biogas in Africa》などを紹介します。
〔…そのような〕作家の精神性が照らし出すような〈場との関係〉とは、ローカル性のもつ物理的な特徴を解釈するようなサイト・スペシフィシティによって確立したのではない。対照的に、そのローカル性へと多かれ少なかれ結びついた、複数でしばしば散在した意味のレイヤーが、ネットワーク化した構造のなかで相互に覆ったり貫いたりするようにするタイプの、最近現われたサイト・スペシフィシックなインスタレーションによって作られる関係である。(ペーターセン)
とくにそうしたプロジェクトが、場を「取り上げる」どころか「拡張する」、場自体が何になるかを方向づける例として、トマス・ヒルシュホルンの《Bataille Monument》(2002) 24をペーターセンは挙げます。作品の内容やポテンシャルを詳述し、同作が、特定のローカル性の外見や歴史を示すのではなく、別の場で実現するような、意味のレイヤーの付加をなしていることを指摘します。それは「場所-出来事(place event)」(ニック・ケイ)であり、1960年代にカプローに取り組まれた、参加者のためのインスタレーションやハプニングの延長にあたる、とペーターセンは述べます。参加者は、不連続的な空間――とくに、芸術と日常――をまたいで作品を探ることで、その作品の構造はパフォームします。
24をペーターセンは挙げます。作品の内容やポテンシャルを詳述し、同作が、特定のローカル性の外見や歴史を示すのではなく、別の場で実現するような、意味のレイヤーの付加をなしていることを指摘します。それは「場所-出来事(place event)」(ニック・ケイ)であり、1960年代にカプローに取り組まれた、参加者のためのインスタレーションやハプニングの延長にあたる、とペーターセンは述べます。参加者は、不連続的な空間――とくに、芸術と日常――をまたいで作品を探ることで、その作品の構造はパフォームします。
こうした、ローカル性・文脈と作品の関係が、表象にとどまらず社会的存在そのものに溶解しているようなプロジェクトにおいては、インスタレーションはそのネットワークの「一部」、社会的関わりの手段になっています。
第11章 結論:芸術と文化の境界で(Conclusion: On the threshold between art and culture)
本章の大部分は各章のまとめなので、それは割愛します。ペーターセンは、インスタレーションが、第二次大戦以降のアヴァンギャルドとして、「作品を世界に開く」「視覚芸術を他の形式に開く」という2つの意味で「開かれた」実践だとまとめます。後者については、クラウスの「ポストメディウム的条件」も参照されます。また、解釈多様性やそのプロセス、作家によるコントロールの縮小という点では、ウンベルト・エーコの「開かれた作品」概念にも結びつけられます。
インスタレーションは独立した形式・構造というより、戦間期の「モンタージュ」と似た機能・広がりをもつ、という指摘は膝を打たせます。複雑性や異質性、曖昧さを結び合わせる機能が両者に共通しているといえるでしょう。
このような開かれ・機能を指す語が、あらためていえば、冒頭に示された「passage」です。ただし、本章後半や次章で、へネップの「通過儀礼」概念に結び付けられるのは、やや牽強付会で批評性に乏しいと思います。
本章冒頭には、ここまでを踏まえた、インスタレーションの新たな定義づけが掲げられています。
インスタレーションという語はシステムを指す。つまり、インスタレーションは、インスタレーションについての言説を手段として用いることで、いまや言説的に制度づけられ定まったジャンルとして理解できるのだ。しかしこの語は、実践(praxis)をも指す。それは、あらゆるメディウムを同時に含み、また同時にコンセプチュアルかつ現象学的なアプローチを好んで用いる芸術的プロジェクトを作り出す、ひとつのやりかたである。そして最後に、この語は、世界のさまざまな地域で作られる、多くのスペシフィックで多様な芸術作品――つまり、物質的現象(material phenomenon)としてのインスタレーションを指す。こうして示されたのは、これら複数の意味は、同じものごとの側面だということだ。それらの関係は、たとえばシステムと実践、言説と現象とのあいだを鋭く区別することが無意味なほどに、密接なのだ。(ペーターセン)
第12章 エピローグ:歴史的な境界(Epilogue: A historical threshold)
本章はいわば英訳にあたって「増補」された部分だと思います。明確に記されてはいないのですが、デンマーク語の原著の刊行(2009)以降に発表された作品が参照されているためです(ほかの章にもあります)。
ざっくりと5つほどのテーマが概観されます。
まず、産業やテレコミュニケーションとの関係。第9章冒頭でも示唆しましたが、映像メディアや20世紀の電子メディアの広がり、ポスト産業社会、グローバリゼーション、「経験経済」などとインスタレーションとの関係がほのめかされます。
次に、「人類の脱中心化」。ビショップのインスタレーション論の中心には「主体の脱中心化(decentring)」概念があり、それに弁証法的に対置される「アクティベーション」へのビショップの偏重をペーターセンは批判していました。ペーターセンは「主体」というある種1990年代的な政治性を、2000年代以降の気候危機いわば「人新世」時代の政治的主体である「人類」に置き換えて「人類の脱中心化」というテーゼを置き、ドクメンタ13(2012)の作品、とくにテリケ・ハーポヤ《Closed Circuit - Open Duration》 に触れます。
に触れます。
三つ目は、「スペクタクル」。本書で論じてきた言説が、後期モダンと並走していたことを考えれば、ギー・ドゥボール的な「スペクタクル」への注目はさもありなんで、ブクローやポッツらの議論を参考に、インスタレーションもまたスペクタクル消費文化のもとで理解される性格をもつことを指摘します。特にローゼンタールやロダウェイを参照した、テーマパークとショッピングセンターとの関連性の示唆は面白く、たとえばクラインやカプロー、オルデンバーグらインスタレーションの新興期が、アナハイムのディズニーランドの開園(1955)や、最初の屋根つきショッピングセンターである「サウスデール・ショッピングセンター」の開館(1956)と同時期であることが紹介されます。
また、消費文化特有の受容のかたちとして、「観光」と並んで、映像の「ザッピング」や、商品にたいするある種の触覚的経験である「ショッピング」が挙げられます。前者は電子メディアとくにインターネットに結びつきます。加えて、昨今では「芸術的」インスタレーションと「商業的」インスタレーションの区別が難しいことを、草間彌生によるルイ・ヴィトンのコンセプトストアや、シャネルの2014A/Wコレクションショー、また家具メーカーの商品紹介のためのインスタレーション や、ジェシカ・ストックホルダー《Color Jam》(2012)
や、ジェシカ・ストックホルダー《Color Jam》(2012) などを挙げて指摘します。こうした「商品の空間化(spatialisation od the commodity)」の機能は、ジンメルやクラカウア、ベンヤミン、そしてシチュアシオニストらが指摘していた資本主義的なモードでしょう。
などを挙げて指摘します。こうした「商品の空間化(spatialisation od the commodity)」の機能は、ジンメルやクラカウア、ベンヤミン、そしてシチュアシオニストらが指摘していた資本主義的なモードでしょう。
最後に、上に挙げたザッピング的視線と結びつけて、ブラウジングつまり情報のナヴィゲーションという側面がインスタレーションに結びつけられます。そうした情報を管理・選別するモードが、レフ・マノヴィッチ『ニュー・メディアの言語』でいう「コンピューターの時代」を特徴づけています。「ナヴィゲーション可能な空間(navigable space)」(マノヴィッチ)の例として、データベースやハイパーテクスト、ないしヴィデオゲームが挙げられます。とはいえ「ナヴィゲーション可能な空間」は、コンピューターこそが完全なメディウムだったとはいえ、それ以前から存在する文化形式です。たとえば既に触れたカバコフの、物語的シークエンスを鑑賞者がナヴィゲーションしながら見出していくインスタレーションは、そのようなシステムを作り出しているでしょう。
このように、第9章で「ポストヒューマン」「デジタル・メディア」という語で扱っていたペーターセンの関心の2010年代的な延長として、この第12章はあるといえるでしょう。人新世という当時のホットワードに加え、携帯電話、GPS、自動車、ゲーム、シミュレーション、アニメーションの発展などの多様になったデジタル技術・表象への注目を促して、本章は締められます。最終節での総括は繰り返しになるので割愛します。
まとめ
以上見てきたように、本書は長大かつトピックが多岐にわたりながら、刊行時期や方針的にも総覧性のある、重要文献です。
全体をさらに要約するより、特徴として以下の3点を挙げてそれに代えます。
- ・パフォーマンスとの言説的・歴史的相互関係
- ・参加やその政治性を必ずしも偏重しないフラットな形式的分類
- ・身体に意味を、内部構造=空間に外部の場(またはネットワーク)をパフォーマティヴに結びつける、鑑賞者の演劇的コミットメント
こうした本書の性質から導かれた概念として、冒頭に挙げた「フィクション的空間」「パフォーマティヴなリアリズム」「ネットワーク化したサイト・スペシフィシティ」が確認できるでしょう。